凍った滝 [男と女ストーリー]
朝ご飯を食べていたら、タケオちゃんがやってきた。
「よう、みっちゃん、朝めし食ってるのかい?」
「見たらわかるでしょ」
「凍った滝を見に行こうよ。すっかり凍ってる。あんな滝はなかなか見られねえぞ」
「今年は寒いからね。そりゃ滝も凍るでしょ」
「なあ、早く行こうよ。昼になったら溶けちまうぞ」
タケオちゃんはしつこくて、あんまり急かすものだから仕方なく、みそ汁かけたご飯をかき込んで、タケオちゃんの軽トラに乗り込んだ。
タケオちゃんは幼なじみ。60年来の付き合いだ。
2年前に夫を亡くしてから、何かと理由をつけてやってくる。
心配してくれるのはありがたい。
子どもたちは都会にいるから頼れないし、男手が必要な時もある。
だけど幼なじみとはいえ男。ご近所の手前もあるし、あんまり甘えるのも悪い。
そう思いつつも、気楽なタケオちゃんといると楽しい。
朝の空気は寒いを通り越して、痛いほどの冷たさだ。
滝は見事に凍っている。
ドドドドと流れる音もなく、全ての時間が止まったように白く固まっていた。
「すごいだろ」
「そうね。だけどさ、滝はどんな気持ちだろうね」
「はあ? 滝の気持ち?」
「だってさ、ドドドと落ちるのが滝の醍醐味でしょ。それをあんな形で凍っちゃってさ、動きたくても動けないんだよ」
「ははは、みっちゃんは相変わらず面白いな」
私は凍った滝と自分を重ねていた。
夫がいたころはあんなに活動的だったのに、今じゃ料理を作るのも億劫になっている。
見事に凍った滝を見ても、以前ほどに心は動かない。
「なあ、みっちゃん、ずっと前、俺たちが若いころ、一緒に滝を見たの憶えてる?」
「ああ、そんなこともあったね」
「おれさ、あのとき、みっちゃんにプロポーズしたんだ。だけどさ、滝の音がうるさくて、俺の声が届かなくて、みっちゃんは何度も聞き返すし、何だか白けてやめちゃった」
「そうだったんだ。じゃああのとき滝が凍っていたら、人生変わっていたかもね」
「よく言うよ。都会から来た色男と、さっさと結婚したくせに」
「あはは、しょうがないよ。一目惚れだったんだもん」
本当は聞こえていた。タケオちゃんの声は滝より大きかったから。
だけど聞こえないふりをした。この人を、友達以上には思えなかったから。
タケオちゃんはそのあと、親が決めた人と見合い結婚をしたけれど、うまくいかなくて別れてしまった。
「なあ、みっちゃん、おれたち一緒にならないか? すぐにじゃなくていい。お互いひとりだし、年も取ったし、支え合って生きて行かないか?」
突然、タケオちゃんが大真面目な顔で言った。
困った。滝は凍って静かな朝だ。聞こえないふりができない。
「じゃあ……お友達から始めましょう」
「もう友達だべや。みっちゃん、相変わらず面白いなあ」
タケオちゃんが大笑いしてくれたから、ちょっと救われた。
私たち、一生涯の茶飲み友達でいましょうね。

にほんブログ村
「よう、みっちゃん、朝めし食ってるのかい?」
「見たらわかるでしょ」
「凍った滝を見に行こうよ。すっかり凍ってる。あんな滝はなかなか見られねえぞ」
「今年は寒いからね。そりゃ滝も凍るでしょ」
「なあ、早く行こうよ。昼になったら溶けちまうぞ」
タケオちゃんはしつこくて、あんまり急かすものだから仕方なく、みそ汁かけたご飯をかき込んで、タケオちゃんの軽トラに乗り込んだ。
タケオちゃんは幼なじみ。60年来の付き合いだ。
2年前に夫を亡くしてから、何かと理由をつけてやってくる。
心配してくれるのはありがたい。
子どもたちは都会にいるから頼れないし、男手が必要な時もある。
だけど幼なじみとはいえ男。ご近所の手前もあるし、あんまり甘えるのも悪い。
そう思いつつも、気楽なタケオちゃんといると楽しい。
朝の空気は寒いを通り越して、痛いほどの冷たさだ。
滝は見事に凍っている。
ドドドドと流れる音もなく、全ての時間が止まったように白く固まっていた。
「すごいだろ」
「そうね。だけどさ、滝はどんな気持ちだろうね」
「はあ? 滝の気持ち?」
「だってさ、ドドドと落ちるのが滝の醍醐味でしょ。それをあんな形で凍っちゃってさ、動きたくても動けないんだよ」
「ははは、みっちゃんは相変わらず面白いな」
私は凍った滝と自分を重ねていた。
夫がいたころはあんなに活動的だったのに、今じゃ料理を作るのも億劫になっている。
見事に凍った滝を見ても、以前ほどに心は動かない。
「なあ、みっちゃん、ずっと前、俺たちが若いころ、一緒に滝を見たの憶えてる?」
「ああ、そんなこともあったね」
「おれさ、あのとき、みっちゃんにプロポーズしたんだ。だけどさ、滝の音がうるさくて、俺の声が届かなくて、みっちゃんは何度も聞き返すし、何だか白けてやめちゃった」
「そうだったんだ。じゃああのとき滝が凍っていたら、人生変わっていたかもね」
「よく言うよ。都会から来た色男と、さっさと結婚したくせに」
「あはは、しょうがないよ。一目惚れだったんだもん」
本当は聞こえていた。タケオちゃんの声は滝より大きかったから。
だけど聞こえないふりをした。この人を、友達以上には思えなかったから。
タケオちゃんはそのあと、親が決めた人と見合い結婚をしたけれど、うまくいかなくて別れてしまった。
「なあ、みっちゃん、おれたち一緒にならないか? すぐにじゃなくていい。お互いひとりだし、年も取ったし、支え合って生きて行かないか?」
突然、タケオちゃんが大真面目な顔で言った。
困った。滝は凍って静かな朝だ。聞こえないふりができない。
「じゃあ……お友達から始めましょう」
「もう友達だべや。みっちゃん、相変わらず面白いなあ」
タケオちゃんが大笑いしてくれたから、ちょっと救われた。
私たち、一生涯の茶飲み友達でいましょうね。
にほんブログ村
氷の世界 [ミステリー?]
体中が凍えるほどの寒さよ。
いったいここはどこかしら?
そこはかとない冷気が、体中を包んで身動きもできないわ。
地球が氷河期になってしまったのかしら。
そうだ。これは夢なんだ。
だって私は、つい最近まで自由に動けたはずだもの。
急に氷河期が訪れたりしないわよね。
突然光が見えた。
私は、光の方向に歩いていく。
自分で歩いたのか、誰かに連れていかれたのか、頭がぼんやりしてよくわからない。
そこは温かかった。楽しそうな音楽も聞こえてくる。
湯気が立ち上り、全身がほぐれるような温かさ。
温泉だわ。温泉に入って、凍えた体をゆっくり温めたら、きっとまた動けるようになるはずよ。
私は服を脱いだ。
自分で脱いだのか、誰かに脱がされたのか、そんなことはどうでもいい。
冷え切った体を早く温めたい。
扉の向こうは温泉よ。芯まで温まるステキな温泉よ。
そのとき、目覚まし時計のような音がした。
うそでしょう。ここで目覚めるなんて。
私はどうにか温泉に入ろうと、扉を開けて転がるように外に出た。
寒い……。
温泉はなかった。そこはさっきよりもずっと寒い世界。
真っ白で、みんな凍って、もう生きることもままならない。
ああ、早く目が覚めて、温かい場所に行きたいわ。
***
彼女は、ウキウキしながらキッチンに立った。
今日は彼が来る日だから、張り切って料理を作ろう。
彼女は冷蔵庫からエビを取り出した。
彼の好物の「エビサラダ」を作るのだ。
彼女は鼻歌を歌いながら、鍋に湯を沸かし、取り出したエビの殻を丁寧に剥いた。
今は黒いけれど、湯に入れたらたちまちきれいなピンクになる。
そんな姿を想像しながら、彼女はエビを湯に入れようとつまみ上げた。
そのとき、電話が鳴った。
彼からの電話で、急な仕事で行けなくなったと告げた。
彼女は不機嫌になり、剥いたエビを放り投げ、パックに戻して冷凍庫に入れた。
次に彼が来る日まで、エビは冷凍保存となった。
***
ああ、そうだった。私、エビだった。
早く夢から覚めて、温かいインド洋で泳ぎたいわ。
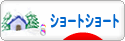
にほんブログ村
いったいここはどこかしら?
そこはかとない冷気が、体中を包んで身動きもできないわ。
地球が氷河期になってしまったのかしら。
そうだ。これは夢なんだ。
だって私は、つい最近まで自由に動けたはずだもの。
急に氷河期が訪れたりしないわよね。
突然光が見えた。
私は、光の方向に歩いていく。
自分で歩いたのか、誰かに連れていかれたのか、頭がぼんやりしてよくわからない。
そこは温かかった。楽しそうな音楽も聞こえてくる。
湯気が立ち上り、全身がほぐれるような温かさ。
温泉だわ。温泉に入って、凍えた体をゆっくり温めたら、きっとまた動けるようになるはずよ。
私は服を脱いだ。
自分で脱いだのか、誰かに脱がされたのか、そんなことはどうでもいい。
冷え切った体を早く温めたい。
扉の向こうは温泉よ。芯まで温まるステキな温泉よ。
そのとき、目覚まし時計のような音がした。
うそでしょう。ここで目覚めるなんて。
私はどうにか温泉に入ろうと、扉を開けて転がるように外に出た。
寒い……。
温泉はなかった。そこはさっきよりもずっと寒い世界。
真っ白で、みんな凍って、もう生きることもままならない。
ああ、早く目が覚めて、温かい場所に行きたいわ。
***
彼女は、ウキウキしながらキッチンに立った。
今日は彼が来る日だから、張り切って料理を作ろう。
彼女は冷蔵庫からエビを取り出した。
彼の好物の「エビサラダ」を作るのだ。
彼女は鼻歌を歌いながら、鍋に湯を沸かし、取り出したエビの殻を丁寧に剥いた。
今は黒いけれど、湯に入れたらたちまちきれいなピンクになる。
そんな姿を想像しながら、彼女はエビを湯に入れようとつまみ上げた。
そのとき、電話が鳴った。
彼からの電話で、急な仕事で行けなくなったと告げた。
彼女は不機嫌になり、剥いたエビを放り投げ、パックに戻して冷凍庫に入れた。
次に彼が来る日まで、エビは冷凍保存となった。
***
ああ、そうだった。私、エビだった。
早く夢から覚めて、温かいインド洋で泳ぎたいわ。
にほんブログ村
コインで決めよう
兄ちゃんは、何でもコインで決めた。
本屋の店先で、漫画雑誌をながめながら腕組みをする。
「ジャンプを買うか、サンデーを買うか」
そしてコインを投げて「表が出たらジャンプ、裏ならサンデー」
コインは、いつも兄ちゃんのポケットに入っていた。
自動販売機の前でも「表が出たらコーラ、裏ならポカリ」
算数の宿題も理科の宿題も、コインで答えを決めた。
「表ならA,裏ならB」
おじさんにもらった外国のコインは、兄ちゃんの宝物だった。
ある日、お父さんとお母さんが、神妙な顔で言った。
「お父さんとお母さんは、離婚することになった」
「ごめんね。離婚しても、あなたたちのお父さんとお母さんであることに変わりはないわ」
お母さんは、涙をこらえながら言った。
「でもね、これからは離れて暮らすしかないの。だからね、お父さんと暮らすか、お母さんと暮らすか、あなたたちが決めていいのよ」
僕たちは、うなだれながら部屋に帰った。
最近ケンカばかりしていたから、何となく予感はあったけど実感がわかない。
「兄ちゃん、どうする?」
長い沈黙の後、兄ちゃんはポケットからコインを取り出した。
「表が出たらお母さん、裏ならお父さん」
そう言って、天井めがけてコインを投げた。
いつもは難なく兄ちゃんの手の中に収まるコインが、手の平をはじいて床を転がり、タンスの裏側に入ってしまった。
「コインなんかで決めるなってことだよ」
埃だらけで輝きを失ったコインを見つめながら、僕はつぶやいた。
けっきょく、兄ちゃんはお父さんと、僕はお母さんと暮らすことになった。
お母さんの実家は栃木県の小さな町だ。お母さんと暮らすなら引っ越さなければならない。
友達が多いお兄ちゃんは、転校したくなかったのだと思う。
兄ちゃんが12歳、僕が10歳の春だった。
僕たちは、少しずつ大人になった。
いつでも会えると思った兄ちゃんとは、一度も会えないまま6年が過ぎた。
春が待ち遠しい2月の半ば、兄ちゃんからメールが来た。
『北海道の大学に行くことになった』
北海道? 東京が好きで離れたくなかった兄ちゃんが、北海道?
僕はどうしても、兄ちゃんに会いたくなった。
お年玉を使って上京した。久しぶりすぎて、すっかりよそ者だ。
兄ちゃんと待ち合わせたのはおしゃれなカフェ。
兄ちゃんはここでアルバイトをしていた。
マスターやバイト仲間に「こいつ、弟」と笑う顔は、昔のまま変わらない。
「兄ちゃん、どうして北海道なの? 東京に大学たくさんあるのに」
「コインで決めたんだ。表が東京、裏が北海道」
ポケットから例のコインを取り出して、兄ちゃんはへへっと笑った。
僕は知っている。
兄ちゃんは、大切なことをコインで決めたりしない。
東京へ行くことを告げると、お母さんは言った。
「お父さんは再婚して、新しい家族と暮らしているわ。家には行かないでね」
離婚してもお父さんだと言ったのに、まるで他人になってしまったみたいだ。
兄ちゃんは、家に居づらくなったのかな。
居場所を失くしてしまったのかな。
「ケーキ食べるか?」
兄ちゃんはコインを取り出して投げた。
「表ならチーズケーキ、裏ならモンブラン」
こんなくだらないことで時間が過ぎていくのが、なんだかとても嬉しかった。
僕たちにはこの先、コインで決められないようなことがたくさんあるだろう。
「兄ちゃん、お母さんのお土産、マカロンとバームクーヘンどっちがいいかな?」
「よし、コインで決めよう」

にほんブログ村
本屋の店先で、漫画雑誌をながめながら腕組みをする。
「ジャンプを買うか、サンデーを買うか」
そしてコインを投げて「表が出たらジャンプ、裏ならサンデー」
コインは、いつも兄ちゃんのポケットに入っていた。
自動販売機の前でも「表が出たらコーラ、裏ならポカリ」
算数の宿題も理科の宿題も、コインで答えを決めた。
「表ならA,裏ならB」
おじさんにもらった外国のコインは、兄ちゃんの宝物だった。
ある日、お父さんとお母さんが、神妙な顔で言った。
「お父さんとお母さんは、離婚することになった」
「ごめんね。離婚しても、あなたたちのお父さんとお母さんであることに変わりはないわ」
お母さんは、涙をこらえながら言った。
「でもね、これからは離れて暮らすしかないの。だからね、お父さんと暮らすか、お母さんと暮らすか、あなたたちが決めていいのよ」
僕たちは、うなだれながら部屋に帰った。
最近ケンカばかりしていたから、何となく予感はあったけど実感がわかない。
「兄ちゃん、どうする?」
長い沈黙の後、兄ちゃんはポケットからコインを取り出した。
「表が出たらお母さん、裏ならお父さん」
そう言って、天井めがけてコインを投げた。
いつもは難なく兄ちゃんの手の中に収まるコインが、手の平をはじいて床を転がり、タンスの裏側に入ってしまった。
「コインなんかで決めるなってことだよ」
埃だらけで輝きを失ったコインを見つめながら、僕はつぶやいた。
けっきょく、兄ちゃんはお父さんと、僕はお母さんと暮らすことになった。
お母さんの実家は栃木県の小さな町だ。お母さんと暮らすなら引っ越さなければならない。
友達が多いお兄ちゃんは、転校したくなかったのだと思う。
兄ちゃんが12歳、僕が10歳の春だった。
僕たちは、少しずつ大人になった。
いつでも会えると思った兄ちゃんとは、一度も会えないまま6年が過ぎた。
春が待ち遠しい2月の半ば、兄ちゃんからメールが来た。
『北海道の大学に行くことになった』
北海道? 東京が好きで離れたくなかった兄ちゃんが、北海道?
僕はどうしても、兄ちゃんに会いたくなった。
お年玉を使って上京した。久しぶりすぎて、すっかりよそ者だ。
兄ちゃんと待ち合わせたのはおしゃれなカフェ。
兄ちゃんはここでアルバイトをしていた。
マスターやバイト仲間に「こいつ、弟」と笑う顔は、昔のまま変わらない。
「兄ちゃん、どうして北海道なの? 東京に大学たくさんあるのに」
「コインで決めたんだ。表が東京、裏が北海道」
ポケットから例のコインを取り出して、兄ちゃんはへへっと笑った。
僕は知っている。
兄ちゃんは、大切なことをコインで決めたりしない。
東京へ行くことを告げると、お母さんは言った。
「お父さんは再婚して、新しい家族と暮らしているわ。家には行かないでね」
離婚してもお父さんだと言ったのに、まるで他人になってしまったみたいだ。
兄ちゃんは、家に居づらくなったのかな。
居場所を失くしてしまったのかな。
「ケーキ食べるか?」
兄ちゃんはコインを取り出して投げた。
「表ならチーズケーキ、裏ならモンブラン」
こんなくだらないことで時間が過ぎていくのが、なんだかとても嬉しかった。
僕たちにはこの先、コインで決められないようなことがたくさんあるだろう。
「兄ちゃん、お母さんのお土産、マカロンとバームクーヘンどっちがいいかな?」
「よし、コインで決めよう」
にほんブログ村
夢から覚めた夢 [公募]
夢から覚めたとき、人は二通りの反応をする。
それがいい夢だったときは「何だ、夢か」とがっかりして、悪い夢だったら「夢でよかった」とホッとする。
つまり、見た夢と現実の反応は、真逆である。
なぜそんな話になったのかは忘れたが、目の前の武田君はAランチのコロッケをほおばりながら、「景子さん、哲学者っすか?」と、相変わらず軽い口調で言った。
武田君と私は、事務用品を販売する会社で経理の仕事をしている。
男のくせにおしゃべりで気さくな彼を、私はよくランチに誘う。
「俺、夢ってあんまり見ないんですよね」
「私はね、時々思うの。今生きている世界が、全部夢だったら……ってね」
「景子さん、詩人っすか?」
翌日、武田君が私の顔を見るなり「見ましたよ、夢」と興奮した様子で言ってきた。
「目が覚めたら、この会社に入社したことも、景子さんとランチを食べたことも、全部夢だったと気づくんですよ。うわ~、マジか~って、落ち込んでいたら、そこでまた目が覚めて、全部夢だったのが夢だったという二段落ち。いやあ、焦りましたよ。景子さんが昨日あんな話をするからですよ」
「それで、武田君の反応は?」
「もちろん、夢でよかったと思いましたよ。だってこの会社に入って景子さんと出会って、一緒にランチしたことが全部夢だったなんて、悲しすぎますよ」
武田君は子供みたいに口を尖らせた。素直な反応に、少し後ろめたい気持ちになる。
私は、今生きている世界が夢だったら、どんなにいいだろうと思っている。
彼を亡くした三年前から、何度も何度も想像してきた。
朝目覚めると、そこは私たちが一緒に暮らすはずだったマンションで、となりには寝ぼけ眼の彼がいて、「ああ、そうか。私は長い夢を見ていたんだ。彼がこの世からいなくなるという、悲しい夢を見ていたんだ」と気づく。
ふたりで選んだ水色のカーテンを開けて、私はすべての光に感謝する。
「ああ、夢でよかった」
彼は同じ会社の同期で、営業の仕事をしていた。
恋に落ちて、結婚の約束をして、ひと月後にはチャペルの鐘を鳴らすはずだった。
だけど彼は、仕事中に突然倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまった。
私は何度も自分に言い聞かせた。
「夢だ。これは悪い夢だ」
だけど現実は、私を置き去りにして過ぎていく。
会社の同僚たちは、はれ物に触るように私に接した。
社内恋愛の噂や合コンの相談など、私が行くとピタリと話をやめた。
重い空気が流れるフロアに、新入社員の武田君が来た。
何の事情も知らない武田君は、「景子さん、彼氏いないんですか。俺、立候補しようかな」などと言って周りを凍りつかせたが、私はそんな彼に救われた。
その日は月末で忙しく、家に着くなりソファーに倒れ込んだ。
ほんの数分だけと思いながら、私は深い眠りに落ちた。
「景子、景子」と呼ぶ声に目を覚まし、貼り付いた瞼をはがして目を開けると、目の前に彼がいた。
「そんなところで寝たら風邪をひくよ」
私はゆっくり起き上がる。
「夢を見ていたわ。すごく長い夢」
「へえ、どんな夢?」
「あなたが死んじゃう夢。あなたが死んでも、私は変わらずあの会社で働いていて、武田君という後輩が出来て、いっしょにランチをしながら、くだらない話をしているの」
「へえ、どんな話?」
「面接の失敗談とか。武田君、私服OKの面接に、アロハシャツを着て行ったんだって。ハワイでは正装だからって。バカでしょう」
「楽しそうだね。景子、もしかして、職場に復帰したいの?」
「まさか。私はこの部屋であなたの帰りを待っているのが幸せなの」
私は立ちあがり、彼に触れようと手をのばす。だけど何故かその手は宙を抱く。
薄暗い部屋の中、彼はもう、どこにもいない。
真夜中に目が覚めた。やっぱり夢だった。
私はのろのろと立ちあがり、洗面所で顔を洗った。
鏡に映った自分に問いかける。
「何だ、夢か」とがっかりしたか、「夢でよかった」とホッとしたか。
不思議なことに、私はホッとしていた。
そんなはずはないと否定してみても、心の奥が「夢でよかった」と安堵している。
「しょうがないっすよ。景子さんは生きてるんだから」
どこからか、武田君の声が聞こえたような気がした。
相変わらず軽いなあと思いながら、ひとりで笑った。
*****
公募ガイド「TO-BE小説工房」で落選だったものです。
課題は「夢」でした。
最優秀作を読むと、さりげなく「夢」を入れていたので、そういう方がいいのかな~と思ったり。
今月の課題は「運」です。
うーん(ダジャレ?)こういう課題って、却って難しいんですよね。

にほんブログ村
それがいい夢だったときは「何だ、夢か」とがっかりして、悪い夢だったら「夢でよかった」とホッとする。
つまり、見た夢と現実の反応は、真逆である。
なぜそんな話になったのかは忘れたが、目の前の武田君はAランチのコロッケをほおばりながら、「景子さん、哲学者っすか?」と、相変わらず軽い口調で言った。
武田君と私は、事務用品を販売する会社で経理の仕事をしている。
男のくせにおしゃべりで気さくな彼を、私はよくランチに誘う。
「俺、夢ってあんまり見ないんですよね」
「私はね、時々思うの。今生きている世界が、全部夢だったら……ってね」
「景子さん、詩人っすか?」
翌日、武田君が私の顔を見るなり「見ましたよ、夢」と興奮した様子で言ってきた。
「目が覚めたら、この会社に入社したことも、景子さんとランチを食べたことも、全部夢だったと気づくんですよ。うわ~、マジか~って、落ち込んでいたら、そこでまた目が覚めて、全部夢だったのが夢だったという二段落ち。いやあ、焦りましたよ。景子さんが昨日あんな話をするからですよ」
「それで、武田君の反応は?」
「もちろん、夢でよかったと思いましたよ。だってこの会社に入って景子さんと出会って、一緒にランチしたことが全部夢だったなんて、悲しすぎますよ」
武田君は子供みたいに口を尖らせた。素直な反応に、少し後ろめたい気持ちになる。
私は、今生きている世界が夢だったら、どんなにいいだろうと思っている。
彼を亡くした三年前から、何度も何度も想像してきた。
朝目覚めると、そこは私たちが一緒に暮らすはずだったマンションで、となりには寝ぼけ眼の彼がいて、「ああ、そうか。私は長い夢を見ていたんだ。彼がこの世からいなくなるという、悲しい夢を見ていたんだ」と気づく。
ふたりで選んだ水色のカーテンを開けて、私はすべての光に感謝する。
「ああ、夢でよかった」
彼は同じ会社の同期で、営業の仕事をしていた。
恋に落ちて、結婚の約束をして、ひと月後にはチャペルの鐘を鳴らすはずだった。
だけど彼は、仕事中に突然倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまった。
私は何度も自分に言い聞かせた。
「夢だ。これは悪い夢だ」
だけど現実は、私を置き去りにして過ぎていく。
会社の同僚たちは、はれ物に触るように私に接した。
社内恋愛の噂や合コンの相談など、私が行くとピタリと話をやめた。
重い空気が流れるフロアに、新入社員の武田君が来た。
何の事情も知らない武田君は、「景子さん、彼氏いないんですか。俺、立候補しようかな」などと言って周りを凍りつかせたが、私はそんな彼に救われた。
その日は月末で忙しく、家に着くなりソファーに倒れ込んだ。
ほんの数分だけと思いながら、私は深い眠りに落ちた。
「景子、景子」と呼ぶ声に目を覚まし、貼り付いた瞼をはがして目を開けると、目の前に彼がいた。
「そんなところで寝たら風邪をひくよ」
私はゆっくり起き上がる。
「夢を見ていたわ。すごく長い夢」
「へえ、どんな夢?」
「あなたが死んじゃう夢。あなたが死んでも、私は変わらずあの会社で働いていて、武田君という後輩が出来て、いっしょにランチをしながら、くだらない話をしているの」
「へえ、どんな話?」
「面接の失敗談とか。武田君、私服OKの面接に、アロハシャツを着て行ったんだって。ハワイでは正装だからって。バカでしょう」
「楽しそうだね。景子、もしかして、職場に復帰したいの?」
「まさか。私はこの部屋であなたの帰りを待っているのが幸せなの」
私は立ちあがり、彼に触れようと手をのばす。だけど何故かその手は宙を抱く。
薄暗い部屋の中、彼はもう、どこにもいない。
真夜中に目が覚めた。やっぱり夢だった。
私はのろのろと立ちあがり、洗面所で顔を洗った。
鏡に映った自分に問いかける。
「何だ、夢か」とがっかりしたか、「夢でよかった」とホッとしたか。
不思議なことに、私はホッとしていた。
そんなはずはないと否定してみても、心の奥が「夢でよかった」と安堵している。
「しょうがないっすよ。景子さんは生きてるんだから」
どこからか、武田君の声が聞こえたような気がした。
相変わらず軽いなあと思いながら、ひとりで笑った。
*****
公募ガイド「TO-BE小説工房」で落選だったものです。
課題は「夢」でした。
最優秀作を読むと、さりげなく「夢」を入れていたので、そういう方がいいのかな~と思ったり。
今月の課題は「運」です。
うーん(ダジャレ?)こういう課題って、却って難しいんですよね。
にほんブログ村
20歳の俺へ [ファンタジー]
グダグダと過ごす正月休み。
真夜中に白い服の妖精が現れて、年賀はがきとペンを俺に渡した。
「このはがきで、30年前の自分に年賀状を送りなさい」
「30年前? 俺は20歳だ」
「20歳の自分に伝えたいことを書いて送りなさい。あなたの未来は、きっと変わります」
「本当に届くの?」
「はい。ただし伝えたいことは、このペンを使って書いてください。このペンで書いた文字は、30年前のあなたにしか読めません。そしてその文字は、読み終えるとすぐに消えてしまいます」
「へえ」
半信半疑でペンをながめていたら、妖精は消えていた。
夢かと思ったけれど、翌朝になっても年賀はがきとペンは消えていなかった。
20歳の自分に伝えたいことを、俺は考えた。
あの頃の俺は、本当にダメだった。大学の授業はさぼってばかりでついに留年。
結局卒業できずにやめてしまった。
「ちゃんとしろ。今のままではおまえは高卒だ」
まずはこれを伝えよう。
しかしそれより大切なことがある。健康だ。
38歳で暴飲暴食がたたって胃潰瘍になる。入院している間に出世コースから外れる。
「酒はほどほどに。タバコも吸うな。腹八分目を心がけろ」
そんなこと、20歳の俺に通じるかな?
やはり心残りは親のことだ。親孝行もしないまま、両親はあの世へ旅立った。
孫の顔も嫁の顔も見せることが出来なかった。
そうだ、最も伝えたいのは女のことだ。
「25歳で知り合うホステスのアケミはやめておけ。バックにやくざがついている。逆に同時期に出逢うマサヨは地味だけど、実は財閥の娘だ」
地味でさえないマサヨをあっさり振ったことを、どれだけ後悔したかわからない。
マサヨと結婚していたら、今ごろ社長になっていたかもしれない。
俺は長い正月休み中に、腕組みをしてはがきとにらめっこした。
ブルーのインクは、書いているうちに消えてしまうんじゃないかと思うほど薄かった。
まあ、20歳の俺は老眼とは無縁だから読めるだろう。
あの頃の俺は、集中力がなくてろくに本も読まず、読解力はゼロに近い。
だからなるべくわかりやすく簡潔に、難しい漢字は避けて慎重にペンを進めた。
書き終えると、ペンは煙のように消えてしまった。
そして正月休み最後の成人の日、記憶をたどってあの頃の住所を書き、願いを込めてはがきをポストに投函した。
このはがきを20歳の俺が受け取ったなら、俺の未来は変わるはずだ。
マサヨと結婚して、大会社の社長もしくは副社長くらいになっているかも。
親父とお袋に、孫を抱かせてやれたかも。
いつ届くのだろう。時空を超えるのだから、簡単ではないだろう。
いずれにしても、来年の正月は、安アパートでグダグダ過ごすことをないだろう。
そんな未来を夢見た翌日、ポストにはがきが届いた。
昨日出したはずの年賀はがきだ。
えっ? なんで?
はがきには、郵便局の張り紙が……。
『料金不足です。10円切手を貼ってください』
52円で年賀状を出せるのは、1月7日までだった。

にほんブログ村
真夜中に白い服の妖精が現れて、年賀はがきとペンを俺に渡した。
「このはがきで、30年前の自分に年賀状を送りなさい」
「30年前? 俺は20歳だ」
「20歳の自分に伝えたいことを書いて送りなさい。あなたの未来は、きっと変わります」
「本当に届くの?」
「はい。ただし伝えたいことは、このペンを使って書いてください。このペンで書いた文字は、30年前のあなたにしか読めません。そしてその文字は、読み終えるとすぐに消えてしまいます」
「へえ」
半信半疑でペンをながめていたら、妖精は消えていた。
夢かと思ったけれど、翌朝になっても年賀はがきとペンは消えていなかった。
20歳の自分に伝えたいことを、俺は考えた。
あの頃の俺は、本当にダメだった。大学の授業はさぼってばかりでついに留年。
結局卒業できずにやめてしまった。
「ちゃんとしろ。今のままではおまえは高卒だ」
まずはこれを伝えよう。
しかしそれより大切なことがある。健康だ。
38歳で暴飲暴食がたたって胃潰瘍になる。入院している間に出世コースから外れる。
「酒はほどほどに。タバコも吸うな。腹八分目を心がけろ」
そんなこと、20歳の俺に通じるかな?
やはり心残りは親のことだ。親孝行もしないまま、両親はあの世へ旅立った。
孫の顔も嫁の顔も見せることが出来なかった。
そうだ、最も伝えたいのは女のことだ。
「25歳で知り合うホステスのアケミはやめておけ。バックにやくざがついている。逆に同時期に出逢うマサヨは地味だけど、実は財閥の娘だ」
地味でさえないマサヨをあっさり振ったことを、どれだけ後悔したかわからない。
マサヨと結婚していたら、今ごろ社長になっていたかもしれない。
俺は長い正月休み中に、腕組みをしてはがきとにらめっこした。
ブルーのインクは、書いているうちに消えてしまうんじゃないかと思うほど薄かった。
まあ、20歳の俺は老眼とは無縁だから読めるだろう。
あの頃の俺は、集中力がなくてろくに本も読まず、読解力はゼロに近い。
だからなるべくわかりやすく簡潔に、難しい漢字は避けて慎重にペンを進めた。
書き終えると、ペンは煙のように消えてしまった。
そして正月休み最後の成人の日、記憶をたどってあの頃の住所を書き、願いを込めてはがきをポストに投函した。
このはがきを20歳の俺が受け取ったなら、俺の未来は変わるはずだ。
マサヨと結婚して、大会社の社長もしくは副社長くらいになっているかも。
親父とお袋に、孫を抱かせてやれたかも。
いつ届くのだろう。時空を超えるのだから、簡単ではないだろう。
いずれにしても、来年の正月は、安アパートでグダグダ過ごすことをないだろう。
そんな未来を夢見た翌日、ポストにはがきが届いた。
昨日出したはずの年賀はがきだ。
えっ? なんで?
はがきには、郵便局の張り紙が……。
『料金不足です。10円切手を貼ってください』
52円で年賀状を出せるのは、1月7日までだった。
にほんブログ村
初詣・初デート [コメディー]
今年の正月は、愛に満ち溢れている。
14歳にして初めてできた彼女と、初詣デート。
幸せすぎる。
さらば家族団らんの正月よ。僕は大人への階段を一段昇るのだ。
「お母さん、おれ、雑煮食べたら出かけるから」
「あら、初詣? だったらアイコも連れて行ってよ。ひとりで行くって朝から騒いでいるのよ。さすがにひとりじゃ危ないでしょ。だからお兄ちゃん、連れてってあげて」
アイコは小学生の妹だ。
妹連れの初デートなんて、シャレにならない。
「いやだよ。おれ、友達と一緒だもん」
「どうせ鈴木君たちでしょ。いいじゃないの。連れて行ってよ。それとも何? 親に言えない友達なの?」
鋭い目で、母が僕の目をのぞきこむ。
「わかったよ。連れて行くよ」
アイコのやつ、どうせ露店が目的なんだろう。
チョコバナナでも買って先に帰せばいいか。
僕はアイコを連れてしぶしぶ家を出た。
「ねえねえお兄ちゃん、お年玉いくらもらった?」
「教えねえ」
「ねえねえお兄ちゃん、おもち何個食べた」
「3こ」
「ねえねえお兄ちゃん、年賀状何枚きた? アイコは15枚」
「数えてねえし」
「ねえねえお兄ちゃん、冬休みの宿題やった?」
「やってねえ」
「勝った! アイコはあと書初めだけ」
妹よ。お兄ちゃんはもう、そんな低レベルな勝ち負けに興味はないのだよ。
純粋無垢で無邪気なおまえが羨ましいよ。
お兄ちゃんはもう、子供じゃないからな。
「ねえねえお兄ちゃん、恋って切ないよね」
「はっ?」
「ねえねえお兄ちゃん、恋すると、秘密が増えるよね」
「はあ?」
「ねえねえお兄ちゃん、恋すると、心の中に違う自分が生まれるよね」
「なになに?」
「お兄ちゃん、じつはわたし、今日デートなの。だからお兄ちゃん、神社に着いたら別行動してほしいの。お母さんとお父さんにはナイショね」
「えっ? ちょっと待て」
「お年玉でチョコバナナ買ってあげるから、お願い」
「デ、デートって、おまえ。誰と?」
「ひとつ上の6年生。優しくてイケメンなの。お母さんには言えないから、お兄ちゃんをダシに使っちゃった。へへ」
いや、あの、別行動は願ったりかなったりのはずなんだけど、なんだこのモヤモヤは。
ああ、もうすぐ神社に着いてしまう。
初デートだけど、楽しみにしていた初デートだけどさ……。
「あのさ、アイコ、今日、ダブルデートしよ」
*******
みなさま、お正月いかがお過ごしですか。
今年もこんな感じでやっていきます。
どうかよろしくお願いします。


にほんブログ村
14歳にして初めてできた彼女と、初詣デート。
幸せすぎる。
さらば家族団らんの正月よ。僕は大人への階段を一段昇るのだ。
「お母さん、おれ、雑煮食べたら出かけるから」
「あら、初詣? だったらアイコも連れて行ってよ。ひとりで行くって朝から騒いでいるのよ。さすがにひとりじゃ危ないでしょ。だからお兄ちゃん、連れてってあげて」
アイコは小学生の妹だ。
妹連れの初デートなんて、シャレにならない。
「いやだよ。おれ、友達と一緒だもん」
「どうせ鈴木君たちでしょ。いいじゃないの。連れて行ってよ。それとも何? 親に言えない友達なの?」
鋭い目で、母が僕の目をのぞきこむ。
「わかったよ。連れて行くよ」
アイコのやつ、どうせ露店が目的なんだろう。
チョコバナナでも買って先に帰せばいいか。
僕はアイコを連れてしぶしぶ家を出た。
「ねえねえお兄ちゃん、お年玉いくらもらった?」
「教えねえ」
「ねえねえお兄ちゃん、おもち何個食べた」
「3こ」
「ねえねえお兄ちゃん、年賀状何枚きた? アイコは15枚」
「数えてねえし」
「ねえねえお兄ちゃん、冬休みの宿題やった?」
「やってねえ」
「勝った! アイコはあと書初めだけ」
妹よ。お兄ちゃんはもう、そんな低レベルな勝ち負けに興味はないのだよ。
純粋無垢で無邪気なおまえが羨ましいよ。
お兄ちゃんはもう、子供じゃないからな。
「ねえねえお兄ちゃん、恋って切ないよね」
「はっ?」
「ねえねえお兄ちゃん、恋すると、秘密が増えるよね」
「はあ?」
「ねえねえお兄ちゃん、恋すると、心の中に違う自分が生まれるよね」
「なになに?」
「お兄ちゃん、じつはわたし、今日デートなの。だからお兄ちゃん、神社に着いたら別行動してほしいの。お母さんとお父さんにはナイショね」
「えっ? ちょっと待て」
「お年玉でチョコバナナ買ってあげるから、お願い」
「デ、デートって、おまえ。誰と?」
「ひとつ上の6年生。優しくてイケメンなの。お母さんには言えないから、お兄ちゃんをダシに使っちゃった。へへ」
いや、あの、別行動は願ったりかなったりのはずなんだけど、なんだこのモヤモヤは。
ああ、もうすぐ神社に着いてしまう。
初デートだけど、楽しみにしていた初デートだけどさ……。
「あのさ、アイコ、今日、ダブルデートしよ」
*******
みなさま、お正月いかがお過ごしですか。
今年もこんな感じでやっていきます。
どうかよろしくお願いします。
にほんブログ村



