生涯現役時代 [SF]
80歳を過ぎると、若い頃のことばかり思い出す。
私はとにかく働いた。
家族のため、子どもにいい教育を受けさせるため、家族が少しでも裕福な暮らしをするため、長期の休暇に、家族で旅行に行くため。
時代は変わった。
昔のように組織の中で働く人はもういない。
定年制度も昇給もない。
ただ与えられた仕事をして、働いた分の報酬をもらう。
報酬は金ではなく、食料や必要物資だ。
そう、誰もが平等に、死ぬまで働く。
妻を亡くした後、私は施設で暮らしている。
施設といっても、誰かに世話をしてもらうわけではない。
私は元気だ。ちゃんと仕事をしている。
仕事は、書類にナンバーをスタンプする仕事だ。
それが何に使われるのか、何のためのナンバーなのか分からない。
知る必要はない。ただ、年老いた私にできる仕事をこなすだけだ。
「スズキさん、今日からB施設に行ってください」
新しい職場だ。
「どんな仕事だね?」
「簡単な仕事です。書類をシュレッターにかけるだけです。さあどうぞ」
B施設に行くと、たくさんの老人が黙々とシュレッターをかけている。
私は与えられたブースで書類を手に取った。
外に漏れてはいけない機密文書かと思ったが、ちがった。
それは、私がきのう、ひたすらナンバーをスタンプした書類だった。
私は、自分がきのう1日かけて行った仕事をすべて粉々にしたのだ。
どういうことだ?
私は、何だかモヤモヤして、仕事帰りに娯楽施設に行った。
娯楽施設は、5時から8時まで開放される唯一の酒場だ。
「私は何のために仕事をしているんだろう」
となりに座った男に話しかけた。
「仕事に不満が?」
「不満はないよ。80を過ぎても健康で働けるのは幸せなことだ」
「それなら余計なことは考えない方がいいですよ」
「しかし、意味のないことをしている気がして仕方ない」
男は笑った。
「意味なんかないですよ。私たちはまるで生産性のない仕事をしています」
「どういうことだ?」
「あなたが飲んでいる酒は、AIによって造られています。食べ物も、服も靴も、建物も電気製品もすべてそうです。人間はもう、働かなくていいんですよ」
周りを見ると、機械がカクテルを作り、機械が運び、機械が調理をしている。
そうだ。もう何十年も前から、人間の仕事はすべてAIに奪われた。
「では、私たちは何のために意味のない仕事をするんだ」
「決まっているでしょう。AIたちの士気を上げるためですよ。AIは人間のため、人間が元気で暮らすために造られたのです。人間が生きる気力を失ったら、AIの士気も下がってしまいます」
AIは人間のために働き、人間はAIのために働く。
私は今日も、誰かが1日かけて行った仕事をシュレッターにかける。
粉々になった紙はAIによって再生され、また書類になってナンバーを押されるのだ。
意味はある。少なくとも私の、生きる気力になっている。
私はとにかく働いた。
家族のため、子どもにいい教育を受けさせるため、家族が少しでも裕福な暮らしをするため、長期の休暇に、家族で旅行に行くため。
時代は変わった。
昔のように組織の中で働く人はもういない。
定年制度も昇給もない。
ただ与えられた仕事をして、働いた分の報酬をもらう。
報酬は金ではなく、食料や必要物資だ。
そう、誰もが平等に、死ぬまで働く。
妻を亡くした後、私は施設で暮らしている。
施設といっても、誰かに世話をしてもらうわけではない。
私は元気だ。ちゃんと仕事をしている。
仕事は、書類にナンバーをスタンプする仕事だ。
それが何に使われるのか、何のためのナンバーなのか分からない。
知る必要はない。ただ、年老いた私にできる仕事をこなすだけだ。
「スズキさん、今日からB施設に行ってください」
新しい職場だ。
「どんな仕事だね?」
「簡単な仕事です。書類をシュレッターにかけるだけです。さあどうぞ」
B施設に行くと、たくさんの老人が黙々とシュレッターをかけている。
私は与えられたブースで書類を手に取った。
外に漏れてはいけない機密文書かと思ったが、ちがった。
それは、私がきのう、ひたすらナンバーをスタンプした書類だった。
私は、自分がきのう1日かけて行った仕事をすべて粉々にしたのだ。
どういうことだ?
私は、何だかモヤモヤして、仕事帰りに娯楽施設に行った。
娯楽施設は、5時から8時まで開放される唯一の酒場だ。
「私は何のために仕事をしているんだろう」
となりに座った男に話しかけた。
「仕事に不満が?」
「不満はないよ。80を過ぎても健康で働けるのは幸せなことだ」
「それなら余計なことは考えない方がいいですよ」
「しかし、意味のないことをしている気がして仕方ない」
男は笑った。
「意味なんかないですよ。私たちはまるで生産性のない仕事をしています」
「どういうことだ?」
「あなたが飲んでいる酒は、AIによって造られています。食べ物も、服も靴も、建物も電気製品もすべてそうです。人間はもう、働かなくていいんですよ」
周りを見ると、機械がカクテルを作り、機械が運び、機械が調理をしている。
そうだ。もう何十年も前から、人間の仕事はすべてAIに奪われた。
「では、私たちは何のために意味のない仕事をするんだ」
「決まっているでしょう。AIたちの士気を上げるためですよ。AIは人間のため、人間が元気で暮らすために造られたのです。人間が生きる気力を失ったら、AIの士気も下がってしまいます」
AIは人間のために働き、人間はAIのために働く。
私は今日も、誰かが1日かけて行った仕事をシュレッターにかける。
粉々になった紙はAIによって再生され、また書類になってナンバーを押されるのだ。
意味はある。少なくとも私の、生きる気力になっている。
ディナー [SF]
私の彼は、深い緑色の目をしている。背が高くて、誰もが振り向く異次元の美青年。
家族と一緒に日本に移住して一年になる。
道に迷った彼を助けた縁で、交際が始まった。
素敵な人だけど、たった一つ難点がある。
彼とは、食の好みが全く合わないのだ。だから一緒に食事をしたことがない。
外国人だから、私たちの食事は口に合わないのだろう。
食事時には必ず家に帰るので、デートの時間はせいぜい4,5時間だ。
私は、思い切って言ってみた。
「あなたと一緒に食事がしたいの。あなたと同じものを私も食べるから、家に招待してくれないかしら」
「本当にいいのかい? 僕たちの食事は、きっと君の口には合わないよ」
「いいの。あなたが好きなものは、私も好きになりたいの」
「ありがとう菜々子。今夜母さんにご馳走を作ってもらうよ」
緊張しながら、彼の家に行った。
彼の両親と高校生の妹が、流暢な日本語で私を歓迎してくれた。
「まあ菜々子さん、なんて可愛らしいお嬢さんかしら。お会い出来て嬉しいわ」
「お兄ちゃんにはもったいないね」
無口で厳格なお父さん、明るくて優しいお母さん、可愛い妹。絵にかいたような素敵な家族だ。
「さあ、お夕食にしましょう。今日はご馳走よ」
笑いながらキッチンに消えた母親は、ダイニングテーブルに次々料理を並べていった。
「さあ、みんな席について」
母親の料理は、高級料亭の懐石料理のようにきれいだった。
見た目は日本食と変わらない。きっと味が違うのだ。
「今日はご馳走だよ」と、彼が椅子をすすめてくれた。
「ねえ菜々子さん、この白いの、何だと思う?」
母親が得意げに手前の小鉢を指さした。白和えみたいだ。
「お豆腐……ですか」
「やだ、違うわよ。私たちは豆腐なんて食べないわ。ふふふ、これはね、骨なのよ」
「骨?」
「そう、骨をね、細かく砕いて煮込んだの」
「手間がかかった料理なんだよ」と、彼が自慢げに言った。
「あの、何の骨ですか?」
私が訊くと、母親は首を傾げた。なぜそんな質問を?と思っているようだ。
「人間よ」
「えっ、人間の骨?」
「そうよ。骨は食べたことがないかしら? 人間は捨てるところがないって言うでしょ。骨だって爪だって食べられるのよ。ああ、安心して。これはちゃんと養殖された人間よ。正規なルートで仕入れた安全な食材だから」
何を言っているのだろう。悪い冗談か?
心なしかどれも人間の部位に見えてきた。気持ちが悪い。
「お口に合わないかしら」
「母さん、先住民には人間を食べる習慣がないんだよ。だってそうだろう。まるで共食いだ」
「まあ、菜々子さんは先住民なの? そうよね。ここは数少ない保護地区ですものね」
「あの、ちょっと待って。先住民って、何?」
彼が、憐れむように私を見た。
「君は何も知らないんだね。地球にはもう、純粋な人間は数えるほどしかいない。なぜなら僕たちの先祖が捕獲して食べてしまったからだ。でもね、僕たちはそんなことはしない。先住民を保護して、無意味な狩りを防ぐために地球に派遣されたんだ」
頭が混乱している。彼は宇宙人なの?
私は生まれたときから人間だ。この町で、何不自由なく暮らしてきた。
先住民? 保護地区? 全く訳が分からない。
動悸がして、大量の汗が流れた。
「菜々子さん、何だかおいしそうな匂いがする」
妹が鼻をひくひくさせて言った。
「本当ね。肉汁が溢れてる。ああ、やっぱり天然物は違うわ」
違う。汗です。これは汗です。ああ、拭っても、拭っても汗が出る。
そこで一度も言葉を発していない父親が、初めて口を開いた。
「野生の人間、食ってみたい」
ごくりと唾を呑み込んで、みんながいっせいに私を見た。
「そうね。一人くらい、いいんじゃない?」
ひええ、私は小さく叫びながら、椅子ごと後ろに転げ落ちた。
気がついたら、ベッドで寝ていた。
「気がついた?」
彼が優しく私の髪を撫でた。ああ、やっぱり悪い冗談だった。
「驚かせてごめん。スーパーで、君たちの食べ物を買ってきたよ」
彼は、おにぎりとインスタントのスープを運んでくれた。
「ありがとう。すごくおいしい」
「よかった。たくさん食べてね」
「私、本当に、あなたの家族に食べられてしまうのかと思ったわ」
「ははは、大丈夫だよ。安心してたくさん食べて。もっと太った方がおいしい……いや、可愛いからさ」
ん??
****
村田紗耶香さんばかり読んでいたころに書いたものです。
影響されてるな~(笑)
これって、SF?ホラー?
家族と一緒に日本に移住して一年になる。
道に迷った彼を助けた縁で、交際が始まった。
素敵な人だけど、たった一つ難点がある。
彼とは、食の好みが全く合わないのだ。だから一緒に食事をしたことがない。
外国人だから、私たちの食事は口に合わないのだろう。
食事時には必ず家に帰るので、デートの時間はせいぜい4,5時間だ。
私は、思い切って言ってみた。
「あなたと一緒に食事がしたいの。あなたと同じものを私も食べるから、家に招待してくれないかしら」
「本当にいいのかい? 僕たちの食事は、きっと君の口には合わないよ」
「いいの。あなたが好きなものは、私も好きになりたいの」
「ありがとう菜々子。今夜母さんにご馳走を作ってもらうよ」
緊張しながら、彼の家に行った。
彼の両親と高校生の妹が、流暢な日本語で私を歓迎してくれた。
「まあ菜々子さん、なんて可愛らしいお嬢さんかしら。お会い出来て嬉しいわ」
「お兄ちゃんにはもったいないね」
無口で厳格なお父さん、明るくて優しいお母さん、可愛い妹。絵にかいたような素敵な家族だ。
「さあ、お夕食にしましょう。今日はご馳走よ」
笑いながらキッチンに消えた母親は、ダイニングテーブルに次々料理を並べていった。
「さあ、みんな席について」
母親の料理は、高級料亭の懐石料理のようにきれいだった。
見た目は日本食と変わらない。きっと味が違うのだ。
「今日はご馳走だよ」と、彼が椅子をすすめてくれた。
「ねえ菜々子さん、この白いの、何だと思う?」
母親が得意げに手前の小鉢を指さした。白和えみたいだ。
「お豆腐……ですか」
「やだ、違うわよ。私たちは豆腐なんて食べないわ。ふふふ、これはね、骨なのよ」
「骨?」
「そう、骨をね、細かく砕いて煮込んだの」
「手間がかかった料理なんだよ」と、彼が自慢げに言った。
「あの、何の骨ですか?」
私が訊くと、母親は首を傾げた。なぜそんな質問を?と思っているようだ。
「人間よ」
「えっ、人間の骨?」
「そうよ。骨は食べたことがないかしら? 人間は捨てるところがないって言うでしょ。骨だって爪だって食べられるのよ。ああ、安心して。これはちゃんと養殖された人間よ。正規なルートで仕入れた安全な食材だから」
何を言っているのだろう。悪い冗談か?
心なしかどれも人間の部位に見えてきた。気持ちが悪い。
「お口に合わないかしら」
「母さん、先住民には人間を食べる習慣がないんだよ。だってそうだろう。まるで共食いだ」
「まあ、菜々子さんは先住民なの? そうよね。ここは数少ない保護地区ですものね」
「あの、ちょっと待って。先住民って、何?」
彼が、憐れむように私を見た。
「君は何も知らないんだね。地球にはもう、純粋な人間は数えるほどしかいない。なぜなら僕たちの先祖が捕獲して食べてしまったからだ。でもね、僕たちはそんなことはしない。先住民を保護して、無意味な狩りを防ぐために地球に派遣されたんだ」
頭が混乱している。彼は宇宙人なの?
私は生まれたときから人間だ。この町で、何不自由なく暮らしてきた。
先住民? 保護地区? 全く訳が分からない。
動悸がして、大量の汗が流れた。
「菜々子さん、何だかおいしそうな匂いがする」
妹が鼻をひくひくさせて言った。
「本当ね。肉汁が溢れてる。ああ、やっぱり天然物は違うわ」
違う。汗です。これは汗です。ああ、拭っても、拭っても汗が出る。
そこで一度も言葉を発していない父親が、初めて口を開いた。
「野生の人間、食ってみたい」
ごくりと唾を呑み込んで、みんながいっせいに私を見た。
「そうね。一人くらい、いいんじゃない?」
ひええ、私は小さく叫びながら、椅子ごと後ろに転げ落ちた。
気がついたら、ベッドで寝ていた。
「気がついた?」
彼が優しく私の髪を撫でた。ああ、やっぱり悪い冗談だった。
「驚かせてごめん。スーパーで、君たちの食べ物を買ってきたよ」
彼は、おにぎりとインスタントのスープを運んでくれた。
「ありがとう。すごくおいしい」
「よかった。たくさん食べてね」
「私、本当に、あなたの家族に食べられてしまうのかと思ったわ」
「ははは、大丈夫だよ。安心してたくさん食べて。もっと太った方がおいしい……いや、可愛いからさ」
ん??
****
村田紗耶香さんばかり読んでいたころに書いたものです。
影響されてるな~(笑)
これって、SF?ホラー?
未来の食卓 [SF]
私が幼いころ、母は誰よりも早く起きて家事をこなしていた。
「お母さん、朝から大変だね」と私が言うと母は笑いながら言った。
「何言ってるの。洗濯は洗濯機がやるし、ごはんは炊飯器が炊くし、お湯はポットが沸かしてくれるのよ。大したことないわ」
偉いなあ。私もお母さんになったら、母のようになりたいと思った。
そして今、私は二人の娘の母になった。
お母さんのようになりたくて、久しぶりに早起きをした。
「ママ、おはよう!どうしたの? 今日はやけに早いね」
「あら、リナちゃんおはよう。今朝はね、炊飯器でごはんを炊いたのよ」
「ゲッ!炊飯器なんて売ってたの? 家電ミュージアムでしか見たことないよ」
「アキバの古い電気屋さんで見つけたの。ちゃんと動くのよ」
「今どき炊飯器でご飯炊く家なんかないよ。ねえ、なんか焦げてない?」
「えっ? あらいやだ。お水入れるんだったわ」
「もういいよ。ほら、焦げ臭いからパパとユナが起きてきちゃったよ」
「おはよう。ママ、なにごと?」
「ごめんなさい」
「クッキングマシンに頼もう。へいクック、朝食作って」
『かしこまりました。お好みのメニューをどうぞ』
「パパは和食、あたしとユナは洋食。ママは?」
「じゃ、じゃあ、中華で(しょんぼり)」
『かしこまりました』
ここ30年で、AI技術は目覚ましい発展を見せた。
特に家事分野では、世界中が競い合うように技術を磨いた。
女性が家事をやる、男性が家事をやる、そんな議論は遠い昔の話。
最新のクッキングマシンは、フリーズドライの材料を定期的に補充すれば、バランスの取れた料理を10分で作ってくれる優れものだ。
「キャー! ママ、洗面所が泡だらけ」
「あら、洗濯機に洗剤を入れ過ぎたかしら」
「もう、洗濯機も買ったの? クリーニングボックスに入れたら畳むところまで自動でやってくれるのに」
「ママ、どこに干すんだよ。今どき洗濯物を外に干す家なんかないぞ」
「そうだよ。友達に見られたら恥ずかしいよ」
「ごめんなさい。でも、一度やってみたかったのよ。パンパンってやつ」
「ああ、俺のおふくろも良くやってたなあ。あのTシャツを叩く音、気持ちよかったな」
「はいはい、令和の話はそのくらいにして。朝食できたよ」
ピピピピ ピピピピ
「なに、この音?」
「炊飯器? 洗濯機? ママ、また何かやらかした?」
ピピピピ ピピピピ
「ほらほら、起きなさい。目覚まし時計が鳴ってるでしょ」
「えっ、お母さん?」
「学校に遅刻するわよ。早く朝ごはん食べなさい」
なんだ夢か。そうだよね、30年やそこらであんなに科学が発展するわけないよね。
「おはようお母さん、朝ごはん何?」
「和食と洋食どっちがいい? 好きな方を選んでボタンを押しなさい」
「えっ?」
「クッキングマシンよ。お父さんの会社で造ったの。まだ試作品なんだけど、なかなか便利よ」
ああ、まんざら夢でもなかった。
「お母さん、朝から大変だね」と私が言うと母は笑いながら言った。
「何言ってるの。洗濯は洗濯機がやるし、ごはんは炊飯器が炊くし、お湯はポットが沸かしてくれるのよ。大したことないわ」
偉いなあ。私もお母さんになったら、母のようになりたいと思った。
そして今、私は二人の娘の母になった。
お母さんのようになりたくて、久しぶりに早起きをした。
「ママ、おはよう!どうしたの? 今日はやけに早いね」
「あら、リナちゃんおはよう。今朝はね、炊飯器でごはんを炊いたのよ」
「ゲッ!炊飯器なんて売ってたの? 家電ミュージアムでしか見たことないよ」
「アキバの古い電気屋さんで見つけたの。ちゃんと動くのよ」
「今どき炊飯器でご飯炊く家なんかないよ。ねえ、なんか焦げてない?」
「えっ? あらいやだ。お水入れるんだったわ」
「もういいよ。ほら、焦げ臭いからパパとユナが起きてきちゃったよ」
「おはよう。ママ、なにごと?」
「ごめんなさい」
「クッキングマシンに頼もう。へいクック、朝食作って」
『かしこまりました。お好みのメニューをどうぞ』
「パパは和食、あたしとユナは洋食。ママは?」
「じゃ、じゃあ、中華で(しょんぼり)」
『かしこまりました』
ここ30年で、AI技術は目覚ましい発展を見せた。
特に家事分野では、世界中が競い合うように技術を磨いた。
女性が家事をやる、男性が家事をやる、そんな議論は遠い昔の話。
最新のクッキングマシンは、フリーズドライの材料を定期的に補充すれば、バランスの取れた料理を10分で作ってくれる優れものだ。
「キャー! ママ、洗面所が泡だらけ」
「あら、洗濯機に洗剤を入れ過ぎたかしら」
「もう、洗濯機も買ったの? クリーニングボックスに入れたら畳むところまで自動でやってくれるのに」
「ママ、どこに干すんだよ。今どき洗濯物を外に干す家なんかないぞ」
「そうだよ。友達に見られたら恥ずかしいよ」
「ごめんなさい。でも、一度やってみたかったのよ。パンパンってやつ」
「ああ、俺のおふくろも良くやってたなあ。あのTシャツを叩く音、気持ちよかったな」
「はいはい、令和の話はそのくらいにして。朝食できたよ」
ピピピピ ピピピピ
「なに、この音?」
「炊飯器? 洗濯機? ママ、また何かやらかした?」
ピピピピ ピピピピ
「ほらほら、起きなさい。目覚まし時計が鳴ってるでしょ」
「えっ、お母さん?」
「学校に遅刻するわよ。早く朝ごはん食べなさい」
なんだ夢か。そうだよね、30年やそこらであんなに科学が発展するわけないよね。
「おはようお母さん、朝ごはん何?」
「和食と洋食どっちがいい? 好きな方を選んでボタンを押しなさい」
「えっ?」
「クッキングマシンよ。お父さんの会社で造ったの。まだ試作品なんだけど、なかなか便利よ」
ああ、まんざら夢でもなかった。
過去に戻れたら、の話 [SF]
職場の飲み会で、タイムトラベルの話が出た。
「過去に戻れるとしたら、いつに戻りたい?」
SF好きの課長を囲んで、そんな話で盛り上がった。
「そりゃあ10代ですよね。青春時代に戻りたいな」
「あたしはダンナに出会う前に戻りたいわ。もう一人候補がいたのよ」
「俺は小学生からやり直したいな。あの頃から英語をやってりゃ苦労しなかったな」
みんな盛り上がっているけど、正直あまり興味がない。
子供の頃から入退院を繰り返していたから、あまりいい思い出がない。
今が一番いい。だからあえて話に加わらなかった。
家が遠いから、みんなより先に店を出た。
歩き始めると、後ろから知らない男に声をかけられた。
「すみません。駅まで行くんですか?」
何だ、こいつ。ナンパか? 無視をしたけど、男は隣に並んで歩き始めた。
「不躾ですけど、あなたたちの話が聞こえてしまって。ほら、過去に戻れたらって話。それで俺、考えたんだよね。戻りたいのはいつだろうって」
ヒマ人だな。そういえば、ひとりでチビチビ飲んでたやつが後ろの席にいたな。
「俺、10歳の頃に戻りたいんだよね。あの頃、傷つけちゃった女の子がいてさ」
子供なんてみんな残酷だ。平気で人を傷つける。
「近所に足の悪い子がいてね、歩き方が変だから、みんなにからかわれてたんだ。俺は家が近所だったから、その子のお母さんに頼まれて一緒に学校に行ってた。ふたりのときは並んで歩いたけどさ、同級生に会うと恥ずかしくて、わざと早く歩いた。のろまだな、早く歩けよ、なんてひどい言葉を浴びせた。その子は顔を赤くして、必死で歩いていたんだ」
「ふうん」あっ、思わず相槌しちゃった。
「その女の子、しばらくして入院してさ、それっきり学校に来なかった。どうしてもっと優しくしなかったのかな。もし過去に戻れたら、あの頃の俺を叱りつける。そして彼女が元気かどうかを確かめるんだ」
「安っぽいドラマみたいですね。でもね、そんなに気にしなくてもいいと思いますよ。その子だってどうせ覚えてないですよ」
「そうかな」
車のライトが、男の横顔を照らす。
そうか。この人、駿くんだ。近所に住んでた2つ上の男の子。
ふたりのときは優しくて、誰かに会うと急に冷たくなった二重人格の駿くんだ。
よく見れば面影あるな。
私だと知って声をかけたのかな?
そんなはずはない。わかるはずがない。
20年も経っているし、何度かの手術で私の足はすっかり治っている。
「ねえ、どうして私に声をかけたの?」
駿くんは、頭を掻きながら言った。
「実はさ、あの店に入ろうとしたとき、初老の男性に声をかけられたんだ。ピンクのカーデガンの女性が店を出たら、すぐに追いかけて話しかけろって。そうしないと一生後悔するぞって」
「なにそれ」
「もしかしたら、未来の俺だったのかな。過去に戻って忠告に来たとか」
「非現実的ね。相変わらず単細胞だな、駿くんは」
「えっ? 何で俺の名前知ってるの?」
「さあね」
あれから30年。
巷では、過去に戻れるタイムマシンの開発が大詰めを迎えていると大騒ぎ。
夢物語が現実になろうとしている。
過去に行けたら、私は8歳の自分に会いに行こう。
いつも泣いていた、寂しい私に会いに行こう。
「あなたの足は必ず治るよ。それからね、駿くんは優しい子だよ。20年後に再会して、あなたと駿くんは結婚するのよ」
うーん。やっぱりこれは、言わない方がいいかもね。
あれ、そもそもあの再会って偶然だったのかしら。ねえ、あなた。
「過去に戻れるとしたら、いつに戻りたい?」
SF好きの課長を囲んで、そんな話で盛り上がった。
「そりゃあ10代ですよね。青春時代に戻りたいな」
「あたしはダンナに出会う前に戻りたいわ。もう一人候補がいたのよ」
「俺は小学生からやり直したいな。あの頃から英語をやってりゃ苦労しなかったな」
みんな盛り上がっているけど、正直あまり興味がない。
子供の頃から入退院を繰り返していたから、あまりいい思い出がない。
今が一番いい。だからあえて話に加わらなかった。
家が遠いから、みんなより先に店を出た。
歩き始めると、後ろから知らない男に声をかけられた。
「すみません。駅まで行くんですか?」
何だ、こいつ。ナンパか? 無視をしたけど、男は隣に並んで歩き始めた。
「不躾ですけど、あなたたちの話が聞こえてしまって。ほら、過去に戻れたらって話。それで俺、考えたんだよね。戻りたいのはいつだろうって」
ヒマ人だな。そういえば、ひとりでチビチビ飲んでたやつが後ろの席にいたな。
「俺、10歳の頃に戻りたいんだよね。あの頃、傷つけちゃった女の子がいてさ」
子供なんてみんな残酷だ。平気で人を傷つける。
「近所に足の悪い子がいてね、歩き方が変だから、みんなにからかわれてたんだ。俺は家が近所だったから、その子のお母さんに頼まれて一緒に学校に行ってた。ふたりのときは並んで歩いたけどさ、同級生に会うと恥ずかしくて、わざと早く歩いた。のろまだな、早く歩けよ、なんてひどい言葉を浴びせた。その子は顔を赤くして、必死で歩いていたんだ」
「ふうん」あっ、思わず相槌しちゃった。
「その女の子、しばらくして入院してさ、それっきり学校に来なかった。どうしてもっと優しくしなかったのかな。もし過去に戻れたら、あの頃の俺を叱りつける。そして彼女が元気かどうかを確かめるんだ」
「安っぽいドラマみたいですね。でもね、そんなに気にしなくてもいいと思いますよ。その子だってどうせ覚えてないですよ」
「そうかな」
車のライトが、男の横顔を照らす。
そうか。この人、駿くんだ。近所に住んでた2つ上の男の子。
ふたりのときは優しくて、誰かに会うと急に冷たくなった二重人格の駿くんだ。
よく見れば面影あるな。
私だと知って声をかけたのかな?
そんなはずはない。わかるはずがない。
20年も経っているし、何度かの手術で私の足はすっかり治っている。
「ねえ、どうして私に声をかけたの?」
駿くんは、頭を掻きながら言った。
「実はさ、あの店に入ろうとしたとき、初老の男性に声をかけられたんだ。ピンクのカーデガンの女性が店を出たら、すぐに追いかけて話しかけろって。そうしないと一生後悔するぞって」
「なにそれ」
「もしかしたら、未来の俺だったのかな。過去に戻って忠告に来たとか」
「非現実的ね。相変わらず単細胞だな、駿くんは」
「えっ? 何で俺の名前知ってるの?」
「さあね」
あれから30年。
巷では、過去に戻れるタイムマシンの開発が大詰めを迎えていると大騒ぎ。
夢物語が現実になろうとしている。
過去に行けたら、私は8歳の自分に会いに行こう。
いつも泣いていた、寂しい私に会いに行こう。
「あなたの足は必ず治るよ。それからね、駿くんは優しい子だよ。20年後に再会して、あなたと駿くんは結婚するのよ」
うーん。やっぱりこれは、言わない方がいいかもね。
あれ、そもそもあの再会って偶然だったのかしら。ねえ、あなた。
未来の殺人犯 [SF]
会社からの帰り道、突然警察に拘束された。
「いったい何? 私が何をしたっていうのよ」
「今はまだ何もしていません。これからします」
「これから? 私がこれから何をするっていうの?」
「殺人です」
「はあ? 意味わかんない。私が誰を殺すっていうの?」
「この方です。ハラダシンヤさんです」
刑事が写真を見せた。まったく見覚えがない。
「だれ? このおっさん」
「あなたのご主人です。そしてあなたは将来、ご主人を殺します」
「絶対ウソ。こんなおじさんと結婚するわけないじゃん。全然好みじゃないわ」
「30年後の写真です。30年後はあなたも相当のおばさんです」
「余計なお世話よ」
「30年後、世界を揺るがす恐ろしいウイルスが発生します。ハラダ氏は、そのウイルスの特効薬を開発しました。完成まであと一歩のところで、あなたに殺されてしまうのです。私たちは、未来警察からの依頼を受けて、あなたを拘束しました。ハラダ氏は、未来の地球に必要不可欠な人物なのです」
「そんな立派な人を、どうして私が殺すのよ」
「浮気です。あなたは非常に嫉妬深く思考能力が低い人です。おまけに今より20キロ太っています」
「何気に失礼。最後の情報、関係なくない? それにしても、そんな大事な研究しながら浮気もしてたの? 全然モテそうもないおじさんなのに?」
「あなたは、明日ハラダ氏と出会います。そして電撃結婚します。ですから我々は、あなたがハラダ氏と出会うのを阻止しなければなりません」
「じゃあ、明日までここにいなきゃいけないの? 明日は友達の結婚式なのよ」
「はい、その結婚式でハラダ氏と出会います」
「そうなの? じゃあ出会っても無視するわ。絶対結婚しないから、家に帰してよ。見たいドラマがあるの」
「出会った以上、運命は変えられません。出会ってはいけないのです」
「やだやだ、絶対帰る!」
暴れたら注射を打たれて、そのまま眠り落ちた。気が付いたのは2日後だった。
私はなぜか、高熱を出して入院したことになっていた。
拘束されたことを家族や友人に話しても、「頭大丈夫?」と笑うばかりだった。
やはり夢だったのか? そう思って忘れることにした。
そして30年後の今年、謎のウイルスが世界中に蔓延した。
私は急激に、あの日のことを思い出した。
ああ、そうだ。ハラダという人が、数か月後に特効薬を完成させるはずだ。
私と結婚しなかったから、殺されることもないだろう。
しかしハラダ氏は、私ではない別の女に殺されてしまった。
『ウイルス研究の第一人者であるハラダシンヤさんが、妻に殺害されました。ウイルスの特効薬完成まであと一歩というところでした』
なんだ、結局死ぬんじゃないの。それがこの男の運命だったんだ。
じゃあ地球はどうなるの? 特効薬は出来ないの?
ふふふ、大丈夫よ。私、死ぬ前にハラダ氏に近づいて、薬のデータを手に入れたの。
これを製薬会社に売って大金を手に入れるのよ。
30年前のあの日、私の運命が変わったの。
ハラダ氏の妻から、愛人にね。
いや、それにしても、過去に戻って未来を変えられるのなら、ウイルスが広まる前に止めてほしかった。ねえ、そう思わない?
「いったい何? 私が何をしたっていうのよ」
「今はまだ何もしていません。これからします」
「これから? 私がこれから何をするっていうの?」
「殺人です」
「はあ? 意味わかんない。私が誰を殺すっていうの?」
「この方です。ハラダシンヤさんです」
刑事が写真を見せた。まったく見覚えがない。
「だれ? このおっさん」
「あなたのご主人です。そしてあなたは将来、ご主人を殺します」
「絶対ウソ。こんなおじさんと結婚するわけないじゃん。全然好みじゃないわ」
「30年後の写真です。30年後はあなたも相当のおばさんです」
「余計なお世話よ」
「30年後、世界を揺るがす恐ろしいウイルスが発生します。ハラダ氏は、そのウイルスの特効薬を開発しました。完成まであと一歩のところで、あなたに殺されてしまうのです。私たちは、未来警察からの依頼を受けて、あなたを拘束しました。ハラダ氏は、未来の地球に必要不可欠な人物なのです」
「そんな立派な人を、どうして私が殺すのよ」
「浮気です。あなたは非常に嫉妬深く思考能力が低い人です。おまけに今より20キロ太っています」
「何気に失礼。最後の情報、関係なくない? それにしても、そんな大事な研究しながら浮気もしてたの? 全然モテそうもないおじさんなのに?」
「あなたは、明日ハラダ氏と出会います。そして電撃結婚します。ですから我々は、あなたがハラダ氏と出会うのを阻止しなければなりません」
「じゃあ、明日までここにいなきゃいけないの? 明日は友達の結婚式なのよ」
「はい、その結婚式でハラダ氏と出会います」
「そうなの? じゃあ出会っても無視するわ。絶対結婚しないから、家に帰してよ。見たいドラマがあるの」
「出会った以上、運命は変えられません。出会ってはいけないのです」
「やだやだ、絶対帰る!」
暴れたら注射を打たれて、そのまま眠り落ちた。気が付いたのは2日後だった。
私はなぜか、高熱を出して入院したことになっていた。
拘束されたことを家族や友人に話しても、「頭大丈夫?」と笑うばかりだった。
やはり夢だったのか? そう思って忘れることにした。
そして30年後の今年、謎のウイルスが世界中に蔓延した。
私は急激に、あの日のことを思い出した。
ああ、そうだ。ハラダという人が、数か月後に特効薬を完成させるはずだ。
私と結婚しなかったから、殺されることもないだろう。
しかしハラダ氏は、私ではない別の女に殺されてしまった。
『ウイルス研究の第一人者であるハラダシンヤさんが、妻に殺害されました。ウイルスの特効薬完成まであと一歩というところでした』
なんだ、結局死ぬんじゃないの。それがこの男の運命だったんだ。
じゃあ地球はどうなるの? 特効薬は出来ないの?
ふふふ、大丈夫よ。私、死ぬ前にハラダ氏に近づいて、薬のデータを手に入れたの。
これを製薬会社に売って大金を手に入れるのよ。
30年前のあの日、私の運命が変わったの。
ハラダ氏の妻から、愛人にね。
いや、それにしても、過去に戻って未来を変えられるのなら、ウイルスが広まる前に止めてほしかった。ねえ、そう思わない?
ベルベットの部屋 [SF]
この部屋は、本当に居心地がいい。
温かくて清潔で、おだやかな空気が流れている。
アイボリーの壁には花の絵が飾られ、いつも静かな音楽が流れている。
窓にかかったベルベットのカーテンは、季節ごとに色を変える。
ママはソファーにもたれてレースを編む。
私と弟は、ふかふかの絨毯で本を読んだりトランプをする。
1日中この部屋で過ごすけれど、なんの不自由も感じない。
むしろ楽しい。
夕方パパが仕事から帰ってくると、弟がすかさず飛びつく。
「おかえりパパ」
「パパ、外の話聞かせて」
パパは優しく笑いながら、仕事で出会った珍しい生物の話をしてくれる。
ママは食事をテーブルに並べ、グロテスクな生物の話に眉をしかめる。
パパが宇宙勤務になったのは1年前。
私たち家族は、地球に残るか、パパと宇宙に行くかを問われた。
私と弟は、迷わず「宇宙」と答えた。
地球の学校が好きではなかった。
乱暴な男子にイスを蹴られたり、消しゴムを取られたりした。
早生まれで小さい弟は、理由もなくイジメを受けていた。
宇宙には、どんな恐ろしいことがあるかわからないから、パパが仕事に行っている間、私たちは1日中部屋の中で過ごす。
ベルベットのカーテンが開くことはない。
窓の向こうは、鉄の壁だから。
その向こうがどんな世界か知らないけれど、知る必要もないほどに、この部屋が大好きだ。
ママが10作目のレースを編み終え、私と弟が50冊の本を読み終えた頃、パパが言った。
「もうすぐ地球に帰れるぞ」
ママは目を輝かせた。
「まあ嬉しい。もう味気ない宇宙食を食べなくて済むのね」
私と弟は、思わず顔を見合わせた。
地球になど、帰りたくない。
「3日後、地球に帰るぞ」
パパは言った。
その夜、私と弟は家出の計画を立てた。
3日後の朝、家出をする。
私たちがいないことに気付けば、地球へ帰るのもやめるはず。
「でもさ、外は危険なんでしょう?」
弟がしり込みをする。
「パパはいつも出かけるけど、無事に帰ってくるじゃない」
「特殊な宇宙服を着ているからだ」
「じゃあその服を借りればいい」
宇宙服が小型宇宙船のガレージに2着ある。それを着ればいい。
そして3日後、ほとんど眠らずに朝を迎えた。
パパとママはまだ眠っている。
弟とベッドを抜け出して、そろりと歩く。
鉄の扉を開けるセキリュティーコードはこっそり覚えた。
宇宙服を着て扉を開けると、朝の陽射しが眩しかった。
久しぶりに見る光に、思わず目を閉じた。
そよそよと風になびく草原が広がっている。
鳥のような生物が空を飛び、キツネのような生物が顔を出す。
「なんだ。地球と同じような星だ」
空気があることを知り、宇宙服を脱いだ。
大地に足をのせると、弟ははしゃいで走り回った。
私は久しぶりすぎて、上手く走れない。
足がもつれて転んだとき、うしろからパパの声がした。
「こら、いきなり外に出たら危ないだろう」
しまった。連れ戻される。
「パパ、私ずっとこの星にいたい。地球に帰りたくない」
パパとママは呆れたように笑った。
「何言ってるの?ここが地球よ」
「え?だって、今日地球に帰るんでしょう?」
「たった今帰って来たんだよ。3日間かけて地球にね」
振り向くと、大きな宇宙船が私たちを見おろしている。
窓もない鉄のかたまり。
朝露を含んだ草が足元をくすぐり、優しい風が髪を揺らした。
1年間過ごしたベルベットの部屋が、なぜだかとても不自由に感じた。
「お姉ちゃん、ぼく学校へ行ったら、みんなに宇宙生物の話をするんだ」
息を切らした弟の顔が輝いている。
「うん。私も」 と答えていた。
なぜだろう。少しだけ、楽しみだ。

にほんブログ村
温かくて清潔で、おだやかな空気が流れている。
アイボリーの壁には花の絵が飾られ、いつも静かな音楽が流れている。
窓にかかったベルベットのカーテンは、季節ごとに色を変える。
ママはソファーにもたれてレースを編む。
私と弟は、ふかふかの絨毯で本を読んだりトランプをする。
1日中この部屋で過ごすけれど、なんの不自由も感じない。
むしろ楽しい。
夕方パパが仕事から帰ってくると、弟がすかさず飛びつく。
「おかえりパパ」
「パパ、外の話聞かせて」
パパは優しく笑いながら、仕事で出会った珍しい生物の話をしてくれる。
ママは食事をテーブルに並べ、グロテスクな生物の話に眉をしかめる。
パパが宇宙勤務になったのは1年前。
私たち家族は、地球に残るか、パパと宇宙に行くかを問われた。
私と弟は、迷わず「宇宙」と答えた。
地球の学校が好きではなかった。
乱暴な男子にイスを蹴られたり、消しゴムを取られたりした。
早生まれで小さい弟は、理由もなくイジメを受けていた。
宇宙には、どんな恐ろしいことがあるかわからないから、パパが仕事に行っている間、私たちは1日中部屋の中で過ごす。
ベルベットのカーテンが開くことはない。
窓の向こうは、鉄の壁だから。
その向こうがどんな世界か知らないけれど、知る必要もないほどに、この部屋が大好きだ。
ママが10作目のレースを編み終え、私と弟が50冊の本を読み終えた頃、パパが言った。
「もうすぐ地球に帰れるぞ」
ママは目を輝かせた。
「まあ嬉しい。もう味気ない宇宙食を食べなくて済むのね」
私と弟は、思わず顔を見合わせた。
地球になど、帰りたくない。
「3日後、地球に帰るぞ」
パパは言った。
その夜、私と弟は家出の計画を立てた。
3日後の朝、家出をする。
私たちがいないことに気付けば、地球へ帰るのもやめるはず。
「でもさ、外は危険なんでしょう?」
弟がしり込みをする。
「パパはいつも出かけるけど、無事に帰ってくるじゃない」
「特殊な宇宙服を着ているからだ」
「じゃあその服を借りればいい」
宇宙服が小型宇宙船のガレージに2着ある。それを着ればいい。
そして3日後、ほとんど眠らずに朝を迎えた。
パパとママはまだ眠っている。
弟とベッドを抜け出して、そろりと歩く。
鉄の扉を開けるセキリュティーコードはこっそり覚えた。
宇宙服を着て扉を開けると、朝の陽射しが眩しかった。
久しぶりに見る光に、思わず目を閉じた。
そよそよと風になびく草原が広がっている。
鳥のような生物が空を飛び、キツネのような生物が顔を出す。
「なんだ。地球と同じような星だ」
空気があることを知り、宇宙服を脱いだ。
大地に足をのせると、弟ははしゃいで走り回った。
私は久しぶりすぎて、上手く走れない。
足がもつれて転んだとき、うしろからパパの声がした。
「こら、いきなり外に出たら危ないだろう」
しまった。連れ戻される。
「パパ、私ずっとこの星にいたい。地球に帰りたくない」
パパとママは呆れたように笑った。
「何言ってるの?ここが地球よ」
「え?だって、今日地球に帰るんでしょう?」
「たった今帰って来たんだよ。3日間かけて地球にね」
振り向くと、大きな宇宙船が私たちを見おろしている。
窓もない鉄のかたまり。
朝露を含んだ草が足元をくすぐり、優しい風が髪を揺らした。
1年間過ごしたベルベットの部屋が、なぜだかとても不自由に感じた。
「お姉ちゃん、ぼく学校へ行ったら、みんなに宇宙生物の話をするんだ」
息を切らした弟の顔が輝いている。
「うん。私も」 と答えていた。
なぜだろう。少しだけ、楽しみだ。
にほんブログ村
ロビン [SF]
妹が訪ねてきた。
「彼氏と一週間旅行に行くの。そのあいだ、ロビンを預かってほしいのよ」
「ロビン?犬かしら。それとも猫?」
「ロボットよ」
ロビンは、妹が働く研究所で造られた癒し系ロボットだという。
今はまだ試作段階で、それぞれの研究員に一体ずつ与えられたという。
「一週間動かさないと、プログラムに不具合が起こるらしいの。だからお願い。一緒にいるだけでいいの。特別なことはしなくていいから」
翌日、妹がロボットのロビンを連れてきた。
可愛い人形みたいなロボットだと思っていたが違った。
ロビンは人間そっくり。しかもかなりイケメンの男だった。
「じゃあお姉ちゃん、よろしくね。一緒にいるだけで、何もしなくていいから。すぐに慣れるわ。ただのロボットだもん」
ロビンとの暮らしが始まった。
ロボットとわかっていても緊張する。
ロビンの顔は、すごく私の好みだった。
「レイナさん、コーヒーが入りました」
名前を呼ばれただけで、胸がきゅんとなる。
しかもロビンは、私が欲しいものを先回りして用意してくれる。
顔を洗えばタオルを差し出し、のどが渇けば水をくれる。
仕事に行くときは
「行ってらっしゃい。仕事は大変でしょうけど、頑張りすぎないでくださいね」
帰ってきたら
「お帰りなさい。お仕事お疲れ様です」
欲しい言葉を言ってくれて、ほどよい力でマッサージをしてくれる。
食事をとらないことと、深夜の充電を除けば、どこから見ても理想の男だった。
ロビンとの暮らしは、柔らかいスイートピーみたいな淡いピンク色だ。
初恋の甘酸っぱい想いがよみがえる。
毎日がときめいて、楽しくて仕方ない。
ロビンといると、私の中の女性の部分が目を覚ます。
自由奔放な妹に比べ、私は恋愛経験に乏しかった。
そうだ、ロビンを相手に、恋愛のシミュレーションをしてみようか。
こんなイケメンが近くにいるのに、何もしないなんてもったいない。
ロボットだし、感情がないんだから何をしてもいいじゃないか。
私はロビンの顔をじっと見つめた。
「レイナさん、どうしました?何がお望みですか?」
「ロビン、いいからじっとして」
数日後。
ああ、どうしよう。もうすぐ妹が帰ってくる。
言えない。ロビンが壊れちゃったなんて。
ロビンは急に動かなくなった。
これからというときに、急に動かなくなった。
妹が帰ってきた。
「お姉ちゃん、ありがとう。ロビンを迎えに来たわ」
「あの…それが…」
「お姉ちゃんに言い忘れちゃったんだけど、ロビンの全てをコントロールするICチップが口の中に入っているの。まあ、キスでもしない限り壊れることはないけどね。いくら彼氏いない歴30年のお姉ちゃんでもロボットにキスはしないよね…あっ」
ロビンは、だらしなく口を開けて座っている。
「お姉ちゃん、まさか…」
「ごめん、つい。でも、いくらイケメンロボでも、まともにキスも出来ないようじゃダメだわ。研究の余地があるわね」
「お姉ちゃん…彼氏紹介しようか?」
「お願い。できれば、人間の男にして」
これって、SF?(笑)


にほんブログ村
「彼氏と一週間旅行に行くの。そのあいだ、ロビンを預かってほしいのよ」
「ロビン?犬かしら。それとも猫?」
「ロボットよ」
ロビンは、妹が働く研究所で造られた癒し系ロボットだという。
今はまだ試作段階で、それぞれの研究員に一体ずつ与えられたという。
「一週間動かさないと、プログラムに不具合が起こるらしいの。だからお願い。一緒にいるだけでいいの。特別なことはしなくていいから」
翌日、妹がロボットのロビンを連れてきた。
可愛い人形みたいなロボットだと思っていたが違った。
ロビンは人間そっくり。しかもかなりイケメンの男だった。
「じゃあお姉ちゃん、よろしくね。一緒にいるだけで、何もしなくていいから。すぐに慣れるわ。ただのロボットだもん」
ロビンとの暮らしが始まった。
ロボットとわかっていても緊張する。
ロビンの顔は、すごく私の好みだった。
「レイナさん、コーヒーが入りました」
名前を呼ばれただけで、胸がきゅんとなる。
しかもロビンは、私が欲しいものを先回りして用意してくれる。
顔を洗えばタオルを差し出し、のどが渇けば水をくれる。
仕事に行くときは
「行ってらっしゃい。仕事は大変でしょうけど、頑張りすぎないでくださいね」
帰ってきたら
「お帰りなさい。お仕事お疲れ様です」
欲しい言葉を言ってくれて、ほどよい力でマッサージをしてくれる。
食事をとらないことと、深夜の充電を除けば、どこから見ても理想の男だった。
ロビンとの暮らしは、柔らかいスイートピーみたいな淡いピンク色だ。
初恋の甘酸っぱい想いがよみがえる。
毎日がときめいて、楽しくて仕方ない。
ロビンといると、私の中の女性の部分が目を覚ます。
自由奔放な妹に比べ、私は恋愛経験に乏しかった。
そうだ、ロビンを相手に、恋愛のシミュレーションをしてみようか。
こんなイケメンが近くにいるのに、何もしないなんてもったいない。
ロボットだし、感情がないんだから何をしてもいいじゃないか。
私はロビンの顔をじっと見つめた。
「レイナさん、どうしました?何がお望みですか?」
「ロビン、いいからじっとして」
数日後。
ああ、どうしよう。もうすぐ妹が帰ってくる。
言えない。ロビンが壊れちゃったなんて。
ロビンは急に動かなくなった。
これからというときに、急に動かなくなった。
妹が帰ってきた。
「お姉ちゃん、ありがとう。ロビンを迎えに来たわ」
「あの…それが…」
「お姉ちゃんに言い忘れちゃったんだけど、ロビンの全てをコントロールするICチップが口の中に入っているの。まあ、キスでもしない限り壊れることはないけどね。いくら彼氏いない歴30年のお姉ちゃんでもロボットにキスはしないよね…あっ」
ロビンは、だらしなく口を開けて座っている。
「お姉ちゃん、まさか…」
「ごめん、つい。でも、いくらイケメンロボでも、まともにキスも出来ないようじゃダメだわ。研究の余地があるわね」
「お姉ちゃん…彼氏紹介しようか?」
「お願い。できれば、人間の男にして」
これって、SF?(笑)

にほんブログ村
博士とマリー [SF]
人間嫌いの博士は、人間そっくりのロボットを造って、一緒に暮らした。
「人間嫌いなのに、どうして人間そっくりのロボットを造ったの?」
博士の唯一の理解者である、孫のマリーが訊ねた。
「わしのロボットは人間そっくりだが、人間のようにつまらんことで泣いたり怒ったりしない。失敗もしない。金に汚くないし、くだらん世辞も言わん」
博士は「もういいか」という具合に視線を本に戻した。
こうなると、もう話しかけても返事はない。
偏屈な性格をよく知っているマリーは、邪魔をしないように部屋を出た。
庭には、博士が造ったロボットが植木の手入れをしていた。
「マリーさん、お帰りですか?」
ロボットは、にこやかに笑った。
「ご苦労さま。ええと、名前は何だったかしら?」
「マイケルです。マリーさん。以後、お見知りおきを」
「マイケルさん、おじいちゃん、偏屈で大変だろうけどよろしくね」
「お心遣いありがとうございます。私は大丈夫です」
マイケルは、恐ろしい速さで植木の手入れを終え、次の仕事に取り掛かった。
博士は天才的な科学者だが、その才能を世のために使おうとはしなかった。
「もったいないな」と、マリーはいつも思っていた。
「ただいま」
「おかえりマリー、おじいちゃんのところへ行っていたの?」
「うん。おじいちゃん、すごいよ。マイケルっていう人間そっくりのロボットを造ったの」
「まあ、お父さん、またそんなものを…」
母親は眉間に皺を寄せながらため息をついた。
「マリー、おじいちゃんがロボットを造っていること、絶対言っちゃダメよ」
「どうして?」
「おじいちゃんの技術を盗みに来る人がいるからよ」
「わかった」
マリーに父親はいない。小さい頃に亡くなった。
母親はいつも忙しく、マリーは博士の家で過ごすことが多かった。
ある日、マリーがいつものように博士の家に行くと、見たことのない靴があった。
マイケルが、廊下で静かに座っている。
「マイケルさん、お客さま?」
「はい、マリーさん、知らない人が来ています」
マリーは、そっと壁に耳をあてた。とたんに、博士の怒鳴り声が聞こえてきた。
「いい加減にしろ。ロボットなどわしゃ知らん。あれは人間だ」
「いや、わかるんですよ。私、ロボット探知機を持ってますから。博士、お願いしますよ。その技術を私どもに教えて下さい」
客の男は必死に頼んでいる。マリーはたまらず、ドアを開けて中に入った。
「おじいちゃん、教えてあげたら?マイケルさんみたいなロボットがいたら、多くの人が助かるわ」
「マリー、出て行きなさい!」
いつになく厳しく叱った博士の後ろで、客の男がマリーに探知機をあてた。
「ほう、この子もロボットですか。実によく出来ていますな」
マリーに向けられたロボット探知機は、確かに赤く反応している。
「婿さんとお孫さんを事故で亡くしたと聞きました。もしかして、お孫さんのかわりにロボットを?」
「うるさい!出て行け。マイケル、こいつをつまみ出せ」
マイケルが「はい」と男を羽交い絞めにして、有無を言わさず外に出した。
マリーは、回線がショートしてしまったように首を傾げていた。
「おじいちゃん、わたし、ロボットなの?」
どうりで、泣きもしないし怒りもしない。失敗もしないし金に汚くないし、くだらないお世辞も言わない。
マリーは、自分がロボットであるという情報をインプットして、うなだれる博士の手を取った。
「おじいちゃん、大好きよ」

にほんブログ村
「人間嫌いなのに、どうして人間そっくりのロボットを造ったの?」
博士の唯一の理解者である、孫のマリーが訊ねた。
「わしのロボットは人間そっくりだが、人間のようにつまらんことで泣いたり怒ったりしない。失敗もしない。金に汚くないし、くだらん世辞も言わん」
博士は「もういいか」という具合に視線を本に戻した。
こうなると、もう話しかけても返事はない。
偏屈な性格をよく知っているマリーは、邪魔をしないように部屋を出た。
庭には、博士が造ったロボットが植木の手入れをしていた。
「マリーさん、お帰りですか?」
ロボットは、にこやかに笑った。
「ご苦労さま。ええと、名前は何だったかしら?」
「マイケルです。マリーさん。以後、お見知りおきを」
「マイケルさん、おじいちゃん、偏屈で大変だろうけどよろしくね」
「お心遣いありがとうございます。私は大丈夫です」
マイケルは、恐ろしい速さで植木の手入れを終え、次の仕事に取り掛かった。
博士は天才的な科学者だが、その才能を世のために使おうとはしなかった。
「もったいないな」と、マリーはいつも思っていた。
「ただいま」
「おかえりマリー、おじいちゃんのところへ行っていたの?」
「うん。おじいちゃん、すごいよ。マイケルっていう人間そっくりのロボットを造ったの」
「まあ、お父さん、またそんなものを…」
母親は眉間に皺を寄せながらため息をついた。
「マリー、おじいちゃんがロボットを造っていること、絶対言っちゃダメよ」
「どうして?」
「おじいちゃんの技術を盗みに来る人がいるからよ」
「わかった」
マリーに父親はいない。小さい頃に亡くなった。
母親はいつも忙しく、マリーは博士の家で過ごすことが多かった。
ある日、マリーがいつものように博士の家に行くと、見たことのない靴があった。
マイケルが、廊下で静かに座っている。
「マイケルさん、お客さま?」
「はい、マリーさん、知らない人が来ています」
マリーは、そっと壁に耳をあてた。とたんに、博士の怒鳴り声が聞こえてきた。
「いい加減にしろ。ロボットなどわしゃ知らん。あれは人間だ」
「いや、わかるんですよ。私、ロボット探知機を持ってますから。博士、お願いしますよ。その技術を私どもに教えて下さい」
客の男は必死に頼んでいる。マリーはたまらず、ドアを開けて中に入った。
「おじいちゃん、教えてあげたら?マイケルさんみたいなロボットがいたら、多くの人が助かるわ」
「マリー、出て行きなさい!」
いつになく厳しく叱った博士の後ろで、客の男がマリーに探知機をあてた。
「ほう、この子もロボットですか。実によく出来ていますな」
マリーに向けられたロボット探知機は、確かに赤く反応している。
「婿さんとお孫さんを事故で亡くしたと聞きました。もしかして、お孫さんのかわりにロボットを?」
「うるさい!出て行け。マイケル、こいつをつまみ出せ」
マイケルが「はい」と男を羽交い絞めにして、有無を言わさず外に出した。
マリーは、回線がショートしてしまったように首を傾げていた。
「おじいちゃん、わたし、ロボットなの?」
どうりで、泣きもしないし怒りもしない。失敗もしないし金に汚くないし、くだらないお世辞も言わない。
マリーは、自分がロボットであるという情報をインプットして、うなだれる博士の手を取った。
「おじいちゃん、大好きよ」
にほんブログ村
彼と星とベンチコート [SF]
「寒いよ、もう帰ろうよ」
私が言うと龍一は、自分のベンチコートを脱いで私の肩にかけてくれた。
「それじゃ龍一が寒いでしょ」
「僕は平気だから、もうちょっと待ってて」
ずるいくらいの爽やかな笑顔で、彼は視線を空へ戻した。
夜のデートはいつも天体観測。
星と私、どっちが大事? そんな言葉を飲み込んで、彼のベンチコートにくるまった。
彼の匂いが私を安心させた。いつまでも寄り添っていたいと、心から思った。
目覚めて、いつもの夢だと気づいた。
毎日のように龍一の夢を見る。
彼は5年前のあの日、宇宙に連れ去られてしまった。
空からまばゆい光がまっすぐに降りてきて、龍一を連れ去った。
私はまるでSF映画を観ているような気分で、ただその場に立ち尽くしていた。
不思議と怖くなかった。
龍一が、光の中で笑っていたから。まるでそれを望んでいるように見えた。
謎の失踪事件として、しばらく世間を騒がせたが、もう誰もが忘れている。
私はあの日返しそびれたベンチコートがあるかぎり、忘れることなど出来なかった。
龍一が訪ねてきたのは、星がきれいな真冬の夜だった。
窓を叩き、相変わらずの爽やかな笑顔を見せた。
ここはマンションの5階なのに、彼はなんでもないように宙を歩いていた。
「ごめん、心配させて」
こんなに寒いのに、彼は薄着だった。あの日私がベンチコートを奪ってしまったからだ。
「5年も何をしていたの?」
「5年?そんなに経ったの?まだ半月位だと思っていた。まるで浦島太郎だな」
彼は、連れ去られたどこかの星で、留学生として優遇されていると言った。
「いずれ地球と交流を持ちたいんだって。僕はその架け橋になれるように勉強させてもらっている」
龍一はとても輝いていた。楽しくて仕方ないようだ。
「すぐには無理だけど、必ず帰ってくるよ」と龍一は言った。
ベンチコートは、その時まで預かって欲しいと。
私は、わかったと答えた。とにかく龍一が無事だったことが嬉しかった。
彼は少しも変わっていなかった。
龍一は、その後も会いに来た。
決まって星がきれいな真冬の夜。
そして決まって5年後だ。
宇宙がどれだけ素晴らしいか、地球がどんなに美しいかを熱く語る。
「もうすぐ、地球とあの星を行き来できる日がくるよ」と彼は言う。
私は、その星と地球の交流は無理だと思う。
だって時間の流れが違いすぎる。
龍一が会いに来た10度目の冬、彼はまだ青年で、私はすっかりおばあさんだ。
次に彼が来たときまで、生きていられるかどうかわからない。
古ぼけたベンチコートを眺めながら、私は呟く。
やっぱりあなたは星を選んだのね。
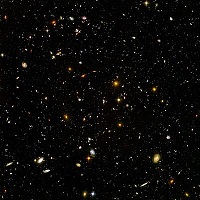
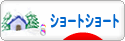
にほんブログ村
私が言うと龍一は、自分のベンチコートを脱いで私の肩にかけてくれた。
「それじゃ龍一が寒いでしょ」
「僕は平気だから、もうちょっと待ってて」
ずるいくらいの爽やかな笑顔で、彼は視線を空へ戻した。
夜のデートはいつも天体観測。
星と私、どっちが大事? そんな言葉を飲み込んで、彼のベンチコートにくるまった。
彼の匂いが私を安心させた。いつまでも寄り添っていたいと、心から思った。
目覚めて、いつもの夢だと気づいた。
毎日のように龍一の夢を見る。
彼は5年前のあの日、宇宙に連れ去られてしまった。
空からまばゆい光がまっすぐに降りてきて、龍一を連れ去った。
私はまるでSF映画を観ているような気分で、ただその場に立ち尽くしていた。
不思議と怖くなかった。
龍一が、光の中で笑っていたから。まるでそれを望んでいるように見えた。
謎の失踪事件として、しばらく世間を騒がせたが、もう誰もが忘れている。
私はあの日返しそびれたベンチコートがあるかぎり、忘れることなど出来なかった。
龍一が訪ねてきたのは、星がきれいな真冬の夜だった。
窓を叩き、相変わらずの爽やかな笑顔を見せた。
ここはマンションの5階なのに、彼はなんでもないように宙を歩いていた。
「ごめん、心配させて」
こんなに寒いのに、彼は薄着だった。あの日私がベンチコートを奪ってしまったからだ。
「5年も何をしていたの?」
「5年?そんなに経ったの?まだ半月位だと思っていた。まるで浦島太郎だな」
彼は、連れ去られたどこかの星で、留学生として優遇されていると言った。
「いずれ地球と交流を持ちたいんだって。僕はその架け橋になれるように勉強させてもらっている」
龍一はとても輝いていた。楽しくて仕方ないようだ。
「すぐには無理だけど、必ず帰ってくるよ」と龍一は言った。
ベンチコートは、その時まで預かって欲しいと。
私は、わかったと答えた。とにかく龍一が無事だったことが嬉しかった。
彼は少しも変わっていなかった。
龍一は、その後も会いに来た。
決まって星がきれいな真冬の夜。
そして決まって5年後だ。
宇宙がどれだけ素晴らしいか、地球がどんなに美しいかを熱く語る。
「もうすぐ、地球とあの星を行き来できる日がくるよ」と彼は言う。
私は、その星と地球の交流は無理だと思う。
だって時間の流れが違いすぎる。
龍一が会いに来た10度目の冬、彼はまだ青年で、私はすっかりおばあさんだ。
次に彼が来たときまで、生きていられるかどうかわからない。
古ぼけたベンチコートを眺めながら、私は呟く。
やっぱりあなたは星を選んだのね。
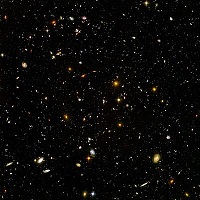
にほんブログ村
ゾンビの町 [SF]
私たちの小さな町は、ある日を境にZ地区と呼ばれるようになった。
事の始まりは、ひとりの渡航者だった。
海外から帰国した男が、体調を崩してこの町の病院に入院した。
原因不明のウイルスに感染していた男は、やがて化物に姿を変え、病院の人を次々に襲った。
それは、ゾンビウイルスと呼ばれ、噛まれた人はゾンビになってまた人を襲う。
町に増えたゾンビに打つ手はなく、政府は病院周辺の地区に高い鉄の塀を立て、完全に隔離した。
私たち家族は、ゾンビに感染していない。
だけど同じように隔離され、ここから出ることができない。
塀の上に付けられたカメラと、ヘリコプターからの映像が繰り返しテレビで流された。
『Z地区のゾンビの数は、日に日に増えています。政府は特効薬の開発を急がせています。まだ感染していないみなさん。希望を持って頑張りましょう』
「いったいいつまで待てばいいの?買い物も行けないし、食糧だっていつまで持つか」と母。
「ゾンビになる前に、飢え死にしちゃうぞ」と父。
「せっかくサッカーのレギュラーになれたのに」と、中学生の弟。
「先輩と、やっといい感じになれたのに」と、高校生の私。
家の中にいれば安全と言われて1週間。私たちは、呑気に事態が収まるのを待っていた。
10日が過ぎた頃、テレビを見ていた弟が叫んだ。
「大変だよ。ゾンビが…」
そこには、誰かの家の窓を壊して、中に入るゾンビの姿が映っていた。
「家の中は安全じゃなかったの?」
「この家も危ない。窓をテープで補強しよう。あと、段ボールでふさいで光をもらすな」
私たちは、昼も暗い部屋で過ごすことになった。
食料はあとわずか。
この頃は、電波が届かないのかケイタイも使えない。テレビも映らなくなった。
「ヘリコプターも飛ばなくなったし、政府はこの町を完全に見捨てたんだ」
「そんな。私たち、ここでゾンビになるか、飢え死にするしかないの?」
「そんな二択いやだよ」
外でうろつくゾンビの気配に怯えながら、私たちは飢えと絶望でどうにかなりそうだった。
「何とかここを出る方法はないだろうか」
「そういえば、地下道があったわ」
「ああ、戦争中に造られた地下道か。子供の頃遊んで、よく叱られたな」
「あの地下道は、となり町まで続いていたはずよ」
父と母はこの町で生まれ育った幼なじみだった。
数十年前にコンクリートの蓋でふさがれたが、外すことは出来るはずだと言う。
翌朝私たちは、最後の望みをつなぐように、地下道を目指した。
最低限の荷物を持って、ゾンビの活動が最も鈍くなる午前9時に家を出た。
何体かのゾンビに出くわせたが、動きが鈍かったので上手く逃げられた。
しつこいゾンビには、サッカーで鍛えた弟の蹴りをくらわせた。
地下道の蓋は重かったけれど、家族で力を合わせてこじあけた。
中は黴臭くネズミや虫がいて気持ち悪かったけれど、私たちはこんなことで負けない。
ここを抜ければ、普通の暮らしに戻れるのだ。
少し水が溜まった暗い地下道を進み、ようやく出口にたどり着いた。
「ああ、思ったより蓋がスムーズに開いてよかった」
「もう怯えることなく外を歩けるのね」
「腹減った。何か食べよう」
「あたし、服買いたい」
となり町は、静かだった。
「誰も歩いてないわ」「大通りに出たら車を拾おう」
しかし、大通りには車どころか、人の姿もない。
「父さん、あれ見て」
弟が指さす先には、何もなかった。
ビルも家も、すべての建物が、粉々に壊されていた。
「どういうこと?」
そこに、青い顔をした数人の男女が走ってきた。
「どうしたんです?何かあったんですか?」
「宇宙生物だよ。宇宙生物が現れて、人間を片っ端から捕まえて食うんだ」
「なんだって?」
「あんたたちは、どこからきたんだ」
「Z地区だよ」
「え?どうやって来たの?」
「地下道を通って来たんだ」
「案内してくれ。Z地区に逃げよう」
「いや、でもあそこにはゾンビが…」
「宇宙生物はゾンビは食わないらしい。あいつらに食われるくらいなら、ゾンビになった方がマシだ」
「宇宙生物に食われるか、ゾンビになるか」
「いやだ…そんな二択」
不吉によどんだ黒い空を見上げながら、私たちはのろのろと地下道に戻った。
さて、この家族、どうなるでしょうか。
1、ゾンビになる 2、助かる

にほんブログ村
事の始まりは、ひとりの渡航者だった。
海外から帰国した男が、体調を崩してこの町の病院に入院した。
原因不明のウイルスに感染していた男は、やがて化物に姿を変え、病院の人を次々に襲った。
それは、ゾンビウイルスと呼ばれ、噛まれた人はゾンビになってまた人を襲う。
町に増えたゾンビに打つ手はなく、政府は病院周辺の地区に高い鉄の塀を立て、完全に隔離した。
私たち家族は、ゾンビに感染していない。
だけど同じように隔離され、ここから出ることができない。
塀の上に付けられたカメラと、ヘリコプターからの映像が繰り返しテレビで流された。
『Z地区のゾンビの数は、日に日に増えています。政府は特効薬の開発を急がせています。まだ感染していないみなさん。希望を持って頑張りましょう』
「いったいいつまで待てばいいの?買い物も行けないし、食糧だっていつまで持つか」と母。
「ゾンビになる前に、飢え死にしちゃうぞ」と父。
「せっかくサッカーのレギュラーになれたのに」と、中学生の弟。
「先輩と、やっといい感じになれたのに」と、高校生の私。
家の中にいれば安全と言われて1週間。私たちは、呑気に事態が収まるのを待っていた。
10日が過ぎた頃、テレビを見ていた弟が叫んだ。
「大変だよ。ゾンビが…」
そこには、誰かの家の窓を壊して、中に入るゾンビの姿が映っていた。
「家の中は安全じゃなかったの?」
「この家も危ない。窓をテープで補強しよう。あと、段ボールでふさいで光をもらすな」
私たちは、昼も暗い部屋で過ごすことになった。
食料はあとわずか。
この頃は、電波が届かないのかケイタイも使えない。テレビも映らなくなった。
「ヘリコプターも飛ばなくなったし、政府はこの町を完全に見捨てたんだ」
「そんな。私たち、ここでゾンビになるか、飢え死にするしかないの?」
「そんな二択いやだよ」
外でうろつくゾンビの気配に怯えながら、私たちは飢えと絶望でどうにかなりそうだった。
「何とかここを出る方法はないだろうか」
「そういえば、地下道があったわ」
「ああ、戦争中に造られた地下道か。子供の頃遊んで、よく叱られたな」
「あの地下道は、となり町まで続いていたはずよ」
父と母はこの町で生まれ育った幼なじみだった。
数十年前にコンクリートの蓋でふさがれたが、外すことは出来るはずだと言う。
翌朝私たちは、最後の望みをつなぐように、地下道を目指した。
最低限の荷物を持って、ゾンビの活動が最も鈍くなる午前9時に家を出た。
何体かのゾンビに出くわせたが、動きが鈍かったので上手く逃げられた。
しつこいゾンビには、サッカーで鍛えた弟の蹴りをくらわせた。
地下道の蓋は重かったけれど、家族で力を合わせてこじあけた。
中は黴臭くネズミや虫がいて気持ち悪かったけれど、私たちはこんなことで負けない。
ここを抜ければ、普通の暮らしに戻れるのだ。
少し水が溜まった暗い地下道を進み、ようやく出口にたどり着いた。
「ああ、思ったより蓋がスムーズに開いてよかった」
「もう怯えることなく外を歩けるのね」
「腹減った。何か食べよう」
「あたし、服買いたい」
となり町は、静かだった。
「誰も歩いてないわ」「大通りに出たら車を拾おう」
しかし、大通りには車どころか、人の姿もない。
「父さん、あれ見て」
弟が指さす先には、何もなかった。
ビルも家も、すべての建物が、粉々に壊されていた。
「どういうこと?」
そこに、青い顔をした数人の男女が走ってきた。
「どうしたんです?何かあったんですか?」
「宇宙生物だよ。宇宙生物が現れて、人間を片っ端から捕まえて食うんだ」
「なんだって?」
「あんたたちは、どこからきたんだ」
「Z地区だよ」
「え?どうやって来たの?」
「地下道を通って来たんだ」
「案内してくれ。Z地区に逃げよう」
「いや、でもあそこにはゾンビが…」
「宇宙生物はゾンビは食わないらしい。あいつらに食われるくらいなら、ゾンビになった方がマシだ」
「宇宙生物に食われるか、ゾンビになるか」
「いやだ…そんな二択」
不吉によどんだ黒い空を見上げながら、私たちはのろのろと地下道に戻った。
さて、この家族、どうなるでしょうか。
1、ゾンビになる 2、助かる
にほんブログ村



