前の10件 | -
行列の女 [男と女ストーリー]
信号待ちの車の中から、ラーメン屋の行列を見ていた。
人気のラーメンに、20人ほどが並んでいる。
その中に、サキがいた。思わず「ウソだろ」とつぶやいた。
サキは僕の元カノで、行列が大嫌いだった。
「ラーメン食べるために並ぶなんてバカみたい。絶対に嫌よ。行列に並ぶくらいならカップ麺を食べるわ」
そう言っていたサキが行列に並んで、楽しそうに笑っている。
隣にいるのは新しい彼だろうか。背の高い男と寄り添っている。
クラクションを鳴らされて、車を発進させた。
別れて3年。僕たちはとてもうまくいっていたけど、突然フラれた。
行列も人混みも嫌いなサキに合わせて、デートはもっぱら家。
テレビで行列の店やイベントを見て「うんざりするわ。バカみたい」と顔をしかめたサキに、「本当にそうだね」と一緒に笑った。
そんなサキが、あんなに楽しそうに行列に並んでいたなんて。
人って変わるんだな。
その日をきっかけに、サキを見かけることが多くなった。
サキはいつも行列に並んでいた。
人気スイーツの店、テーマパークのアトラクション、ショッピングモールのくじ引き。
男と一緒の時もあれば、ひとりの時もある。
いつでもサキは楽しそうに並んでいた。
そしてとうとう、サキが僕に気づいた。
人気のホットドック売るキッチンカーに並んだ時、僕の前にサキがいた。
「あれ? やだ、久しぶりね」
「3年ぶりだね」
「あっ、そうか。ここ、あなたの会社の近くだったね」
「うん。たまに買いに来るんだ。サキはどうして?」
「彼の家がこの近くなの」
「ふうん、そうなんだ。前に見かけたことあるよ。背の高い人だね」
「うん。すごいイケメンなの。5人待ちだったの」
「5人待ち?」
「そう、やっと順番が来たの。待った甲斐があったわ。今はすごく幸せ」
「待つの、嫌いじゃなかった?」
「たくさん待つからこそ、本当に欲しいものに出会えるの。あたし、それが解ってから待つのが楽しくて」
「へえ」
「簡単に手に入るものってつまらないし、飽きるのよ。物も男もね」
「へ、へえ」
「今の彼は2年も待ったのよ」
「2年・・・」
かつてサキは言っていた。
「レストランの予約が2年先まで埋まってるなんて信じられない。そんな先のことわからないわよねえ。本当にバカみたい」
人って変わるな。
「あたし、今すごく頑張ってるの。6番目に彼を取られないようにしなくちゃね」
サキはキラキラしていた。きれいになった。
チリドックを2個買って、楽しそうに帰って行った。
ひとりで食べたチリドックは、並んだ割にたいして美味しくなかった。
人気のラーメンに、20人ほどが並んでいる。
その中に、サキがいた。思わず「ウソだろ」とつぶやいた。
サキは僕の元カノで、行列が大嫌いだった。
「ラーメン食べるために並ぶなんてバカみたい。絶対に嫌よ。行列に並ぶくらいならカップ麺を食べるわ」
そう言っていたサキが行列に並んで、楽しそうに笑っている。
隣にいるのは新しい彼だろうか。背の高い男と寄り添っている。
クラクションを鳴らされて、車を発進させた。
別れて3年。僕たちはとてもうまくいっていたけど、突然フラれた。
行列も人混みも嫌いなサキに合わせて、デートはもっぱら家。
テレビで行列の店やイベントを見て「うんざりするわ。バカみたい」と顔をしかめたサキに、「本当にそうだね」と一緒に笑った。
そんなサキが、あんなに楽しそうに行列に並んでいたなんて。
人って変わるんだな。
その日をきっかけに、サキを見かけることが多くなった。
サキはいつも行列に並んでいた。
人気スイーツの店、テーマパークのアトラクション、ショッピングモールのくじ引き。
男と一緒の時もあれば、ひとりの時もある。
いつでもサキは楽しそうに並んでいた。
そしてとうとう、サキが僕に気づいた。
人気のホットドック売るキッチンカーに並んだ時、僕の前にサキがいた。
「あれ? やだ、久しぶりね」
「3年ぶりだね」
「あっ、そうか。ここ、あなたの会社の近くだったね」
「うん。たまに買いに来るんだ。サキはどうして?」
「彼の家がこの近くなの」
「ふうん、そうなんだ。前に見かけたことあるよ。背の高い人だね」
「うん。すごいイケメンなの。5人待ちだったの」
「5人待ち?」
「そう、やっと順番が来たの。待った甲斐があったわ。今はすごく幸せ」
「待つの、嫌いじゃなかった?」
「たくさん待つからこそ、本当に欲しいものに出会えるの。あたし、それが解ってから待つのが楽しくて」
「へえ」
「簡単に手に入るものってつまらないし、飽きるのよ。物も男もね」
「へ、へえ」
「今の彼は2年も待ったのよ」
「2年・・・」
かつてサキは言っていた。
「レストランの予約が2年先まで埋まってるなんて信じられない。そんな先のことわからないわよねえ。本当にバカみたい」
人って変わるな。
「あたし、今すごく頑張ってるの。6番目に彼を取られないようにしなくちゃね」
サキはキラキラしていた。きれいになった。
チリドックを2個買って、楽しそうに帰って行った。
ひとりで食べたチリドックは、並んだ割にたいして美味しくなかった。
赤ずきんちゃん、マジで気を付けて [名作パロディー]
どうも、あたし、赤ずきん。
あたしとおばあさんが、オオカミに食べられたのに生きて帰ったあの話。
今じゃすっかり有名になって、あたしはまさに時の人。
雑誌の取材やテレビに引っ張りだこなの。
あたしが歩いたあの森は、聖地巡礼とばかりに人が集まって、屋台やキッチンカーまで出る始末よ。
どこにいてもサインを求められて大変なの。
もちろん、中にはひねくれたアンチもいるわ。
ワイルドで野蛮なオオカミ推しもいるの。
「オオカミ様が沈められた川よ」なんて言いながら手を合わせてる。
別にいいけどね。
可哀想なのはお母さんよ。
子どもを一人でお遣いに出したことが、倫理的にどうなの?って言われてる。
そのせいであたし、一人で外出禁止になっちゃった。
おまけにあの森、子どもだけで歩いちゃいけない決まりが出来たの。
おばあさまに会いたいなあ。あの森、通りたいなあ。
おばあさま、毎日マスコミが来て疲れちゃったみたいだから、慰めてあげたいの。
そこであたしは考えた。
赤いずきんを脱げばいいのよ。
ずきんを脱げば、そこら辺にいるただの子どもと変わらないもん。
だからあたしはずきんを脱いで、こっそり家を出たの。
森の入り口には、見張り番がいた。子どもが一人で入らないように見張っているの。
あたしは、前を歩く毛むくじゃらのおじさんを呼び止めて言った。
「おじさん、一緒に森に入って。親子の振りをしてほしいの」
おじさんは「お安い御用さ」と笑って、一緒に森に入ってくれた。
「お嬢ちゃん、どこへ行くんだい?」
「おばあさまのところよ」
「えっ、おばあさまのところに行くのに、手ぶらなのかい?」
「手ぶらじゃダメなの?」
「そりゃあそうさ。手土産は必要だろう。そうだ、この先においしいケーキ屋があるよ」
「わあ、食べたい。でもあたし、お金持ってないの」
「おじさんが買ってあげるよ」
「本当? あたし、モンブランがいいなあ」
毛むくじゃらだけど優しいおじさんだな。
あたしはケーキの種類を思い浮かべながら、おじさんの後についていった。
あれ、けっこう遠いな。聖地巡礼のコースからも外れてる。
「おじさん、ケーキ屋さんはどこにあるの?早くおばあさまに会いたいんだけど」
「もうすぐだよ。おばあさんの家とは逆方向だけど、そんなに遠くないから」
「ふうん」
ん? なんか変。どうして初めて会ったおじさんが、おばあさまの家を知っているの?
しかも、このシチュエーション、前にもあったわ。
「さてはあんた、オオカミでしょ。生きていたのね」
「へっ、バレちゃ仕方ねえ。そうさ、おまえのせいでひどい目に遭ったオオカミ様だ。今度こそちゃんと食ってやる」
「ずきんを脱いできたのに、どうしてわかったのよ」
「赤いずきんがなくても、匂いで分かるんだよ。何しろ一度食ってるからな」
オオカミが大きな口で笑った。
ヤバい。また食べられる。
でも、この森は今や観光地。そうよ。何とかなるわ。あたしは、大声で叫んだ。
「オオカミ推しのみなさ~ん。ここに本物がいますよー」
あたしの声を聞きつけた女たちが、雪崩のように押し寄せて来た。
「オオカミ様」「ワイルドでステキ」「ガオ~って言ってみて」
たちまち女たちに囲まれたオオカミは「まいったなあ~、こんなに食えないよ~」と言いながらデレデレしてた。
さあ、この隙に逃げましょ。ああ、助かった。
あたしは無事に、おばあさまの家に着いた。
「おばあさま~、こんにちは」
玄関に出て来たおばあさまは、あたしを見てひとこと。
「どこのガキだい?サインはお断りだよ」
ああ、赤いずきんを被らないと認識してもらえないあたしって、いったい何?
あたしとおばあさんが、オオカミに食べられたのに生きて帰ったあの話。
今じゃすっかり有名になって、あたしはまさに時の人。
雑誌の取材やテレビに引っ張りだこなの。
あたしが歩いたあの森は、聖地巡礼とばかりに人が集まって、屋台やキッチンカーまで出る始末よ。
どこにいてもサインを求められて大変なの。
もちろん、中にはひねくれたアンチもいるわ。
ワイルドで野蛮なオオカミ推しもいるの。
「オオカミ様が沈められた川よ」なんて言いながら手を合わせてる。
別にいいけどね。
可哀想なのはお母さんよ。
子どもを一人でお遣いに出したことが、倫理的にどうなの?って言われてる。
そのせいであたし、一人で外出禁止になっちゃった。
おまけにあの森、子どもだけで歩いちゃいけない決まりが出来たの。
おばあさまに会いたいなあ。あの森、通りたいなあ。
おばあさま、毎日マスコミが来て疲れちゃったみたいだから、慰めてあげたいの。
そこであたしは考えた。
赤いずきんを脱げばいいのよ。
ずきんを脱げば、そこら辺にいるただの子どもと変わらないもん。
だからあたしはずきんを脱いで、こっそり家を出たの。
森の入り口には、見張り番がいた。子どもが一人で入らないように見張っているの。
あたしは、前を歩く毛むくじゃらのおじさんを呼び止めて言った。
「おじさん、一緒に森に入って。親子の振りをしてほしいの」
おじさんは「お安い御用さ」と笑って、一緒に森に入ってくれた。
「お嬢ちゃん、どこへ行くんだい?」
「おばあさまのところよ」
「えっ、おばあさまのところに行くのに、手ぶらなのかい?」
「手ぶらじゃダメなの?」
「そりゃあそうさ。手土産は必要だろう。そうだ、この先においしいケーキ屋があるよ」
「わあ、食べたい。でもあたし、お金持ってないの」
「おじさんが買ってあげるよ」
「本当? あたし、モンブランがいいなあ」
毛むくじゃらだけど優しいおじさんだな。
あたしはケーキの種類を思い浮かべながら、おじさんの後についていった。
あれ、けっこう遠いな。聖地巡礼のコースからも外れてる。
「おじさん、ケーキ屋さんはどこにあるの?早くおばあさまに会いたいんだけど」
「もうすぐだよ。おばあさんの家とは逆方向だけど、そんなに遠くないから」
「ふうん」
ん? なんか変。どうして初めて会ったおじさんが、おばあさまの家を知っているの?
しかも、このシチュエーション、前にもあったわ。
「さてはあんた、オオカミでしょ。生きていたのね」
「へっ、バレちゃ仕方ねえ。そうさ、おまえのせいでひどい目に遭ったオオカミ様だ。今度こそちゃんと食ってやる」
「ずきんを脱いできたのに、どうしてわかったのよ」
「赤いずきんがなくても、匂いで分かるんだよ。何しろ一度食ってるからな」
オオカミが大きな口で笑った。
ヤバい。また食べられる。
でも、この森は今や観光地。そうよ。何とかなるわ。あたしは、大声で叫んだ。
「オオカミ推しのみなさ~ん。ここに本物がいますよー」
あたしの声を聞きつけた女たちが、雪崩のように押し寄せて来た。
「オオカミ様」「ワイルドでステキ」「ガオ~って言ってみて」
たちまち女たちに囲まれたオオカミは「まいったなあ~、こんなに食えないよ~」と言いながらデレデレしてた。
さあ、この隙に逃げましょ。ああ、助かった。
あたしは無事に、おばあさまの家に着いた。
「おばあさま~、こんにちは」
玄関に出て来たおばあさまは、あたしを見てひとこと。
「どこのガキだい?サインはお断りだよ」
ああ、赤いずきんを被らないと認識してもらえないあたしって、いったい何?
桜、散る
春の嵐で、桜の花が散ってしまった。
せっかくきれいに咲いたのに。
もっと咲いていたかっただろうに、無情にも儚い命。
だけどそれは、桜に限ったことではない。
仕事を突然クビになった。
「ごめんね。上の判断だからさ」
上司は気の毒そうに言いながら、どこかホッとしたような顔をした。
リストラの噂があったとき、切られるのは私だろうと思った。
子どものことで休みも多かったし、残業は出来ない。陰で色々言われていたのも知っていた。
頑張ったのに。スキルは私の方が絶対上なのに。
時代は変わっても、女が普通に働くのって難しい。
「子どもが小学校に上がるまでは、家にいてあげたほうがいいわよ」
なんてことを言う人は、いまだに多い。
だったら毎月、無条件で10万円援助してくれますか、って話よ。
マイホームだって欲しいし、子どもの学費だって貯めなきゃいけないんだから。
ああ、明日ハローワークに、次の仕事を探しに行こう。
職種とかスキルとか、もうそんなのどうでもいい。
土日休みで残業がなくて、時間給が取れて、子育て世代が多い職場。
早く働きたい。止まっていたら腐ってしまいそう。
4時になるのを待って、保育園に息子の春希(5歳)を迎えに行った。
天気がいいから歩いて行った。いつもより早いお迎えだ。
春希と手を繋ぎながら、川沿いの桜並木を歩く。
きのうの雨風で、花びらが無残に散っている。
「あーあ、花が散ってかわいそう」
(そして私もクビになってかわいそう)これは心の声。
春希が、首をかしげながら言った。
「ママ、桜は散ってもかわいそうじゃないよ」
「どうして?」
「だって見て。地面も川もピンク色。散ってもきれいだよ」
ニッコリ笑う春希に、桜吹雪が降り注ぐ。
はっとした。そんなふうに考えたこともなかった。
そうだ。きれいに咲くのも今だけなら、きれいに散るのも今だけ。
ましてや道路や川をピンクに染めていくなんて、まさに今だけ。
「本当だね。春希、そんなことを言うようになったんだね」
「だってぼく、もう5歳だよ」
「そうか、そうだよね」
肩の力がストンと抜けた。
今だけ。そうだ。春希とこうして桜の下を歩けるのは、ずっとじゃない。
焦って仕事を探すより、もう少しのんびり今を楽しむのもいいかもしれない。
たぶん私は、仕事を失ったことよりも、クビになったことが悔しくて仕方なかった。
だから間を開けずに働きたかっただけなんだ。
息子の成長を喜ぶ余裕も失くしてたな。
よし、焦らないで、自分を生かせる仕事を探そう。
そして春希との時間を、少しでも長く楽しむんだ。
「あっ、ママ、明日のお迎えは遅くていいよ。リカちゃんと遊ぶ約束してるから」
あらら、成長って、ちょっと寂しいものね。
せっかくきれいに咲いたのに。
もっと咲いていたかっただろうに、無情にも儚い命。
だけどそれは、桜に限ったことではない。
仕事を突然クビになった。
「ごめんね。上の判断だからさ」
上司は気の毒そうに言いながら、どこかホッとしたような顔をした。
リストラの噂があったとき、切られるのは私だろうと思った。
子どものことで休みも多かったし、残業は出来ない。陰で色々言われていたのも知っていた。
頑張ったのに。スキルは私の方が絶対上なのに。
時代は変わっても、女が普通に働くのって難しい。
「子どもが小学校に上がるまでは、家にいてあげたほうがいいわよ」
なんてことを言う人は、いまだに多い。
だったら毎月、無条件で10万円援助してくれますか、って話よ。
マイホームだって欲しいし、子どもの学費だって貯めなきゃいけないんだから。
ああ、明日ハローワークに、次の仕事を探しに行こう。
職種とかスキルとか、もうそんなのどうでもいい。
土日休みで残業がなくて、時間給が取れて、子育て世代が多い職場。
早く働きたい。止まっていたら腐ってしまいそう。
4時になるのを待って、保育園に息子の春希(5歳)を迎えに行った。
天気がいいから歩いて行った。いつもより早いお迎えだ。
春希と手を繋ぎながら、川沿いの桜並木を歩く。
きのうの雨風で、花びらが無残に散っている。
「あーあ、花が散ってかわいそう」
(そして私もクビになってかわいそう)これは心の声。
春希が、首をかしげながら言った。
「ママ、桜は散ってもかわいそうじゃないよ」
「どうして?」
「だって見て。地面も川もピンク色。散ってもきれいだよ」
ニッコリ笑う春希に、桜吹雪が降り注ぐ。
はっとした。そんなふうに考えたこともなかった。
そうだ。きれいに咲くのも今だけなら、きれいに散るのも今だけ。
ましてや道路や川をピンクに染めていくなんて、まさに今だけ。
「本当だね。春希、そんなことを言うようになったんだね」
「だってぼく、もう5歳だよ」
「そうか、そうだよね」
肩の力がストンと抜けた。
今だけ。そうだ。春希とこうして桜の下を歩けるのは、ずっとじゃない。
焦って仕事を探すより、もう少しのんびり今を楽しむのもいいかもしれない。
たぶん私は、仕事を失ったことよりも、クビになったことが悔しくて仕方なかった。
だから間を開けずに働きたかっただけなんだ。
息子の成長を喜ぶ余裕も失くしてたな。
よし、焦らないで、自分を生かせる仕事を探そう。
そして春希との時間を、少しでも長く楽しむんだ。
「あっ、ママ、明日のお迎えは遅くていいよ。リカちゃんと遊ぶ約束してるから」
あらら、成長って、ちょっと寂しいものね。
夜鳴き猫
午前二時に、聞こえてくるニャルメラの音。
ああ、今日も来た。夜鳴き猫の屋台。
そうなの、この時間になると私、無性に猫を撫でたくなるの。
パジャマのまま、サンダルを突っかけて外に出た。
「おじさん、夜鳴き猫一丁」
「へい、毎度」
おじさんが、屋台の下から黒い猫を取り出して、私の手に乗せる。
黒い猫は、私の胸に顔をうずめて「にゃー」と鳴く。
ああ、なんて幸せ。なんて癒されるひと時。
ニャルメラを聞いた客が、次々とやってくる。
「おじさん、私も夜鳴き猫」
「私もお願い」
私と同じように、一人暮らしでペット禁止のアパートで暮らす女たちが、夜鳴き猫を求めてやって来る。
みんな猫を胸に抱き、その体を優しく撫でる。
猫は気持ちよさそうに甘えてくる。
ああ、なんて可愛い。なんて愛おしい。
酔っ払いの男がやって来た。
「おやじ、ラーメン一丁」
ラーメンの屋台と勘違いしている。女たちの冷たい視線。
「お客さん、うちは夜鳴きそばじゃなくて、夜鳴き猫を提供しているんですよ」
「猫だと? ほう、おもしれえ。じゃあ、その夜鳴き猫一丁」
「へい、毎度」
おじさんが酔っ払いに猫を渡すと、猫はいきなり「ふぎゃー」と鳴き、酔っ払いの顔を引っ掻いた。
「いててて。何するんだ、この猫!」
酔っ払いは猫をぶん投げて、ヒイヒイ言いながら帰った。
「猫は酔っ払いが嫌いなのね」
「男が嫌いなのかしら」
「ふふ、私たちにはこんなに懐いて可愛いのにね」
私たちは、猫との時間を存分に楽しんで、それぞれのアパートに帰る。
「バイバイ、また明日」
「猫ちゃんのおかげで、明日も頑張れるわ」
そして私は、ぐっすり眠る。
猫のぬくもりと、可愛い表情を思い出しながら眠る。
ああ、明日もまた、夜鳴き猫を撫でに行こう。
***
朝が来た。
夜鳴き猫屋は、仕事を終えて空き地に行くと「ごくろうさん」と、手をパンと叩いた。
屋台の下にいた猫たちがのっそり出て来た。
猫たちは、朝日に照らされて、徐々に大きくなる。
そしてその姿は、みすぼらしい服を着た男たちに変わった。
「今夜の報酬だよ」
男たちは、僅かな食べ物を受け取って公園に帰っていく。
男たちはホームレスだ。
夜鳴き猫屋は、ホームレスたちを猫に変え、夜鳴き猫屋を営んでいた。
ホームレスたちは僅かな食べ物でも文句を言わず、喜んで男に従う。
なぜなら無条件で女の胸に抱かれ、優しく撫でてもらえるからだ。
****
ああ、ニャルメラが聞こえる。
今夜はどの子を撫でようかしら。
ああ、今日も来た。夜鳴き猫の屋台。
そうなの、この時間になると私、無性に猫を撫でたくなるの。
パジャマのまま、サンダルを突っかけて外に出た。
「おじさん、夜鳴き猫一丁」
「へい、毎度」
おじさんが、屋台の下から黒い猫を取り出して、私の手に乗せる。
黒い猫は、私の胸に顔をうずめて「にゃー」と鳴く。
ああ、なんて幸せ。なんて癒されるひと時。
ニャルメラを聞いた客が、次々とやってくる。
「おじさん、私も夜鳴き猫」
「私もお願い」
私と同じように、一人暮らしでペット禁止のアパートで暮らす女たちが、夜鳴き猫を求めてやって来る。
みんな猫を胸に抱き、その体を優しく撫でる。
猫は気持ちよさそうに甘えてくる。
ああ、なんて可愛い。なんて愛おしい。
酔っ払いの男がやって来た。
「おやじ、ラーメン一丁」
ラーメンの屋台と勘違いしている。女たちの冷たい視線。
「お客さん、うちは夜鳴きそばじゃなくて、夜鳴き猫を提供しているんですよ」
「猫だと? ほう、おもしれえ。じゃあ、その夜鳴き猫一丁」
「へい、毎度」
おじさんが酔っ払いに猫を渡すと、猫はいきなり「ふぎゃー」と鳴き、酔っ払いの顔を引っ掻いた。
「いててて。何するんだ、この猫!」
酔っ払いは猫をぶん投げて、ヒイヒイ言いながら帰った。
「猫は酔っ払いが嫌いなのね」
「男が嫌いなのかしら」
「ふふ、私たちにはこんなに懐いて可愛いのにね」
私たちは、猫との時間を存分に楽しんで、それぞれのアパートに帰る。
「バイバイ、また明日」
「猫ちゃんのおかげで、明日も頑張れるわ」
そして私は、ぐっすり眠る。
猫のぬくもりと、可愛い表情を思い出しながら眠る。
ああ、明日もまた、夜鳴き猫を撫でに行こう。
***
朝が来た。
夜鳴き猫屋は、仕事を終えて空き地に行くと「ごくろうさん」と、手をパンと叩いた。
屋台の下にいた猫たちがのっそり出て来た。
猫たちは、朝日に照らされて、徐々に大きくなる。
そしてその姿は、みすぼらしい服を着た男たちに変わった。
「今夜の報酬だよ」
男たちは、僅かな食べ物を受け取って公園に帰っていく。
男たちはホームレスだ。
夜鳴き猫屋は、ホームレスたちを猫に変え、夜鳴き猫屋を営んでいた。
ホームレスたちは僅かな食べ物でも文句を言わず、喜んで男に従う。
なぜなら無条件で女の胸に抱かれ、優しく撫でてもらえるからだ。
****
ああ、ニャルメラが聞こえる。
今夜はどの子を撫でようかしら。
発売になりました

「ラストで君はゾッとする」PHP研究所
ついに発売になりました!
先週見本が届いて、いち早く読むことができました。
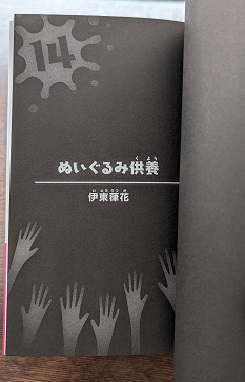
私が書いた「ぬいぐるみ供養」が、掲載されています。
よかったらぜひ、手に取ってみて下さい。
子ども向きだけど、どのお話もゾクッとなります。
さあ、雨が止んだら、本屋さんに行こう!!
代わってよ [ホラー]
「代わって。ねえ、代わってよ」
真夜中に声がした。それは、誰かの声じゃない。
僕の声だった。
「代わって。ねえ、代わってよ」
怖くて、目が開けられない。耳をふさいでも無駄だ。
だって、声は僕の体の中から聞こえている。
「代わって。ねえ、代わってよ」
「いやだよ」と答えてみた。
「ケチだな」と声がした。不思議だ。僕の中で、僕と僕が会話している。
怖くなって起き上がって、おかあさんのところに行った。
「怖い夢を見たのね」
おかあさんは優しく背中を撫でてくれた。もう声は聞こえない。
僕は安心して眠った。
翌朝、おばあちゃんに話した。
「その子は、おそらく双子のかたわれだ」
おばあちゃんはそう言って、仏壇に手を合わせた。
「かたわれ?」
「もうひとりの、おまえだよ」
「もうひとりの、僕?」
「おまえは、双子で生まれるはずだった。だけど、どういうわけかひとりで生まれた」
かたわれ。双子の、かたわれ。
僕の中に、もう一人の僕がいるってこと?
「おばあちゃん、僕、どうしたらいいの?」
「さあね、あたしにとっては、どちらも可愛い孫だから」
おばあちゃんは、ガサガサの手で僕を撫でた。
「そろそろ、代わってあげてもいいかもしれないねえ」
その夜、また声がした。
「代わって。ねえ、代わってよ」
「代わるって、なに?」
「もう七年も生きたんだから、そろそろいいでしょう。代わってよ」
「代わるって、なに? 代わったらどうなるの?」
「大丈夫。代わっても誰も気づかない。何も変わらない」
僕の中から、僕が出てきた。
ゆらゆらと揺れながら、僕の体を離れていく。
「怖いよ。おかあさん」
叫んでみたけど声が出ない。
起き上がりたいけど、起きられない。
「代わってくれてありがとう」
代わったの? いつ代わったの? 今の僕は僕なの?
それともかたわれなの?
ゆらゆら揺れて消えたのは、僕なの?
それともかたわれなの?
「大丈夫。代わっても、何も変わらない」
起き上がって、鏡を見た。
何も変わっていない。
そう、何も、変わっていない。
僕はぐっすり眠って、太陽の光で目覚めた。
まるで初めて迎える朝みたいに、気分が良かった。
***
少し前に書き止めておいた話です。
爽やかな春にホラーっていうのもどうかな、と思いましたが、最近話が思いつかなくて。
頭がさび付いてきたかもしれません。
真夜中に声がした。それは、誰かの声じゃない。
僕の声だった。
「代わって。ねえ、代わってよ」
怖くて、目が開けられない。耳をふさいでも無駄だ。
だって、声は僕の体の中から聞こえている。
「代わって。ねえ、代わってよ」
「いやだよ」と答えてみた。
「ケチだな」と声がした。不思議だ。僕の中で、僕と僕が会話している。
怖くなって起き上がって、おかあさんのところに行った。
「怖い夢を見たのね」
おかあさんは優しく背中を撫でてくれた。もう声は聞こえない。
僕は安心して眠った。
翌朝、おばあちゃんに話した。
「その子は、おそらく双子のかたわれだ」
おばあちゃんはそう言って、仏壇に手を合わせた。
「かたわれ?」
「もうひとりの、おまえだよ」
「もうひとりの、僕?」
「おまえは、双子で生まれるはずだった。だけど、どういうわけかひとりで生まれた」
かたわれ。双子の、かたわれ。
僕の中に、もう一人の僕がいるってこと?
「おばあちゃん、僕、どうしたらいいの?」
「さあね、あたしにとっては、どちらも可愛い孫だから」
おばあちゃんは、ガサガサの手で僕を撫でた。
「そろそろ、代わってあげてもいいかもしれないねえ」
その夜、また声がした。
「代わって。ねえ、代わってよ」
「代わるって、なに?」
「もう七年も生きたんだから、そろそろいいでしょう。代わってよ」
「代わるって、なに? 代わったらどうなるの?」
「大丈夫。代わっても誰も気づかない。何も変わらない」
僕の中から、僕が出てきた。
ゆらゆらと揺れながら、僕の体を離れていく。
「怖いよ。おかあさん」
叫んでみたけど声が出ない。
起き上がりたいけど、起きられない。
「代わってくれてありがとう」
代わったの? いつ代わったの? 今の僕は僕なの?
それともかたわれなの?
ゆらゆら揺れて消えたのは、僕なの?
それともかたわれなの?
「大丈夫。代わっても、何も変わらない」
起き上がって、鏡を見た。
何も変わっていない。
そう、何も、変わっていない。
僕はぐっすり眠って、太陽の光で目覚めた。
まるで初めて迎える朝みたいに、気分が良かった。
***
少し前に書き止めておいた話です。
爽やかな春にホラーっていうのもどうかな、と思いましたが、最近話が思いつかなくて。
頭がさび付いてきたかもしれません。
ママの第二ボタン [男と女ストーリー]
ブラウスのボタンが取れちゃったから、似たようなボタンを探そうと思って、ママの裁縫箱を開けた。
ママの裁縫箱には、とにかくたくさんのボタンが入っている。
その中に、男子学生の制服のボタンがあった。
「ママ、これって、第二ボタンってやつ? 卒業式で彼氏からもらうやつ?」
「あー、そうだね。制服の第二ボタンだね」
「誰にもらったの? JKだったころの彼氏?」
「憶えてないわね」
「うそ。今でも大切に取ってあるのに、憶えてないの?」
「憶えてないわよ。そんな昔の話」
ママの初恋の人って、全然想像できないんだけど。
パパとは、30歳を過ぎてからお見合い結婚したって聞いた。
ママは年頃になっても全然恋人が出来なくて、おばあちゃんの方が焦って相手を探したそうだ。
当たり前だけど、ママにもちゃんと初恋があったんだよね。どんな人だろう。
ママは面食いじゃないよね。だってパパを選んだんだし。あっ、パパを選んだのはおばあちゃんか。
翌日、おばあちゃんの家に行って、ママの卒業アルバムを見せてもらった。
ママはメガネに三つ編みの、いかにも優等生って感じだ。
「本当に真面目な子でね、彼氏なんていなかったと思うよ。あたしが知る限り、第二ボタンをもらうような男の子はいなかったわね」
「そうか。ねえ、おばあちゃん。パパとママはお見合い結婚なんでしょう」
「そうよ。3回目のお見合いで決まったの。それまでは全然乗り気じゃなかったのに、あんたのパパとはビックリするほど早く話が進んだのよ」
「好みのタイプだったのかな?」
「同じ年だし、話が合ったんでしょ」
「今も仲良しだよ。おばあちゃん、すごいね。私もお見合いしようかな」
「何言ってるの。あんたはまだ高校生でしょ」
結局ママの初恋に関しては、何もわからなかった。
夜、帰って来たパパに聞いた。
「ねえパパ、高校の卒業式の日、第二ボタン誰かにあげた?」
「いや、あげてないよ。パパが卒業したのは男子校だしな。あっ、でも、第二ボタン取られたことあるな」
「取られた? 男子校で? それってBL?」
「違う、違う、パパは家の都合で一度転校してるんだ。前の高校が共学で、転校する日にボタンを取られた。話したこともない女子がいきなりハサミを持って近づいてきて、パパの第二ボタンを取っていった。ビックリしたよ。刺されるかと思った」
「あはは。第二ボタン強盗だね。その女の子、パパのことが好きだったんだね。意外だな~。ちっともイケメンじゃないのに」
「パパだって昔はイケメンだったぞ」
「えー、マジで。ねえママ、どう思う?」
振り向くと、キッチンバサミを持ったママが、真っ赤な顔をしていた。
「ママ。ハサミ怖いよ」
「あっ、ごめん。海苔を切っていたら、話が聞こえて……」
パパがポカンと口を開けて、ハサミを持ったママを見ている。
「あのときと同じだ」
まさかの展開! 第二ボタン強盗はママだった。
あのボタンは、パパのボタンだった。
憶えてないなんて嘘。言えるわけないよね、無理やり取ったボタンだなんて。
あのボタンのおかげか、おばあちゃんのおかげか、ママはパパに再会して結婚を決めて、そして私が生まれたんだ。
ひとつのボタンにも、物語があるなあ。
もうすぐ大好きな先輩の卒業式。
ネクタイもらおうと思ったけど、やっぱりボタンにしようかな。
ママの裁縫箱には、とにかくたくさんのボタンが入っている。
その中に、男子学生の制服のボタンがあった。
「ママ、これって、第二ボタンってやつ? 卒業式で彼氏からもらうやつ?」
「あー、そうだね。制服の第二ボタンだね」
「誰にもらったの? JKだったころの彼氏?」
「憶えてないわね」
「うそ。今でも大切に取ってあるのに、憶えてないの?」
「憶えてないわよ。そんな昔の話」
ママの初恋の人って、全然想像できないんだけど。
パパとは、30歳を過ぎてからお見合い結婚したって聞いた。
ママは年頃になっても全然恋人が出来なくて、おばあちゃんの方が焦って相手を探したそうだ。
当たり前だけど、ママにもちゃんと初恋があったんだよね。どんな人だろう。
ママは面食いじゃないよね。だってパパを選んだんだし。あっ、パパを選んだのはおばあちゃんか。
翌日、おばあちゃんの家に行って、ママの卒業アルバムを見せてもらった。
ママはメガネに三つ編みの、いかにも優等生って感じだ。
「本当に真面目な子でね、彼氏なんていなかったと思うよ。あたしが知る限り、第二ボタンをもらうような男の子はいなかったわね」
「そうか。ねえ、おばあちゃん。パパとママはお見合い結婚なんでしょう」
「そうよ。3回目のお見合いで決まったの。それまでは全然乗り気じゃなかったのに、あんたのパパとはビックリするほど早く話が進んだのよ」
「好みのタイプだったのかな?」
「同じ年だし、話が合ったんでしょ」
「今も仲良しだよ。おばあちゃん、すごいね。私もお見合いしようかな」
「何言ってるの。あんたはまだ高校生でしょ」
結局ママの初恋に関しては、何もわからなかった。
夜、帰って来たパパに聞いた。
「ねえパパ、高校の卒業式の日、第二ボタン誰かにあげた?」
「いや、あげてないよ。パパが卒業したのは男子校だしな。あっ、でも、第二ボタン取られたことあるな」
「取られた? 男子校で? それってBL?」
「違う、違う、パパは家の都合で一度転校してるんだ。前の高校が共学で、転校する日にボタンを取られた。話したこともない女子がいきなりハサミを持って近づいてきて、パパの第二ボタンを取っていった。ビックリしたよ。刺されるかと思った」
「あはは。第二ボタン強盗だね。その女の子、パパのことが好きだったんだね。意外だな~。ちっともイケメンじゃないのに」
「パパだって昔はイケメンだったぞ」
「えー、マジで。ねえママ、どう思う?」
振り向くと、キッチンバサミを持ったママが、真っ赤な顔をしていた。
「ママ。ハサミ怖いよ」
「あっ、ごめん。海苔を切っていたら、話が聞こえて……」
パパがポカンと口を開けて、ハサミを持ったママを見ている。
「あのときと同じだ」
まさかの展開! 第二ボタン強盗はママだった。
あのボタンは、パパのボタンだった。
憶えてないなんて嘘。言えるわけないよね、無理やり取ったボタンだなんて。
あのボタンのおかげか、おばあちゃんのおかげか、ママはパパに再会して結婚を決めて、そして私が生まれたんだ。
ひとつのボタンにも、物語があるなあ。
もうすぐ大好きな先輩の卒業式。
ネクタイもらおうと思ったけど、やっぱりボタンにしようかな。
家電ハラスメント [コメディー]
私、疲れてます。
毎日家電に振り回されてます。
まずはホットプレート。
ピンク色でとても可愛いんです。マカロンみたいな可愛い蓋で、取っ手はイチゴ。
ショップで一目惚れして買いました。
ところがホットプレートはわがままで、パンケーキしか焼かせてくれないんです。
お好み焼きや焼きそばは、電源切って全力で拒否。
「おとぎの国には、お好み焼きも焼きそばもないわ」
餃子なんか焼こうとしたら、蓋で手をはさまれます。
「ここはおとぎの国よ。ニンニクの匂いがついたらどうしてくれるの?」
アリスだってシンデレラだって、目の前に餃子があれば食べますよね。
ああ、一度でいい。ニンニクたっぷりのタレで、焼き肉食べたーい!
それから電子レンジです。
すぐにキレて、口うるさいんです。
コンビニ弁当を温めようとした時です。
「はぁっ?なんでコンビニで温めてもらわないの?おれ今休憩中なんだけど」
「レジが混んでて」
「そんなのさあ、温めてる間に次の客の対応するから大丈夫なんだよ。だいたいさあ、いつも電気代が高いって愚痴ってる割に無駄なことしてるよね。分かったよ、温めてやるからスイッチ押せよ。あー、ほら、ブレーカー落ちた。あー、面倒くさいなあ。もう、冷えた弁当でも食ってろ」
ああ、これって、パワハラで訴えること出来ますか?
次は、コーヒーメーカーです。
コーヒーを飲んでリラックスしようと思うと、決まって話しかけてきます。
「これは、いくらのコーヒーかね?」
「200グラムで、500円くらいだったかしら」
「安い豆だな。まあいい、不景気だしな。ところで、僕には豆を挽く機能がついているのをご存知かな?ほう、知っているのに何故使わない? どうせ洗うのが面倒とか、そういう理由だろう。嘆かわしい。そういうことに手間をかけるからこそ旨いコーヒーが飲めるんだ。せっかくの素晴らしい機能を、なぜ使いこなすことが出来ないんだ。これでは宝の持ち腐れ。まあいい。安い豆でも100倍美味しく淹れたから飲みなさい」
ああ、コーヒーは美味しくても、ちっともリラックスできません。
極めつけはエアコンです、
20分ほどの外出だったので、エアコンをつけたまま出かけました。
ところが帰ってきたら部屋が寒いんです。まるで氷河期です。
なんとエアコンが、冷房になっていたのです。
「ちょっと、どうして冷房になってるの?」
「だって、室外機さんに悪くて。私は部屋の中で、冬はぬくぬく、夏はひんやり、快適に過ごしているけど、室外機さんは一年中外よ。寒くても暑くても、雨でも雪でも。室外機さんの気持ちを考えたら私、たまらくなっちゃって」
「気持ちは分かるわ。でもね、こんなに部屋を冷やしたら、電気代が高くなっちゃう。お願い、暖房に戻して」
「わかったわ。じゃあせめて、室外機さんに毛布を掛けてあげて。室外機さんの気持ちも考えてあげて。室外機さん、暖房に切り替えるわね。ごめんね、強く生きてね」
うわ、水漏れ。これってエアコンの涙? いや、迷惑なんだけど。
あー、きょうも疲れました。
ゴロンと横になったとたん「ちょっと!」と声がした。
「テレビさん、どうしました?」
「寝るなら消してよ」
「いえ、見てます」
「うそ、今、目をつぶってたわよ」
「見てるってば」(昭和のお父さんか)
毎日家電に振り回されてます。
まずはホットプレート。
ピンク色でとても可愛いんです。マカロンみたいな可愛い蓋で、取っ手はイチゴ。
ショップで一目惚れして買いました。
ところがホットプレートはわがままで、パンケーキしか焼かせてくれないんです。
お好み焼きや焼きそばは、電源切って全力で拒否。
「おとぎの国には、お好み焼きも焼きそばもないわ」
餃子なんか焼こうとしたら、蓋で手をはさまれます。
「ここはおとぎの国よ。ニンニクの匂いがついたらどうしてくれるの?」
アリスだってシンデレラだって、目の前に餃子があれば食べますよね。
ああ、一度でいい。ニンニクたっぷりのタレで、焼き肉食べたーい!
それから電子レンジです。
すぐにキレて、口うるさいんです。
コンビニ弁当を温めようとした時です。
「はぁっ?なんでコンビニで温めてもらわないの?おれ今休憩中なんだけど」
「レジが混んでて」
「そんなのさあ、温めてる間に次の客の対応するから大丈夫なんだよ。だいたいさあ、いつも電気代が高いって愚痴ってる割に無駄なことしてるよね。分かったよ、温めてやるからスイッチ押せよ。あー、ほら、ブレーカー落ちた。あー、面倒くさいなあ。もう、冷えた弁当でも食ってろ」
ああ、これって、パワハラで訴えること出来ますか?
次は、コーヒーメーカーです。
コーヒーを飲んでリラックスしようと思うと、決まって話しかけてきます。
「これは、いくらのコーヒーかね?」
「200グラムで、500円くらいだったかしら」
「安い豆だな。まあいい、不景気だしな。ところで、僕には豆を挽く機能がついているのをご存知かな?ほう、知っているのに何故使わない? どうせ洗うのが面倒とか、そういう理由だろう。嘆かわしい。そういうことに手間をかけるからこそ旨いコーヒーが飲めるんだ。せっかくの素晴らしい機能を、なぜ使いこなすことが出来ないんだ。これでは宝の持ち腐れ。まあいい。安い豆でも100倍美味しく淹れたから飲みなさい」
ああ、コーヒーは美味しくても、ちっともリラックスできません。
極めつけはエアコンです、
20分ほどの外出だったので、エアコンをつけたまま出かけました。
ところが帰ってきたら部屋が寒いんです。まるで氷河期です。
なんとエアコンが、冷房になっていたのです。
「ちょっと、どうして冷房になってるの?」
「だって、室外機さんに悪くて。私は部屋の中で、冬はぬくぬく、夏はひんやり、快適に過ごしているけど、室外機さんは一年中外よ。寒くても暑くても、雨でも雪でも。室外機さんの気持ちを考えたら私、たまらくなっちゃって」
「気持ちは分かるわ。でもね、こんなに部屋を冷やしたら、電気代が高くなっちゃう。お願い、暖房に戻して」
「わかったわ。じゃあせめて、室外機さんに毛布を掛けてあげて。室外機さんの気持ちも考えてあげて。室外機さん、暖房に切り替えるわね。ごめんね、強く生きてね」
うわ、水漏れ。これってエアコンの涙? いや、迷惑なんだけど。
あー、きょうも疲れました。
ゴロンと横になったとたん「ちょっと!」と声がした。
「テレビさん、どうしました?」
「寝るなら消してよ」
「いえ、見てます」
「うそ、今、目をつぶってたわよ」
「見てるってば」(昭和のお父さんか)
小学生、浦島太郎 [名作パロディー]
はじめまして。浦島太郎です。
今日からこのクラスに編入しました。
特技は、魚を捕ることです。
よろしくお願いします。
僕は約600年前からタイムスリップしてきました。
海の中にある竜宮城っていうところから戻ったら、時代が大きく変わっていたのです。
親もいなくて、家もなくて、村はすっかり変わっていました。
途方に暮れていましたが、村……いや、この町の人はなぜかみんな僕のことを知っていました。
「浦島太郎さんでしょ」
「カメを助けて竜宮城に行った浦島さんよね」
僕は、意外と有名人でした。
町の人はみんな親切で、いろいろ世話をしてくれました。
600年の間に、この国が大きく変わったことを教えてくれました。
僕が学校へ行っていないことを知って、小学校から学ぶように勧めてくれました。
年齢は皆さんよりずいぶん上ですが、仲良くしてください。
「はい、みんな拍手!」
パチパチパチ
「ところで浦島君、急な編入だったから、君の給食が用意できなかったの。お弁当は持ってきた?」
「はい、組合長の奥さんが作ってくれました」
「それはよかったわ。3年生に混ざっての勉強は大変だけど頑張ってね。教科書とノートの使い方を説明するわね」
「はい、お願いします」
「みんなはちょっと自習しててね」
「はーい」
「なあ、浦島君の弁当って、あれかな?」
「きっとそうだよ。大事そうにふろしきに包んでる」
「きっと豪華な弁当なんだろうな」
「弁当箱大きいし、たぶんおかずもいっぱいだね」
「ローストビーフとか、エビフライとか入ってるかも」
「ちょっと開けて見ちゃおうぜ」
「ちょっと男子たち、やめなさいよ」
「いいじゃん。見るだけ、見るだけ」
「うわ、紐が掛かってる」
「高級なやつだ」
「いい、開けるよ。せーの」
パカ
「はーい、みんな、授業を始めますよ。えっ、なに、この煙。えっ、あの、どちらの老人会の方々ですか? うちの生徒たちはどこに?」
「先生、僕が乙姫様にもらった玉手箱が開いています。絶対開けるなって言われたのにな。あれ、先生、どこに行くんですか?」
「煙を浴びたら大変、私、婚活中なのよ」
乙姫様は、いったい何を下さったのだろう。
そしていきなり現れた老人たちは何?
僕のクラスメートたちは、どこに行ってしまったのかな?
(浦島君、家に帰ってうらしまたろうの物語を読んで下さい。すべて分かります)
今日からこのクラスに編入しました。
特技は、魚を捕ることです。
よろしくお願いします。
僕は約600年前からタイムスリップしてきました。
海の中にある竜宮城っていうところから戻ったら、時代が大きく変わっていたのです。
親もいなくて、家もなくて、村はすっかり変わっていました。
途方に暮れていましたが、村……いや、この町の人はなぜかみんな僕のことを知っていました。
「浦島太郎さんでしょ」
「カメを助けて竜宮城に行った浦島さんよね」
僕は、意外と有名人でした。
町の人はみんな親切で、いろいろ世話をしてくれました。
600年の間に、この国が大きく変わったことを教えてくれました。
僕が学校へ行っていないことを知って、小学校から学ぶように勧めてくれました。
年齢は皆さんよりずいぶん上ですが、仲良くしてください。
「はい、みんな拍手!」
パチパチパチ
「ところで浦島君、急な編入だったから、君の給食が用意できなかったの。お弁当は持ってきた?」
「はい、組合長の奥さんが作ってくれました」
「それはよかったわ。3年生に混ざっての勉強は大変だけど頑張ってね。教科書とノートの使い方を説明するわね」
「はい、お願いします」
「みんなはちょっと自習しててね」
「はーい」
「なあ、浦島君の弁当って、あれかな?」
「きっとそうだよ。大事そうにふろしきに包んでる」
「きっと豪華な弁当なんだろうな」
「弁当箱大きいし、たぶんおかずもいっぱいだね」
「ローストビーフとか、エビフライとか入ってるかも」
「ちょっと開けて見ちゃおうぜ」
「ちょっと男子たち、やめなさいよ」
「いいじゃん。見るだけ、見るだけ」
「うわ、紐が掛かってる」
「高級なやつだ」
「いい、開けるよ。せーの」
パカ
「はーい、みんな、授業を始めますよ。えっ、なに、この煙。えっ、あの、どちらの老人会の方々ですか? うちの生徒たちはどこに?」
「先生、僕が乙姫様にもらった玉手箱が開いています。絶対開けるなって言われたのにな。あれ、先生、どこに行くんですか?」
「煙を浴びたら大変、私、婚活中なのよ」
乙姫様は、いったい何を下さったのだろう。
そしていきなり現れた老人たちは何?
僕のクラスメートたちは、どこに行ってしまったのかな?
(浦島君、家に帰ってうらしまたろうの物語を読んで下さい。すべて分かります)
不快な通勤快速 [コメディー]
電車が揺れるたびに、コーヒーの空き缶が右へ左へゴロゴロ転がった。
今日の電車は、珍しく空いている。
私の右隣に座る女が言った。
「非常識ね。電車の中に空き缶を捨てるなんて。飲み終わって邪魔になったからって、平気でポイするなんて人間のクズよ」
私の左隣に座る男が、それに反論した。
「言い過ぎ。捨てたかどうかわからないよ。足元に置いたら転がっちゃったのかも。何でも悪く取るのは君の悪い癖だ」
「はあ?何いい人ぶってるのよ。このコウモリ男。誰にでもいい顔するから出世できないのよ」
「君みたいに粗探しする女が、陰でお局様なんて呼ばれるんだろうな」
「粗探しなんてしてないわ。私は正義感が強いだけよ」
「あの……」と私は、両隣のふたりの顔を交互に見ながら言った。
「席、代わりましょうか?」
この二人は、同じ車両の同じドアから乗ってきたが、まるで他人みたいに私を挟んで座った。二人連れだと分かっていたら席をずらしたのに。
「いいよ。代わらなくて」と男が言った。
「そうよ。見てわかるでしょ。私たちケンカ中なの」
「そうそう。隣に座ったら思い切り脛を蹴られる。そういう女なんだ」
「失礼ね。脛なんか蹴らないわよ。こっちのつま先が痛くなるわ」
ああ、居づらい。
そのときだ。乗って来た男子高校生が、足元の空き缶を蹴った。
その缶は、斜め前に座る老人の足に見事に当たった。
「ちょっと君、電車の中で缶を蹴るなんて非常識よ。おじいさんに謝りなさいよ」
女が言った。
「俺、サッカー部だから、足元に来たものは何でも蹴っちゃうの。そういう習性なの」
高校生は「めんどくせえ」と言いながら、車両を移ってしまった。
「まあ、なんて子。親の顔が見てみたい」
「あのさ、君も悪いよ」と男が言った。
「何が悪いの?」
「君はさっき、あのご高齢の方をおじいさんと呼んだけど、あの人は君のおじいさんじゃない。それに、もしかしたら老けて見えるだけで、そんなに年寄りじゃないかもしれない。おじいさんは失礼だよ。君だっておばさんって呼ばれたら嫌だろう」
「私はおばさんじゃないわ。でもあの人は誰がどう見てもおじいさんよ。要するにあなたは私が言うことを全部否定したいだけなのよ」
「そうじゃないよ。君はもっともらしく正義をかざすけど、根本に愛がない。自己満足なんだ」
「あら、言ってくれるじゃないの。そもそもあなたは……」
「あっ、降りる駅だ。続きは家でやろう」
「望むところよ。あっ、ビールあったかしら」
「コンビニ寄って行こう。久々にバドワイザーの気分」
「いいね。ビールの好みだけは合うわね、私たち」
二人は寄り添って電車を降りた。しんどかった。嵐が過ぎた気分だ。
そう思ったのもつかの間、今度は斜め前の老人が私の隣に移動して来た。
「ねえ、あんた。あたしゃおじいさんじゃないよ」
「はあ、そうですね」
「あたしゃ、ばあさんだ」
「えっ、あっ、そうですか。でも私、関係ないです。さっきの夫婦とは赤の他人です」
「関係あるよ」
老人は、ふふっと笑った。
「あの空き缶を捨てたのはあんただろう。あたしゃ見てたよ。あんたがシートの下に缶を投げるのをね」
あー、生きた心地がしないとはこのことだ。
確かに捨てた。私が捨てた。まさか見られていたなんて。
「あんた、降りるときに缶を拾って行くんだよ。あたしゃ終点まで行くからね。ずっと見てるよ」
老人はニタっと笑って元の席に戻った。
電車が揺れて、空き缶が私の足元に転がって来た。
飲み終わったときよりずいぶん汚れている。
「おかえり」
私は缶を拾い上げて、電車を降りた。あー、しんどかった。
今日の電車は、珍しく空いている。
私の右隣に座る女が言った。
「非常識ね。電車の中に空き缶を捨てるなんて。飲み終わって邪魔になったからって、平気でポイするなんて人間のクズよ」
私の左隣に座る男が、それに反論した。
「言い過ぎ。捨てたかどうかわからないよ。足元に置いたら転がっちゃったのかも。何でも悪く取るのは君の悪い癖だ」
「はあ?何いい人ぶってるのよ。このコウモリ男。誰にでもいい顔するから出世できないのよ」
「君みたいに粗探しする女が、陰でお局様なんて呼ばれるんだろうな」
「粗探しなんてしてないわ。私は正義感が強いだけよ」
「あの……」と私は、両隣のふたりの顔を交互に見ながら言った。
「席、代わりましょうか?」
この二人は、同じ車両の同じドアから乗ってきたが、まるで他人みたいに私を挟んで座った。二人連れだと分かっていたら席をずらしたのに。
「いいよ。代わらなくて」と男が言った。
「そうよ。見てわかるでしょ。私たちケンカ中なの」
「そうそう。隣に座ったら思い切り脛を蹴られる。そういう女なんだ」
「失礼ね。脛なんか蹴らないわよ。こっちのつま先が痛くなるわ」
ああ、居づらい。
そのときだ。乗って来た男子高校生が、足元の空き缶を蹴った。
その缶は、斜め前に座る老人の足に見事に当たった。
「ちょっと君、電車の中で缶を蹴るなんて非常識よ。おじいさんに謝りなさいよ」
女が言った。
「俺、サッカー部だから、足元に来たものは何でも蹴っちゃうの。そういう習性なの」
高校生は「めんどくせえ」と言いながら、車両を移ってしまった。
「まあ、なんて子。親の顔が見てみたい」
「あのさ、君も悪いよ」と男が言った。
「何が悪いの?」
「君はさっき、あのご高齢の方をおじいさんと呼んだけど、あの人は君のおじいさんじゃない。それに、もしかしたら老けて見えるだけで、そんなに年寄りじゃないかもしれない。おじいさんは失礼だよ。君だっておばさんって呼ばれたら嫌だろう」
「私はおばさんじゃないわ。でもあの人は誰がどう見てもおじいさんよ。要するにあなたは私が言うことを全部否定したいだけなのよ」
「そうじゃないよ。君はもっともらしく正義をかざすけど、根本に愛がない。自己満足なんだ」
「あら、言ってくれるじゃないの。そもそもあなたは……」
「あっ、降りる駅だ。続きは家でやろう」
「望むところよ。あっ、ビールあったかしら」
「コンビニ寄って行こう。久々にバドワイザーの気分」
「いいね。ビールの好みだけは合うわね、私たち」
二人は寄り添って電車を降りた。しんどかった。嵐が過ぎた気分だ。
そう思ったのもつかの間、今度は斜め前の老人が私の隣に移動して来た。
「ねえ、あんた。あたしゃおじいさんじゃないよ」
「はあ、そうですね」
「あたしゃ、ばあさんだ」
「えっ、あっ、そうですか。でも私、関係ないです。さっきの夫婦とは赤の他人です」
「関係あるよ」
老人は、ふふっと笑った。
「あの空き缶を捨てたのはあんただろう。あたしゃ見てたよ。あんたがシートの下に缶を投げるのをね」
あー、生きた心地がしないとはこのことだ。
確かに捨てた。私が捨てた。まさか見られていたなんて。
「あんた、降りるときに缶を拾って行くんだよ。あたしゃ終点まで行くからね。ずっと見てるよ」
老人はニタっと笑って元の席に戻った。
電車が揺れて、空き缶が私の足元に転がって来た。
飲み終わったときよりずいぶん汚れている。
「おかえり」
私は缶を拾い上げて、電車を降りた。あー、しんどかった。
前の10件 | -



