ソラシド [公募]
日曜日の昼下がり、君がピアノを弾いている。
その横で、五歳の春香が歌を歌っている。
僕たちの可愛い娘は、少し舌足らずのあどけない声で歌う。
「ドはドーナッツのド、レはレモンのレ」
ドレミの歌だ。まるでサウンドオブミュージックみたいだ。
そういえば君の笑顔は、あの女優に少し似ている。
幸せとは、きっとこういうひと時のことをいうのだろう。
君がプロポーズを受けてくれたときが人生の最高潮だと思っていたのに、それ以上の幸せがたくさんあることを、娘の春香が教えてくれた。
「ソ」のところで、春香が急に歌をやめた。
「ねえママ、ソだけが他と違うのはなぜ?」
「えっ?」
君は怪訝な顔で春香を見た。
「ドはドーナッツ、レはレモン、ミはみんな、ファはファイト、全部音符と同じ文字から始まるのに、ソだけが違うよ」
春香は、「ソはあおいそら~」と歌った。
「ねっ、ソだけが違う言葉で始まるよ。どうしてかなあ。あとね、空は青いだけじゃないよ。赤いときも黒いときも灰色のときもあるよ。ねえ、おかしいよね」
春香は、何にでも疑問を持つ子どもだ。「なぜ? どうして?」が実に多い。
僕はそういうところが素晴らしいと思っている。とても賢い子どもだ。
君はいつも答えに迷う。さて、今日はどんなふうに応えるのだろう。
「ねえ、ねえ」とまとわりつく春香と君を、僕はニヤニヤしながら見ていた。
君は突然、両手で鍵盤を思い切り叩いた。静かな部屋に、不協和音が鳴り響いた。
「知らないわよ。どうでもいいじゃない、そんなこと!」
一瞬の静けさの後、春香が大声で泣き出した。
君はピアノを離れてソファーに座り、苛立ちとモヤモヤを抑えきれずに震えた。
僕は春香の髪を撫で、「大丈夫だよ」と言った。
「ママは少し疲れているんだよ」と。
春香は泣き止まない。重い空気が部屋中のカーテンを暗い色に染めていく。
「春香のことは僕にまかせて」
僕の声を振り払うように、君は頭を抱えた。
頷くこともなく、こめかみを抑えて耳をふさいだ。
春香の泣き声だけが四角い部屋を支配していた。
やがて日が暮れて、赤い夕焼けがレースのカーテンをミカンみたいな暖色に染めた。
「見て、ママ、お空が赤いよ」
ようやく泣き止んだ春香が、君の腕をそっとつかんだ。
本当に、きれいな夕焼けだ。泣きたくなるような、きれいな夕焼けだ。
君はようやく立ち上がり、春香の小さな手を握った。
「本当にきれいな赤い空。目に染みるわ」
「目にしみる? 何がしみるの? 痛い?」
あどけない顔で見上げる春香に、君の心が丸く溶ける。
「どこも痛くないわ。悲しいだけよ」
「きれいなのに、悲しいの?」
「きれいだから、悲しいの」
君はしゃがんで、春香と目線を合わせた。そして優しく抱き寄せた。
「それでいいよ」
僕は後ろから、そっとふたりを見守った。もう見守ることしか出来ないからね。
「パパにも見せてあげようよ」
春香が祭壇から、僕の写真を持って来た。
三人で遊園地に行ったときに撮ったものを、切り抜いて引き延ばした写真だ。
僕は笑っている。その横で、君と春香も笑っていた。
楽しかった思い出から、僕だけが切り取られてしまった。
「ほらママ、三人で見てるよ。赤いきれいなお空を、ママとパパと春香の三人で見てるよ」
「そうだね」
君が、やっと笑った。
もう大丈夫だね。僕は空へ帰るよ。
ふたたび、美しいピアノの音が聞こえた。
春香が歌う。舌足らずのあどけない声で、可愛く歌う。
「シはしあわせよ」
幸せか……。誰にも聞こえない声でつぶやいた。
君と春香の幸せを、僕はずっと祈っている。永遠に、空の上から。

公募ガイド「TO-BE小説工房」で佳作をいただいた作品です。
課題は「空」でした。
今回は次点だったので、選評もいただきました。
最優秀の話も、この話も、悲しいですね。空って、悲しいのかな。

にほんブログ村
その横で、五歳の春香が歌を歌っている。
僕たちの可愛い娘は、少し舌足らずのあどけない声で歌う。
「ドはドーナッツのド、レはレモンのレ」
ドレミの歌だ。まるでサウンドオブミュージックみたいだ。
そういえば君の笑顔は、あの女優に少し似ている。
幸せとは、きっとこういうひと時のことをいうのだろう。
君がプロポーズを受けてくれたときが人生の最高潮だと思っていたのに、それ以上の幸せがたくさんあることを、娘の春香が教えてくれた。
「ソ」のところで、春香が急に歌をやめた。
「ねえママ、ソだけが他と違うのはなぜ?」
「えっ?」
君は怪訝な顔で春香を見た。
「ドはドーナッツ、レはレモン、ミはみんな、ファはファイト、全部音符と同じ文字から始まるのに、ソだけが違うよ」
春香は、「ソはあおいそら~」と歌った。
「ねっ、ソだけが違う言葉で始まるよ。どうしてかなあ。あとね、空は青いだけじゃないよ。赤いときも黒いときも灰色のときもあるよ。ねえ、おかしいよね」
春香は、何にでも疑問を持つ子どもだ。「なぜ? どうして?」が実に多い。
僕はそういうところが素晴らしいと思っている。とても賢い子どもだ。
君はいつも答えに迷う。さて、今日はどんなふうに応えるのだろう。
「ねえ、ねえ」とまとわりつく春香と君を、僕はニヤニヤしながら見ていた。
君は突然、両手で鍵盤を思い切り叩いた。静かな部屋に、不協和音が鳴り響いた。
「知らないわよ。どうでもいいじゃない、そんなこと!」
一瞬の静けさの後、春香が大声で泣き出した。
君はピアノを離れてソファーに座り、苛立ちとモヤモヤを抑えきれずに震えた。
僕は春香の髪を撫で、「大丈夫だよ」と言った。
「ママは少し疲れているんだよ」と。
春香は泣き止まない。重い空気が部屋中のカーテンを暗い色に染めていく。
「春香のことは僕にまかせて」
僕の声を振り払うように、君は頭を抱えた。
頷くこともなく、こめかみを抑えて耳をふさいだ。
春香の泣き声だけが四角い部屋を支配していた。
やがて日が暮れて、赤い夕焼けがレースのカーテンをミカンみたいな暖色に染めた。
「見て、ママ、お空が赤いよ」
ようやく泣き止んだ春香が、君の腕をそっとつかんだ。
本当に、きれいな夕焼けだ。泣きたくなるような、きれいな夕焼けだ。
君はようやく立ち上がり、春香の小さな手を握った。
「本当にきれいな赤い空。目に染みるわ」
「目にしみる? 何がしみるの? 痛い?」
あどけない顔で見上げる春香に、君の心が丸く溶ける。
「どこも痛くないわ。悲しいだけよ」
「きれいなのに、悲しいの?」
「きれいだから、悲しいの」
君はしゃがんで、春香と目線を合わせた。そして優しく抱き寄せた。
「それでいいよ」
僕は後ろから、そっとふたりを見守った。もう見守ることしか出来ないからね。
「パパにも見せてあげようよ」
春香が祭壇から、僕の写真を持って来た。
三人で遊園地に行ったときに撮ったものを、切り抜いて引き延ばした写真だ。
僕は笑っている。その横で、君と春香も笑っていた。
楽しかった思い出から、僕だけが切り取られてしまった。
「ほらママ、三人で見てるよ。赤いきれいなお空を、ママとパパと春香の三人で見てるよ」
「そうだね」
君が、やっと笑った。
もう大丈夫だね。僕は空へ帰るよ。
ふたたび、美しいピアノの音が聞こえた。
春香が歌う。舌足らずのあどけない声で、可愛く歌う。
「シはしあわせよ」
幸せか……。誰にも聞こえない声でつぶやいた。
君と春香の幸せを、僕はずっと祈っている。永遠に、空の上から。
公募ガイド「TO-BE小説工房」で佳作をいただいた作品です。
課題は「空」でした。
今回は次点だったので、選評もいただきました。
最優秀の話も、この話も、悲しいですね。空って、悲しいのかな。
にほんブログ村
置手紙 [公募]
置手紙をテーブルの上に置いた。書いているうちに泣きそうになった。
明日の朝、家を出て行く。家族が寝ている間にこっそり出て行く。
お父さん、高校まで出してくれてありがとう。
お母さん、いつもおいしいご飯をありがとう。
弟の祐介、お兄ちゃんはもう帰らないかもしれない。お父さんとお母さんを頼んだぞ。
最低限の荷物をカバンに詰めて、始発に乗るため夜明け前に家を出た。
大学受験に失敗したことを、僕はチャンスだと思った。
やっぱり僕にはダンスしかない。東京に行って、プロのダンサーになる。
去年上京したダンス仲間のサトシ先輩が、事務所に紹介してくれるという。
「東京はすげーぞ。いろんなところにチャンスが転がってる」
と興奮して言った。だから僕は自分を信じて賭けてみようと思う。
まだ薄暗い庭に、李の花が白く浮かんで見えた。満開だ。
春の花と言えば、わが家では桜ではなく李だった。
この花が、毎年僕たちに笑顔をくれた。泣かないと決めたのに、涙が出た。
でも、もう振り返らない。一張羅の革ジャンの襟を立て、駅まで一気に走った。
東京に着いたのは午前八時半で、通勤時間と重なって信じられないほどの人がいる。
サトシ先輩の住む駅まで、身動きできない超満員電車に揺られ、吐き出されるように降りた。
一息ついて、サトシ先輩に電話をかけた。
「おう、啓介。受験ダメだったって? 風のうわさで聞いた。えっ? こっちに来てる? マジか。じゃあ駅まで迎えに行く。午後からバイトだけど、カフェで茶でも飲もうぜ」
すっかり垢抜けていると思ったサトシ先輩は、あまり変わっていなかった。
先輩が住む町も静かで、駅前に小さな商店街があって、僕の町と大して変わらない。
「なに、その荷物」
先輩が、僕のボストンバッグを指さした。
「家出してきたんだ。俺、ダンサーを目指すことにした。サトシさん、前に言ってたでしょ。事務所に紹介してくれるって」
「ええ~、マジで? いやいやおまえ、親御さんが心配するだろう。今すぐ帰れ」
「なに先生みたいなこと言ってるの。俺は本気だよ。家族には、置手紙を残してきた」
「あのね、啓介君。プロのダンサーなんて、そんなに甘い世界じゃないよ」
「だってサトシさんは成功したんだろう? ステージで踊ったんだろう? 新聞の切り抜き、見せてくれたじゃないか」
「あれは、祭のイベントで、たまたま踊っただけ。そんでたまたま写真撮られて新聞に載っただけ。俺、もうダンスやってねーから」
「だって、事務所は?」
「やめたよ。みんな半端なく上手いやつばかりだ。啓介、やめとけ。おまえ程度じゃプロにはなれない。俺が保証する」
「保証するなよ」
泣きそうだった。
僕たちの中で一番上手かったサトシ先輩が通用しない世界に、飛び込む勇気はない。
結局コーヒー二杯とカルボナーラを奢ってもらって店を出た。
「ちゃんと大学行けよ。おまえは俺より頭がいいんだから」
「うん。先輩も東京で頑張って」
「あのさ、さっきから東京って言ってるけど、ここ、埼玉だから」
先輩は、笑いながら見送ってくれた。なんだ。ここは埼玉か。
やけに空いている電車の中で、一人で笑った。
家に着いたのは夕方だった。真っ赤な夕焼けが町を包んでいた。
一泊ぐらいしようと思ったけれど、結局帰ってきた。
置手紙までしたのに、東京、いや、埼玉でお茶しただけだ。
夜明け前は白く浮かび上がっていた李の花が、オレンジ色に染まっている。
「おかえり」と微笑んでいるように見える。
家の中から笑い声が聞こえた。やけに楽しそうだ。
家出した僕が、心配じゃないのか。
カラスの声に背中を押され、気まずさを纏って家に入った。
「あっ、おかえり兄ちゃん。早かったね」
「あら、二年くらい帰らないかと思ったわ」
「頭、丸めてないんだな」
家族が笑いを堪えるように言う。
テーブルの上には、僕の置手紙がある。所々赤ペンで直してある。
「啓介、誤字脱字、多すぎよ」
「僕の漢字ドリル貸そうか?」
「修行が足りんな」
家族の含み笑いが気になる。モヤモヤしながら手紙を読み返した。
『お父さん、お母さん、僕は出家します』
あっ、「家出」を「出家」と書いている。そういうことか。
だからって、笑うことないじゃないか。僕は本気だったのに。
「夕飯は、精進料理にする?」と、お母さんがまた笑った。
ひどいよ。
李の花だけが、僕を慰めて優しく揺れた。
*******
公募ガイド「TO-BE小説工房」で佳作をいただきました。
久しぶりの佳作。課題は「李」難しいですよね。
あまり身近じゃないし。
最優秀作品は、いい話でした。私には書けないな。。。

にほんブログ村
明日の朝、家を出て行く。家族が寝ている間にこっそり出て行く。
お父さん、高校まで出してくれてありがとう。
お母さん、いつもおいしいご飯をありがとう。
弟の祐介、お兄ちゃんはもう帰らないかもしれない。お父さんとお母さんを頼んだぞ。
最低限の荷物をカバンに詰めて、始発に乗るため夜明け前に家を出た。
大学受験に失敗したことを、僕はチャンスだと思った。
やっぱり僕にはダンスしかない。東京に行って、プロのダンサーになる。
去年上京したダンス仲間のサトシ先輩が、事務所に紹介してくれるという。
「東京はすげーぞ。いろんなところにチャンスが転がってる」
と興奮して言った。だから僕は自分を信じて賭けてみようと思う。
まだ薄暗い庭に、李の花が白く浮かんで見えた。満開だ。
春の花と言えば、わが家では桜ではなく李だった。
この花が、毎年僕たちに笑顔をくれた。泣かないと決めたのに、涙が出た。
でも、もう振り返らない。一張羅の革ジャンの襟を立て、駅まで一気に走った。
東京に着いたのは午前八時半で、通勤時間と重なって信じられないほどの人がいる。
サトシ先輩の住む駅まで、身動きできない超満員電車に揺られ、吐き出されるように降りた。
一息ついて、サトシ先輩に電話をかけた。
「おう、啓介。受験ダメだったって? 風のうわさで聞いた。えっ? こっちに来てる? マジか。じゃあ駅まで迎えに行く。午後からバイトだけど、カフェで茶でも飲もうぜ」
すっかり垢抜けていると思ったサトシ先輩は、あまり変わっていなかった。
先輩が住む町も静かで、駅前に小さな商店街があって、僕の町と大して変わらない。
「なに、その荷物」
先輩が、僕のボストンバッグを指さした。
「家出してきたんだ。俺、ダンサーを目指すことにした。サトシさん、前に言ってたでしょ。事務所に紹介してくれるって」
「ええ~、マジで? いやいやおまえ、親御さんが心配するだろう。今すぐ帰れ」
「なに先生みたいなこと言ってるの。俺は本気だよ。家族には、置手紙を残してきた」
「あのね、啓介君。プロのダンサーなんて、そんなに甘い世界じゃないよ」
「だってサトシさんは成功したんだろう? ステージで踊ったんだろう? 新聞の切り抜き、見せてくれたじゃないか」
「あれは、祭のイベントで、たまたま踊っただけ。そんでたまたま写真撮られて新聞に載っただけ。俺、もうダンスやってねーから」
「だって、事務所は?」
「やめたよ。みんな半端なく上手いやつばかりだ。啓介、やめとけ。おまえ程度じゃプロにはなれない。俺が保証する」
「保証するなよ」
泣きそうだった。
僕たちの中で一番上手かったサトシ先輩が通用しない世界に、飛び込む勇気はない。
結局コーヒー二杯とカルボナーラを奢ってもらって店を出た。
「ちゃんと大学行けよ。おまえは俺より頭がいいんだから」
「うん。先輩も東京で頑張って」
「あのさ、さっきから東京って言ってるけど、ここ、埼玉だから」
先輩は、笑いながら見送ってくれた。なんだ。ここは埼玉か。
やけに空いている電車の中で、一人で笑った。
家に着いたのは夕方だった。真っ赤な夕焼けが町を包んでいた。
一泊ぐらいしようと思ったけれど、結局帰ってきた。
置手紙までしたのに、東京、いや、埼玉でお茶しただけだ。
夜明け前は白く浮かび上がっていた李の花が、オレンジ色に染まっている。
「おかえり」と微笑んでいるように見える。
家の中から笑い声が聞こえた。やけに楽しそうだ。
家出した僕が、心配じゃないのか。
カラスの声に背中を押され、気まずさを纏って家に入った。
「あっ、おかえり兄ちゃん。早かったね」
「あら、二年くらい帰らないかと思ったわ」
「頭、丸めてないんだな」
家族が笑いを堪えるように言う。
テーブルの上には、僕の置手紙がある。所々赤ペンで直してある。
「啓介、誤字脱字、多すぎよ」
「僕の漢字ドリル貸そうか?」
「修行が足りんな」
家族の含み笑いが気になる。モヤモヤしながら手紙を読み返した。
『お父さん、お母さん、僕は出家します』
あっ、「家出」を「出家」と書いている。そういうことか。
だからって、笑うことないじゃないか。僕は本気だったのに。
「夕飯は、精進料理にする?」と、お母さんがまた笑った。
ひどいよ。
李の花だけが、僕を慰めて優しく揺れた。
*******
公募ガイド「TO-BE小説工房」で佳作をいただきました。
久しぶりの佳作。課題は「李」難しいですよね。
あまり身近じゃないし。
最優秀作品は、いい話でした。私には書けないな。。。
にほんブログ村
いつか、ママのように [公募]
鏡はうそつきだ。鏡にうつるわたしは、本当のわたしじゃない。
だって、パパもママもおばさんたちも、みんなわたしを「かわいい」というけれど、鏡にうつるわたしは、ちっともかわいくない。
鏡の中の世界は、うそばっかりだ。
私がそんなふうに思っていたのは幼稚園までで、小学校に入学すると、さすがに現実を思い知る。
私は決して、可愛い方ではなかった。
「かわいい」は、子ども全般に当てはまる言葉であり、それは顔ではなく仕草や言動に対するものだと知る。
ママは美人で、パパはハンサム。
美男美女のふたりから生まれたのに、なぜか私は全然似ていない。
腫れぼったい一重の目も、横に広がった丸い鼻も、何ひとつ似ていない。
「ママは美人なのにね」と陰で言う女子たちや、「おまえ、母ちゃんに全然似てねえな」と直接言ってくる無神経な男子たちに傷つき、その度私は鏡を見ながら泣きそうになる。
そして私は疑い始めた。もしかしたら、私はパパとママの本当の子どもではないのではないか。
どこかからもらわれたか、拾われて育ててもらっているのではないか。
「ママ、私は本当にパパとママの子どもなの?」
ついにママに尋ねたのは、小学三年生のときだった。ママは笑いながら言った。
「あなたは正真正銘、パパとママの子どもだよ。足の指を見てごらん。ママとそっくりでしょう」
言われた通り、わたしの足の指は、細くて長くて、ママの足の指とそっくりだった。
「凛々しい眉毛は、パパにそっくりね」
太い眉毛は似たくはなかったけれど、確かにそっくりだ。とりあえずはホッとした。
「ねえママ、それじゃあ、私も大人になったらママみたいな美人になれる?」
「もちろん、なれるわよ」
ママは、わたしの髪を撫でながら言った。
「だけどね、そのためには内面を磨かないとね。たくさん勉強して、いろんなことを学ぶの。人には優しく、他人を羨まない、そして無駄遣いをしないこと」
ママはそう言ってウインクをした。
それはきっと、大人が子供を躾けるための魔法みたいな言葉だ。
だけど私は信じた。ママのような美人になりたかったから。
それから私は、一生懸命勉強をした。たくさんの知識を身に着けて、成績はいつも一番だった。
友達にも優しくした。人が嫌がることも進んでやった。
おかげで私の容姿をバカにする子はいなくなって、学級委員や生徒会役員に、いつも推薦された。
言いつけを守って無駄遣いもしなかった。
正直、それが美人になることと関係あるのか疑問だったけれど、お年玉は全部貯金した。
高校は、地元一の進学校に進み、一流の大学に入り、そしてこの春、誰もが羨む一流企業に就職をした。
ママの言いつけを守りながら、私は毎朝毎朝、鏡を見た。
「今日はきれいになっているかな? 突然目が二重になっていないかな? 鼻がすらりと細くなっていないかな?」と。
だけど鏡に映っているのは、いつものさえない私だった。
どんなに内面を磨いたって、ちっとも変わらない。
メイクをするようになって少しはマシになったけれど、ママのような美人には程遠い。
研修を終えて希望の部署に配属された。
新入社員の中では仕事が出来る方だけど、課長のお気に入りは可愛い女子社員だ。
男性社員の接し方にも差があるような気がする。
仕事を頼むときの態度が、あの子と私とでは微妙に違う。
人を羨んではいけないと言い聞かせても、ため息ばかりの毎日だ。
入社して初めて行われた同期の飲み会に、私は誘われなかった。
誘われたのは可愛い女の子ばかりで、私は当然のようにその中には入れない。
胸の中の何かが爆発したように、私はママに泣きついた。
「ママの嘘つき。言いつけを守っても、ちっとも美人にならないわ」
ママは、子どもの頃のように私の髪を優しく撫でた。
「言いつけを守ったから、いい会社に入れたでしょう? お給料もいいしボーナスもちゃんと出る。貯金もすぐに貯まるわ」
「お金ばかり貯まってもしょうがないよ」
「あなたの貯金が百万円になったら、いいお医者さまを紹介してあげるわ」
「お医者さま?」
「いい、一度にやっちゃだめよ。少しずつ、少しずつ直していくの」
「……ママ?」
完璧に整った顔で、ママが微笑んだ。
一瞬ママの顔が、百万円に見えた。
++++++++++
公募ガイド「TO-BE小説工房」の落選作です。
課題は「鏡」でした。
現実離れした話が多かったようです。
そういえば、前回お知らせした百物語の本に、阿刀田先生のお話も入っています。

にほんブログ村
だって、パパもママもおばさんたちも、みんなわたしを「かわいい」というけれど、鏡にうつるわたしは、ちっともかわいくない。
鏡の中の世界は、うそばっかりだ。
私がそんなふうに思っていたのは幼稚園までで、小学校に入学すると、さすがに現実を思い知る。
私は決して、可愛い方ではなかった。
「かわいい」は、子ども全般に当てはまる言葉であり、それは顔ではなく仕草や言動に対するものだと知る。
ママは美人で、パパはハンサム。
美男美女のふたりから生まれたのに、なぜか私は全然似ていない。
腫れぼったい一重の目も、横に広がった丸い鼻も、何ひとつ似ていない。
「ママは美人なのにね」と陰で言う女子たちや、「おまえ、母ちゃんに全然似てねえな」と直接言ってくる無神経な男子たちに傷つき、その度私は鏡を見ながら泣きそうになる。
そして私は疑い始めた。もしかしたら、私はパパとママの本当の子どもではないのではないか。
どこかからもらわれたか、拾われて育ててもらっているのではないか。
「ママ、私は本当にパパとママの子どもなの?」
ついにママに尋ねたのは、小学三年生のときだった。ママは笑いながら言った。
「あなたは正真正銘、パパとママの子どもだよ。足の指を見てごらん。ママとそっくりでしょう」
言われた通り、わたしの足の指は、細くて長くて、ママの足の指とそっくりだった。
「凛々しい眉毛は、パパにそっくりね」
太い眉毛は似たくはなかったけれど、確かにそっくりだ。とりあえずはホッとした。
「ねえママ、それじゃあ、私も大人になったらママみたいな美人になれる?」
「もちろん、なれるわよ」
ママは、わたしの髪を撫でながら言った。
「だけどね、そのためには内面を磨かないとね。たくさん勉強して、いろんなことを学ぶの。人には優しく、他人を羨まない、そして無駄遣いをしないこと」
ママはそう言ってウインクをした。
それはきっと、大人が子供を躾けるための魔法みたいな言葉だ。
だけど私は信じた。ママのような美人になりたかったから。
それから私は、一生懸命勉強をした。たくさんの知識を身に着けて、成績はいつも一番だった。
友達にも優しくした。人が嫌がることも進んでやった。
おかげで私の容姿をバカにする子はいなくなって、学級委員や生徒会役員に、いつも推薦された。
言いつけを守って無駄遣いもしなかった。
正直、それが美人になることと関係あるのか疑問だったけれど、お年玉は全部貯金した。
高校は、地元一の進学校に進み、一流の大学に入り、そしてこの春、誰もが羨む一流企業に就職をした。
ママの言いつけを守りながら、私は毎朝毎朝、鏡を見た。
「今日はきれいになっているかな? 突然目が二重になっていないかな? 鼻がすらりと細くなっていないかな?」と。
だけど鏡に映っているのは、いつものさえない私だった。
どんなに内面を磨いたって、ちっとも変わらない。
メイクをするようになって少しはマシになったけれど、ママのような美人には程遠い。
研修を終えて希望の部署に配属された。
新入社員の中では仕事が出来る方だけど、課長のお気に入りは可愛い女子社員だ。
男性社員の接し方にも差があるような気がする。
仕事を頼むときの態度が、あの子と私とでは微妙に違う。
人を羨んではいけないと言い聞かせても、ため息ばかりの毎日だ。
入社して初めて行われた同期の飲み会に、私は誘われなかった。
誘われたのは可愛い女の子ばかりで、私は当然のようにその中には入れない。
胸の中の何かが爆発したように、私はママに泣きついた。
「ママの嘘つき。言いつけを守っても、ちっとも美人にならないわ」
ママは、子どもの頃のように私の髪を優しく撫でた。
「言いつけを守ったから、いい会社に入れたでしょう? お給料もいいしボーナスもちゃんと出る。貯金もすぐに貯まるわ」
「お金ばかり貯まってもしょうがないよ」
「あなたの貯金が百万円になったら、いいお医者さまを紹介してあげるわ」
「お医者さま?」
「いい、一度にやっちゃだめよ。少しずつ、少しずつ直していくの」
「……ママ?」
完璧に整った顔で、ママが微笑んだ。
一瞬ママの顔が、百万円に見えた。
++++++++++
公募ガイド「TO-BE小説工房」の落選作です。
課題は「鏡」でした。
現実離れした話が多かったようです。
そういえば、前回お知らせした百物語の本に、阿刀田先生のお話も入っています。
にほんブログ村
僕の忠臣蔵 [公募]
「旧暦」というものがあることを知ったのは、じいちゃんと忠臣蔵のドラマを見ていたときだった。
12月14日、雪の中、赤穂浪士が吉良邸に討ち入りに行くクライマックス、そういえば去年も見たなと思いながら、小学生の僕は炬燵でみかんの皮を剥いていた。
「じいちゃん、江戸って東京でしょう。12月にこんな大雪降らないよね」
定番の時代劇にすっかり飽きた僕は、粗探しみたいな突っ込みを入れた。
じいちゃんは笑いながら「旧暦の12月だ」と言った。
「今の暦に直すと一月の後半だ。ちょうど一番寒いころだ。そりゃ雪も降るだろう」
じいちゃんは、壁からカレンダーを外して僕に見せた。
日にちの横に、旧暦の日付が小さく書いてあった。
「へえ」と僕は感心して、どうして旧暦があるのか尋ねたけれど、じいちゃんは面倒になったのか、それとも知らなかったのか、得意の寝たふりを決め込んだ。
ストーブの上の薬缶がシュンシュンと音を立て、父が仕事から戻るころ、じいちゃんは本格的に寝息を立てる。
ほぼ毎日繰り返される、わが家の定番だ。
その翌年の11月、じいちゃんは静かに天国へ旅立った。
母が、7歳の僕を置いて家を出て行ってから、殆どの時間をじいちゃんと過ごした。
ひとりで過ごす12月、忠臣蔵のドラマは、他の番組に変わっていた。
時代劇と懐メロ、かりんとうと昆布茶、こけしと木彫りの熊、だるまストーブで焼くお餅。じいちゃんに繋がる全ての物が、僕の中から消えていくような気がした。
その後僕と父は、じいちゃんの家を売って、父の仕事場から近いマンションで暮らした。
父の帰りはずいぶんと早くなり、僕の暮らしはずいぶん変わった。
少しだけ大人になって、じいちゃんのことを思い出すことも少なくなったけれど、カレンダーで旧暦を見る癖だけは残った。
僕は高校生になり、同じクラスのユリとつきあい始めた。
ユリの誕生日は12月14日。赤穂浪士の討ち入りと同じ日だ。
「損なのよ。誕生日とクリスマスを一緒にされちゃうの。プレゼントも一緒よ。つまらないわ。かと言って、10日で2回もイベントをやってもらうのは気が引けるでしょう」
ユリは口を尖らせた。僕はひらめいた。
「じゃあさ、誕生日は旧暦でやろうよ」
「何それ? どういうこと?」
僕は手帳を取り出した。旧暦が書かれたお気に入りの黒い手帳だ。
「ほら、旧暦の12月14日は、新暦の1月19日だ。この日に君の誕生日を祝おう」
ユリは手帳を眺めながら「ふうん。よくわからないけど、それでいいわ」と言った。
リスマスイブはイルミネーションを見に行った。
初めて手を繋ぎ、女の子の手はなんて柔らかいのだろうと思った。
夜の街を二人で歩いていたら、運悪く同級生の大石に会ってしまった。
しかも大石は、ユリの元カレだ。
「へえ、おまえら、つきあってるんだ」
大石はユリに未練があって、何度か復縁を迫っているらしい。
僕は無視して行こうとしたが、奴が共通の友人の話を始め、ユリもそれに応えたりしたものだから少し頭にきた。
「もう帰ろう」と、二人の間に入った弾みに、肘が大石の顔に当たってしまった。
故意ではないが奴が怒って喧嘩になり、僕が一方的に悪いという流れになり、気まずいイブになってしまった。
冷え切った家は真っ暗で寂しくて、じいちゃんがいてくれたらと、子どもみたいなことを思った。
1月19日(旧暦の12月14日)、僕はユリを家に招いた。
父は帰りが遅いし、僕は高校男子にしてはかなり料理が得意だった。
「ケーキも作ってくれたのね。すごーい。パティシエになれるわ」
彼女は感激して、すべての料理を褒めた。
そして食べて笑って、寄り添ってDVDを見た。
僕がキスのチャンスを狙っていたら、玄関のチャイムが鳴った。
残念ながら父が帰ってきたようだ。
「お父さん、鍵忘れたのかな?」と、ドアを開けると、立っていたのは大石だった。
「ユリを返してもらいに来た」
「はっ? おまえ何言ってんの?」
「俺ら復縁したんだ。正月に一緒に出掛けた」
振り返ると、ユリが気まずそうに俯いた。
「ごめんね。誕生日に、彼がプレゼントをくれたの。欲しかったブランドのお財布。それでね、お礼にデートして、それで、つまり、そういうことに……」
手料理よりブランド、旧暦より新暦。つまりそういうことか。
ユリは何度も謝って、奴に手を引かれて帰った。帰り際、大石に腹を殴られた。
「この前の仕返しだ」と奴は言った。
なあ、じいちゃん、これって打ち入りか?
窓の外には、雪が舞い始めた。いっそ大雪になればいいと、僕は思った。
****
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「暦」でした。
このブログではお馴染みの忠臣蔵ネタでしたが、残念です。
でもまあ、書いてて楽しかったからいいか^^
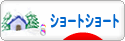
にほんブログ村
12月14日、雪の中、赤穂浪士が吉良邸に討ち入りに行くクライマックス、そういえば去年も見たなと思いながら、小学生の僕は炬燵でみかんの皮を剥いていた。
「じいちゃん、江戸って東京でしょう。12月にこんな大雪降らないよね」
定番の時代劇にすっかり飽きた僕は、粗探しみたいな突っ込みを入れた。
じいちゃんは笑いながら「旧暦の12月だ」と言った。
「今の暦に直すと一月の後半だ。ちょうど一番寒いころだ。そりゃ雪も降るだろう」
じいちゃんは、壁からカレンダーを外して僕に見せた。
日にちの横に、旧暦の日付が小さく書いてあった。
「へえ」と僕は感心して、どうして旧暦があるのか尋ねたけれど、じいちゃんは面倒になったのか、それとも知らなかったのか、得意の寝たふりを決め込んだ。
ストーブの上の薬缶がシュンシュンと音を立て、父が仕事から戻るころ、じいちゃんは本格的に寝息を立てる。
ほぼ毎日繰り返される、わが家の定番だ。
その翌年の11月、じいちゃんは静かに天国へ旅立った。
母が、7歳の僕を置いて家を出て行ってから、殆どの時間をじいちゃんと過ごした。
ひとりで過ごす12月、忠臣蔵のドラマは、他の番組に変わっていた。
時代劇と懐メロ、かりんとうと昆布茶、こけしと木彫りの熊、だるまストーブで焼くお餅。じいちゃんに繋がる全ての物が、僕の中から消えていくような気がした。
その後僕と父は、じいちゃんの家を売って、父の仕事場から近いマンションで暮らした。
父の帰りはずいぶんと早くなり、僕の暮らしはずいぶん変わった。
少しだけ大人になって、じいちゃんのことを思い出すことも少なくなったけれど、カレンダーで旧暦を見る癖だけは残った。
僕は高校生になり、同じクラスのユリとつきあい始めた。
ユリの誕生日は12月14日。赤穂浪士の討ち入りと同じ日だ。
「損なのよ。誕生日とクリスマスを一緒にされちゃうの。プレゼントも一緒よ。つまらないわ。かと言って、10日で2回もイベントをやってもらうのは気が引けるでしょう」
ユリは口を尖らせた。僕はひらめいた。
「じゃあさ、誕生日は旧暦でやろうよ」
「何それ? どういうこと?」
僕は手帳を取り出した。旧暦が書かれたお気に入りの黒い手帳だ。
「ほら、旧暦の12月14日は、新暦の1月19日だ。この日に君の誕生日を祝おう」
ユリは手帳を眺めながら「ふうん。よくわからないけど、それでいいわ」と言った。
リスマスイブはイルミネーションを見に行った。
初めて手を繋ぎ、女の子の手はなんて柔らかいのだろうと思った。
夜の街を二人で歩いていたら、運悪く同級生の大石に会ってしまった。
しかも大石は、ユリの元カレだ。
「へえ、おまえら、つきあってるんだ」
大石はユリに未練があって、何度か復縁を迫っているらしい。
僕は無視して行こうとしたが、奴が共通の友人の話を始め、ユリもそれに応えたりしたものだから少し頭にきた。
「もう帰ろう」と、二人の間に入った弾みに、肘が大石の顔に当たってしまった。
故意ではないが奴が怒って喧嘩になり、僕が一方的に悪いという流れになり、気まずいイブになってしまった。
冷え切った家は真っ暗で寂しくて、じいちゃんがいてくれたらと、子どもみたいなことを思った。
1月19日(旧暦の12月14日)、僕はユリを家に招いた。
父は帰りが遅いし、僕は高校男子にしてはかなり料理が得意だった。
「ケーキも作ってくれたのね。すごーい。パティシエになれるわ」
彼女は感激して、すべての料理を褒めた。
そして食べて笑って、寄り添ってDVDを見た。
僕がキスのチャンスを狙っていたら、玄関のチャイムが鳴った。
残念ながら父が帰ってきたようだ。
「お父さん、鍵忘れたのかな?」と、ドアを開けると、立っていたのは大石だった。
「ユリを返してもらいに来た」
「はっ? おまえ何言ってんの?」
「俺ら復縁したんだ。正月に一緒に出掛けた」
振り返ると、ユリが気まずそうに俯いた。
「ごめんね。誕生日に、彼がプレゼントをくれたの。欲しかったブランドのお財布。それでね、お礼にデートして、それで、つまり、そういうことに……」
手料理よりブランド、旧暦より新暦。つまりそういうことか。
ユリは何度も謝って、奴に手を引かれて帰った。帰り際、大石に腹を殴られた。
「この前の仕返しだ」と奴は言った。
なあ、じいちゃん、これって打ち入りか?
窓の外には、雪が舞い始めた。いっそ大雪になればいいと、僕は思った。
****
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「暦」でした。
このブログではお馴染みの忠臣蔵ネタでしたが、残念です。
でもまあ、書いてて楽しかったからいいか^^
にほんブログ村
ピンときた [公募]
不動産会社に勤める矢野詩織は、逞しい営業力で女性初の営業課長になった。
彼女の武器は高学歴でも、特別なスキルでも、魅力的な容姿でもない。
彼女の武器は、直観力だ。
「ピンときた」が詩織の口癖で、いい物件、いいオーナー、いいクライアントを一瞬で見極める力を持っていた。
詩織がピンときた客は、百パーセントの確率で商談が成立する。
逆にピンとこない客や物件からは、さっと引く。まったく無駄がないのだ。
「矢野さん、駅前で居酒屋をやりたいという知人がいるんだが、何とかならないかね。出来れば居抜きで探してくれないか」
「部長、駅前は無理ですよ。空いているテナントはないし、どの店も繁盛しているから大金を積まれても売りませんよ」
ピンとこない話は、例え部長からの依頼でもきっぱり断る。できる女に忖度はない。
部下を誘って、飲みに行くことも多い。酔うと部下は無礼講になる。
「課長の直観力はホント凄いっす。尊敬するっす。だけど何で独身なんすか? ピンとくる男、いないんすか?」
「君、その発言はセクハラよ」と軽くかわしながらも、詩織は思う。
どうして私の直観力は恋愛には効かないのかしら。
仕事ばかりで気づけば三十代半ば。そろそろピンとくる男が現れてもいいのではないかと。
抜けるような青空が広がる秋晴れの日、詩織はついに、ピンとくる男に出逢った。
詩織はその日、部下の女性社員の結婚披露宴に出席した。
「20代で結婚する」と公言していた彼女は、28歳でIT企業のエリート社員とゴールインした。
詩織は「ご祝儀を出すのは何度めかしら」などと、およそめでたくないことを考えながら、豪華な料理に舌鼓を打っていた。
ふと顔を上げると、隣のテーブルの男と目が合った。
「ピンときた」
男は、特に詩織の好みのタイプではない。
だけど直観力を信じる彼女は、彼をじっくり観察した。食べ方がきれいだ。
清潔感もある。
そして彼が新郎の先輩としてスピーチに立ったとき、この直感は間違いないと確信した。
彼は実に話が上手かった。
淀みなく、笑顔を絶やさず、品のいいユーモアで会場を沸かした。頭のいい人だ。
「後輩に先を越されてしまいました」と言っていたので、独身なのは確実。
年齢は恐らく詩織と変わらない。
彼が席に戻ると、詩織はすかさずビールを注ぎに行った。
素敵なスピーチだったことを告げ、名刺を差し出した。
「へえ、課長さんですか。若いのに凄いな」
男性の9割が言う「女性なのに凄い」という言葉を彼が言わなかったことに、詩織はますます好感を抱いた。
すると彼から、思いがけない誘いがあった。
「この後、ふたりで飲みに行きませんか」
詩織は、少し悩む振りをしながら、心の中でガッツポーズをした。
街は夕暮れ、ふたりは駅前の居酒屋でグラスを合わせた。
古民家を改装したような、なかなかしゃれた店だ。
店選びのセンスもいいと、また好感度がアップした。
「実はここ、母の店なんです。祖父母の家を改装して十年前に居酒屋にしたんです」
カウンターの奥で、老婦人が会釈した。彼の母親だ。
いきなり母親と対面だなんて、結婚も視野に入れているということか。
最低でも三3か月はお付き合いをして、仕事と家庭のバランスも考えないと。
そんな気の早いプロセスを考えていた詩織に彼が言った。
「この店を売りたいんです。出来れば居抜きで。母はもう引退するので、いい不動産屋を探していたんです。矢野さんから名刺をもらったとき、僕、ピンときたんです」
ついさっきまで結婚までのプロセスを考えていた詩織は、たちまち仕事モードになった。
部長の知人が探していた駅前の居酒屋と、条件がぴたりと一致している。
これはいける。
一カ月もしないうちに商談は成立した。
売り手からも買い手からも部長からも感謝され、いい仕事をしたと詩織は思った。
それなのに、晩秋の風がやけに心に染みるのは、ピンときて運命だと思った彼が、アドレスの交換もしないまま海外赴任になってしまったからだ。
結婚どころか、恋愛にすら発展しなかった。
けっきょく詩織の直感は、仕事にしか反応しないということだ。
年が明け、部長の知人が始めた居酒屋で、営業部の新年会が開かれた。
なかなかいい店だ。いい酒を置いている。料理も洒落ている。
何より家庭的な雰囲気が実にいい。
古民家再生プロジェクトに力を入れようかしら。詩織は腕組みをして考える。
「課長、何考えてるんすか。飲みましょうよ」
「ちょっと待って。今ピンときたの」
*****
公募ガイド「TO-BE小説工房」の落選作です。
課題は「ピン」
阿刀田先生も選評で書いていました。色んなピンがあって難しい。(題を決めるのは阿刀田先生ではありません)
本当に何を書いていいのかさっぱりでした。
11月は何かと忙しく、なかなか創作時間がとれません。
ぼちぼち書いていきますね。

にほんブログ村
彼女の武器は高学歴でも、特別なスキルでも、魅力的な容姿でもない。
彼女の武器は、直観力だ。
「ピンときた」が詩織の口癖で、いい物件、いいオーナー、いいクライアントを一瞬で見極める力を持っていた。
詩織がピンときた客は、百パーセントの確率で商談が成立する。
逆にピンとこない客や物件からは、さっと引く。まったく無駄がないのだ。
「矢野さん、駅前で居酒屋をやりたいという知人がいるんだが、何とかならないかね。出来れば居抜きで探してくれないか」
「部長、駅前は無理ですよ。空いているテナントはないし、どの店も繁盛しているから大金を積まれても売りませんよ」
ピンとこない話は、例え部長からの依頼でもきっぱり断る。できる女に忖度はない。
部下を誘って、飲みに行くことも多い。酔うと部下は無礼講になる。
「課長の直観力はホント凄いっす。尊敬するっす。だけど何で独身なんすか? ピンとくる男、いないんすか?」
「君、その発言はセクハラよ」と軽くかわしながらも、詩織は思う。
どうして私の直観力は恋愛には効かないのかしら。
仕事ばかりで気づけば三十代半ば。そろそろピンとくる男が現れてもいいのではないかと。
抜けるような青空が広がる秋晴れの日、詩織はついに、ピンとくる男に出逢った。
詩織はその日、部下の女性社員の結婚披露宴に出席した。
「20代で結婚する」と公言していた彼女は、28歳でIT企業のエリート社員とゴールインした。
詩織は「ご祝儀を出すのは何度めかしら」などと、およそめでたくないことを考えながら、豪華な料理に舌鼓を打っていた。
ふと顔を上げると、隣のテーブルの男と目が合った。
「ピンときた」
男は、特に詩織の好みのタイプではない。
だけど直観力を信じる彼女は、彼をじっくり観察した。食べ方がきれいだ。
清潔感もある。
そして彼が新郎の先輩としてスピーチに立ったとき、この直感は間違いないと確信した。
彼は実に話が上手かった。
淀みなく、笑顔を絶やさず、品のいいユーモアで会場を沸かした。頭のいい人だ。
「後輩に先を越されてしまいました」と言っていたので、独身なのは確実。
年齢は恐らく詩織と変わらない。
彼が席に戻ると、詩織はすかさずビールを注ぎに行った。
素敵なスピーチだったことを告げ、名刺を差し出した。
「へえ、課長さんですか。若いのに凄いな」
男性の9割が言う「女性なのに凄い」という言葉を彼が言わなかったことに、詩織はますます好感を抱いた。
すると彼から、思いがけない誘いがあった。
「この後、ふたりで飲みに行きませんか」
詩織は、少し悩む振りをしながら、心の中でガッツポーズをした。
街は夕暮れ、ふたりは駅前の居酒屋でグラスを合わせた。
古民家を改装したような、なかなかしゃれた店だ。
店選びのセンスもいいと、また好感度がアップした。
「実はここ、母の店なんです。祖父母の家を改装して十年前に居酒屋にしたんです」
カウンターの奥で、老婦人が会釈した。彼の母親だ。
いきなり母親と対面だなんて、結婚も視野に入れているということか。
最低でも三3か月はお付き合いをして、仕事と家庭のバランスも考えないと。
そんな気の早いプロセスを考えていた詩織に彼が言った。
「この店を売りたいんです。出来れば居抜きで。母はもう引退するので、いい不動産屋を探していたんです。矢野さんから名刺をもらったとき、僕、ピンときたんです」
ついさっきまで結婚までのプロセスを考えていた詩織は、たちまち仕事モードになった。
部長の知人が探していた駅前の居酒屋と、条件がぴたりと一致している。
これはいける。
一カ月もしないうちに商談は成立した。
売り手からも買い手からも部長からも感謝され、いい仕事をしたと詩織は思った。
それなのに、晩秋の風がやけに心に染みるのは、ピンときて運命だと思った彼が、アドレスの交換もしないまま海外赴任になってしまったからだ。
結婚どころか、恋愛にすら発展しなかった。
けっきょく詩織の直感は、仕事にしか反応しないということだ。
年が明け、部長の知人が始めた居酒屋で、営業部の新年会が開かれた。
なかなかいい店だ。いい酒を置いている。料理も洒落ている。
何より家庭的な雰囲気が実にいい。
古民家再生プロジェクトに力を入れようかしら。詩織は腕組みをして考える。
「課長、何考えてるんすか。飲みましょうよ」
「ちょっと待って。今ピンときたの」
*****
公募ガイド「TO-BE小説工房」の落選作です。
課題は「ピン」
阿刀田先生も選評で書いていました。色んなピンがあって難しい。(題を決めるのは阿刀田先生ではありません)
本当に何を書いていいのかさっぱりでした。
11月は何かと忙しく、なかなか創作時間がとれません。
ぼちぼち書いていきますね。
にほんブログ村
患者が愛した男 [公募]
あの人に会えると思ったんですよ。
現世では結ばれなかったあの人と、あの世で一緒になりたかった。
だけどあの人は、迎えに来てはくれませんでした。
お花畑が見えたんです。きれいな川が流れていて、あれが恐らく、三途の川だったのでしょう。
向こう岸で手招きしたのは、あの人ではありませんでした。
白い着物を着た女の人でした。
よく見たらその人は、あの人の奥様じゃありませんか。
物凄く怖い顔で、手招きをするのです。
「早く渡っていらっしゃいな。閻魔様とかけ合って地獄に落としてもらうから」
まるで鬼のような形相なのです。私、すっかり怖くなって引き返してしまいました。
それで気がついたらこの病院のベッドの上だったというわけです。
一命をとりとめた患者は、白髪の老婆だが、仕草や話し方がどこか艶めかしい。
若いころはさぞかし美人だっただろう。点滴を替えながら、私は患者に話しかけた。
「あの人って、誰のことですか?」
「私が生涯で、唯一愛した男ですよ。もう三十年も前の話ですけどね」
「奥様がいる方だったんですね」
「そう。今でいう不倫です。でもね、看護師さん、絶対に私の方が愛されていましたよ。ええ、それは間違いないわ」
患者は、自信たっぷりに言い切った。
その患者が運ばれてきたのは、三日前のことだった。
信号待ちの交差点で心臓麻痺を起こして倒れた。
幸い人通りが多く、処置が早かったために一命を取り留めることが出来た。
物腰が柔らかく、丁寧な言葉遣いの患者に好印象を持った。
あの不倫の話を聞くまでは。
私の父は不倫をしていた。母は随分と泣いていたし、そのせいで、ひどく辛い最期を迎えた。
母は死んでも父と不倫相手を許さないだろうし、それは私も同じだ。
あの患者が、昔の不倫を美しい究極の愛だと語るたびに、吐き気が込み上げるほどの嫌悪を感じたが、ベテランナースとして普通に接した。
患者に対しては、分け隔てなく誠心誠意尽くすのが私たちの仕事だ。
患者には、身内はいなかった。誰も見舞いに来ない寂しい女だった。
「ご両親は健在なの?」
朝の血圧を測っているときに、不意に聞かれた。細い腕が微かに動いた。
「母はとっくに亡くなりました。私が十八のときです。父は三年前に、この病院で看取りました」
「ご結婚は?」
「していません。たぶん、もうしません。両親の幸せな姿を見て育たなかったから、結婚に対する夢も希望も持ったことはありません」
「そうね。愛の形って結婚だけじゃないもの。結婚にとらわれることなんてないのよ」
患者は、また三十年前の不倫のことでも思い出したのか、うっとりしたような顔つきになった。
私はさっさと血圧計を片づけて病室を後にした。これ以上話すと、爆発しそうだった。
患者の退院が決まった。
薬や、通院の予定表を持って病室に行くと、夕焼けを見ながら患者が泣いていた。
「死にたかった。どうして私、助かってしまったのでしょう」
「そんなこと言っちゃだめですよ。生きたくても生きられない人だっているんだから」
私の母のように、という言葉は呑み込んだ。
「看護師さん、私を殺してくれませんか。点滴に何かの薬を混ぜれば、きっと誰も気づかない。ねえ看護師さん、あなただって、私を殺したいでしょう?」
患者は拝むように手を合わせ、私のネームプレートに視線を移した。
ああ、やはりそうかと、私は思った。三十年前に父と不倫したあげく、私の母を刺殺した女だ。
ありふれた名前だったから確証はなかったけれど、話すうちに芽生える黒い感情の理由がやっとわかった。
この女はきっと、最初から知っていたのだ。私が、愛した男の娘であることを。
「バカじゃないの。死んでも父のところへなんか行けないわ。あなたは地獄に落ちるのよ。父が母よりあなたを愛していたなんて、本気で思ってる? ただの遊びだった、許してくれって、墓の前で泣いていたわ。私はあなたを殺さない。あなたとは違うもの」
きれいな夕陽を隠すように、カーテンをピシャリと閉めて、私は速足で病室を出た。
もう会うことはないだろう。
彼岸花が、急斜面を赤く染めている。高台の墓には、父と母が仲良く眠っている。
父が本当に愛していたのが誰だったかなんて、そんなことはどうでもいい。
私は手を合わせ、あの女が天国に行かないことだけを祈った。
*****
公募ガイド「TO-BE小説工房」の落選作です。課題は「彼岸」です。
最近は佳作にも選ばれなくなりました。
最優秀作品、面白かった。こういうのを私も書きたかったな。

にほんブログ村
現世では結ばれなかったあの人と、あの世で一緒になりたかった。
だけどあの人は、迎えに来てはくれませんでした。
お花畑が見えたんです。きれいな川が流れていて、あれが恐らく、三途の川だったのでしょう。
向こう岸で手招きしたのは、あの人ではありませんでした。
白い着物を着た女の人でした。
よく見たらその人は、あの人の奥様じゃありませんか。
物凄く怖い顔で、手招きをするのです。
「早く渡っていらっしゃいな。閻魔様とかけ合って地獄に落としてもらうから」
まるで鬼のような形相なのです。私、すっかり怖くなって引き返してしまいました。
それで気がついたらこの病院のベッドの上だったというわけです。
一命をとりとめた患者は、白髪の老婆だが、仕草や話し方がどこか艶めかしい。
若いころはさぞかし美人だっただろう。点滴を替えながら、私は患者に話しかけた。
「あの人って、誰のことですか?」
「私が生涯で、唯一愛した男ですよ。もう三十年も前の話ですけどね」
「奥様がいる方だったんですね」
「そう。今でいう不倫です。でもね、看護師さん、絶対に私の方が愛されていましたよ。ええ、それは間違いないわ」
患者は、自信たっぷりに言い切った。
その患者が運ばれてきたのは、三日前のことだった。
信号待ちの交差点で心臓麻痺を起こして倒れた。
幸い人通りが多く、処置が早かったために一命を取り留めることが出来た。
物腰が柔らかく、丁寧な言葉遣いの患者に好印象を持った。
あの不倫の話を聞くまでは。
私の父は不倫をしていた。母は随分と泣いていたし、そのせいで、ひどく辛い最期を迎えた。
母は死んでも父と不倫相手を許さないだろうし、それは私も同じだ。
あの患者が、昔の不倫を美しい究極の愛だと語るたびに、吐き気が込み上げるほどの嫌悪を感じたが、ベテランナースとして普通に接した。
患者に対しては、分け隔てなく誠心誠意尽くすのが私たちの仕事だ。
患者には、身内はいなかった。誰も見舞いに来ない寂しい女だった。
「ご両親は健在なの?」
朝の血圧を測っているときに、不意に聞かれた。細い腕が微かに動いた。
「母はとっくに亡くなりました。私が十八のときです。父は三年前に、この病院で看取りました」
「ご結婚は?」
「していません。たぶん、もうしません。両親の幸せな姿を見て育たなかったから、結婚に対する夢も希望も持ったことはありません」
「そうね。愛の形って結婚だけじゃないもの。結婚にとらわれることなんてないのよ」
患者は、また三十年前の不倫のことでも思い出したのか、うっとりしたような顔つきになった。
私はさっさと血圧計を片づけて病室を後にした。これ以上話すと、爆発しそうだった。
患者の退院が決まった。
薬や、通院の予定表を持って病室に行くと、夕焼けを見ながら患者が泣いていた。
「死にたかった。どうして私、助かってしまったのでしょう」
「そんなこと言っちゃだめですよ。生きたくても生きられない人だっているんだから」
私の母のように、という言葉は呑み込んだ。
「看護師さん、私を殺してくれませんか。点滴に何かの薬を混ぜれば、きっと誰も気づかない。ねえ看護師さん、あなただって、私を殺したいでしょう?」
患者は拝むように手を合わせ、私のネームプレートに視線を移した。
ああ、やはりそうかと、私は思った。三十年前に父と不倫したあげく、私の母を刺殺した女だ。
ありふれた名前だったから確証はなかったけれど、話すうちに芽生える黒い感情の理由がやっとわかった。
この女はきっと、最初から知っていたのだ。私が、愛した男の娘であることを。
「バカじゃないの。死んでも父のところへなんか行けないわ。あなたは地獄に落ちるのよ。父が母よりあなたを愛していたなんて、本気で思ってる? ただの遊びだった、許してくれって、墓の前で泣いていたわ。私はあなたを殺さない。あなたとは違うもの」
きれいな夕陽を隠すように、カーテンをピシャリと閉めて、私は速足で病室を出た。
もう会うことはないだろう。
彼岸花が、急斜面を赤く染めている。高台の墓には、父と母が仲良く眠っている。
父が本当に愛していたのが誰だったかなんて、そんなことはどうでもいい。
私は手を合わせ、あの女が天国に行かないことだけを祈った。
*****
公募ガイド「TO-BE小説工房」の落選作です。課題は「彼岸」です。
最近は佳作にも選ばれなくなりました。
最優秀作品、面白かった。こういうのを私も書きたかったな。
にほんブログ村
隣のおばさん [公募]
隣の住人が出かけたのを見て、萌はこっそり家を出た。
おばさんから預かった鍵を握りしめ、誰にも見られていないことを確かめながら鍵を開け、隣の家に入った。
おばさんが書いたメモを見ながら奥の部屋に行き、タンスの扉を開けた。
宝石箱には赤や緑の宝石がついた指輪やネックレスがたくさん入っている。
それらを全部袋に入れて、萌は素早く家を出た。
悪いことをしている感覚は全くなかった。
だって萌は、大好きなおばさんに頼まれて、忘れ物を取りに来ただけなのだ。
萌の家のお隣さんは、子供がいない夫婦だった。
萌が生まれてからずっと、家族みたいに可愛がってくれた。
おばさんは優しくて、母に叱られた萌を、いつも庇ってくれた。
萌が九歳になった夏、おばさんが家を出て行った。
両親の話で、隣の夫婦が離婚したことを知った。ショックだった。
しかもおばさんが出て行ったあと、おじさんはすぐに別の女性と暮らし始めた。
ひどく不愛想な女で、「隣のご主人を見損なったわ。奥さんが可哀想よ」と、母が憤慨していた。
夏休みに入り、萌は毎日プールに行った。
お盆が過ぎて、夏休みもあと少しになった帰り道、名前を呼ばれて振り向くと、おばさんが立っていた。
萌が大好きな隣のおばさんだ。
「萌ちゃん、パフェ食べに行かない? 寄り道したら、叱られちゃう?」
「ママはパートで夕方まで帰って来ないよ」
「じゃあ、行こうか」
近くのカフェで、イチゴのパフェを二人で食べた。おばさんは、優しい顔で笑っている。
「萌ちゃん、おじさん、どうしてる?」
「女の人と住んでる。感じの悪い人。萌はあの人好きじゃない。おばさんの方が好き」
「ありがとう、萌ちゃん」
おばさんは、少し泣きそうな顔をした。
「ねえ萌ちゃん、おばさんね、あの家に忘れ物をしちゃったの。取りに行きたいけど、女の人がいたら行けないわね」
「大切なもの?」
「うん。萌ちゃん、取って来てくれる?」
おばさんは、鞄から鍵を出して萌に渡した。
「おじさんに見つからないように、こっそり持ってきてほしいの。ママにも内緒で」
自分の忘れ物も取りに行けないなんて。
萌はおばさんが気の毒で、「わかった」と鍵を受け取った。
うまく持ち出した宝石を渡すと、おばさんは喜んで何度も礼を言った。
萌は、いい事をしたと思っていた。翌日、隣の家に警察が来るまでは。
「宝石を盗まれたらしいわよ」
母の言葉に、萌は凍りついた。盗んだつもりなど、まるでなかった。
おばさんに頼まれたとはいえ、留守に入り込んでどろぼうをしてしまった。
逮捕されて、刑務所に入れられる。萌は本気で怯えた。
夕方には警察が来て、何か物音を聞かなかったかと萌に尋ねた。
萌は、震えながら知らないと答えたが、押しつぶされそうな罪悪感が体中に広がって、泣きながら両親に真実を話した。
すごく叱られると思ったけれど両親は優しく萌を抱きしめて、「よく話してくれたね」と言った。
隣のおじさんは、真実を知って愕然とした。
「驚いたな。あいつ、そこまでするとは」
「だけどおばさんの忘れ物でしょう。だからおばさん、萌に頼んだんだよね」
萌は泣きながら訴えた。
「違うの。あれは私たちの母の物よ」
不愛想な女が言った。女は萌の両親に向かって軽く頭を下げた。
「ご挨拶が遅れましたが、私達兄妹なんです」
「まあ、妹さんだったの」
「母が認知症になりまして、義姉が時おり介護に来てくれていたんです。だけどあの人、母の貯金を自分の口座に移していたんです。認知症の母を騙して銀行に連れて行って、巧く貯金を引き出させていたんです」
おばさんは、そのお金で都心のマンションを借り、贅沢な二重生活をしていた。
おまけに姑の宝石まで現金に換えようとしていたという。
それを知ったおじさんは、おばさんを追い出し、母親を安全な施設に入れた。
そして母の残った財産を、この家で妹と守っていこうと決めたのだ。
不愛想な女が、屈んで萌と視線を合わせた。
「嫌な思いをさせてごめんね。萌ちゃんは何も悪くないから」
萌は、ポロポロ泣いた。女は、萌の頭を優しく撫でた。
おばさんみたいだと萌は思った。
おばさんは、まもなく警察に捕まった。萌に対する謝罪は、とうとうなかった。
萌は思った。九歳の萌にはわからない何かが、優しいおばさんを変えてしまったのだと。
いくらか涼しい風が吹いて、少しだけ大人になった萌の夏が、終わりを告げる。
*****
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「隣人」でした。
最近の課題のは、どうもイメージが湧かなくて。
先月の「商売」は、とうとう出せませんでした。暑かったり仕事が忙しかったりで書けませんでした。
今月は「ピン」? 難しい。。。。

にほんブログ村
おばさんから預かった鍵を握りしめ、誰にも見られていないことを確かめながら鍵を開け、隣の家に入った。
おばさんが書いたメモを見ながら奥の部屋に行き、タンスの扉を開けた。
宝石箱には赤や緑の宝石がついた指輪やネックレスがたくさん入っている。
それらを全部袋に入れて、萌は素早く家を出た。
悪いことをしている感覚は全くなかった。
だって萌は、大好きなおばさんに頼まれて、忘れ物を取りに来ただけなのだ。
萌の家のお隣さんは、子供がいない夫婦だった。
萌が生まれてからずっと、家族みたいに可愛がってくれた。
おばさんは優しくて、母に叱られた萌を、いつも庇ってくれた。
萌が九歳になった夏、おばさんが家を出て行った。
両親の話で、隣の夫婦が離婚したことを知った。ショックだった。
しかもおばさんが出て行ったあと、おじさんはすぐに別の女性と暮らし始めた。
ひどく不愛想な女で、「隣のご主人を見損なったわ。奥さんが可哀想よ」と、母が憤慨していた。
夏休みに入り、萌は毎日プールに行った。
お盆が過ぎて、夏休みもあと少しになった帰り道、名前を呼ばれて振り向くと、おばさんが立っていた。
萌が大好きな隣のおばさんだ。
「萌ちゃん、パフェ食べに行かない? 寄り道したら、叱られちゃう?」
「ママはパートで夕方まで帰って来ないよ」
「じゃあ、行こうか」
近くのカフェで、イチゴのパフェを二人で食べた。おばさんは、優しい顔で笑っている。
「萌ちゃん、おじさん、どうしてる?」
「女の人と住んでる。感じの悪い人。萌はあの人好きじゃない。おばさんの方が好き」
「ありがとう、萌ちゃん」
おばさんは、少し泣きそうな顔をした。
「ねえ萌ちゃん、おばさんね、あの家に忘れ物をしちゃったの。取りに行きたいけど、女の人がいたら行けないわね」
「大切なもの?」
「うん。萌ちゃん、取って来てくれる?」
おばさんは、鞄から鍵を出して萌に渡した。
「おじさんに見つからないように、こっそり持ってきてほしいの。ママにも内緒で」
自分の忘れ物も取りに行けないなんて。
萌はおばさんが気の毒で、「わかった」と鍵を受け取った。
うまく持ち出した宝石を渡すと、おばさんは喜んで何度も礼を言った。
萌は、いい事をしたと思っていた。翌日、隣の家に警察が来るまでは。
「宝石を盗まれたらしいわよ」
母の言葉に、萌は凍りついた。盗んだつもりなど、まるでなかった。
おばさんに頼まれたとはいえ、留守に入り込んでどろぼうをしてしまった。
逮捕されて、刑務所に入れられる。萌は本気で怯えた。
夕方には警察が来て、何か物音を聞かなかったかと萌に尋ねた。
萌は、震えながら知らないと答えたが、押しつぶされそうな罪悪感が体中に広がって、泣きながら両親に真実を話した。
すごく叱られると思ったけれど両親は優しく萌を抱きしめて、「よく話してくれたね」と言った。
隣のおじさんは、真実を知って愕然とした。
「驚いたな。あいつ、そこまでするとは」
「だけどおばさんの忘れ物でしょう。だからおばさん、萌に頼んだんだよね」
萌は泣きながら訴えた。
「違うの。あれは私たちの母の物よ」
不愛想な女が言った。女は萌の両親に向かって軽く頭を下げた。
「ご挨拶が遅れましたが、私達兄妹なんです」
「まあ、妹さんだったの」
「母が認知症になりまして、義姉が時おり介護に来てくれていたんです。だけどあの人、母の貯金を自分の口座に移していたんです。認知症の母を騙して銀行に連れて行って、巧く貯金を引き出させていたんです」
おばさんは、そのお金で都心のマンションを借り、贅沢な二重生活をしていた。
おまけに姑の宝石まで現金に換えようとしていたという。
それを知ったおじさんは、おばさんを追い出し、母親を安全な施設に入れた。
そして母の残った財産を、この家で妹と守っていこうと決めたのだ。
不愛想な女が、屈んで萌と視線を合わせた。
「嫌な思いをさせてごめんね。萌ちゃんは何も悪くないから」
萌は、ポロポロ泣いた。女は、萌の頭を優しく撫でた。
おばさんみたいだと萌は思った。
おばさんは、まもなく警察に捕まった。萌に対する謝罪は、とうとうなかった。
萌は思った。九歳の萌にはわからない何かが、優しいおばさんを変えてしまったのだと。
いくらか涼しい風が吹いて、少しだけ大人になった萌の夏が、終わりを告げる。
*****
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「隣人」でした。
最近の課題のは、どうもイメージが湧かなくて。
先月の「商売」は、とうとう出せませんでした。暑かったり仕事が忙しかったりで書けませんでした。
今月は「ピン」? 難しい。。。。
にほんブログ村
新盆の夜 [公募]
入道雲を従えた緑の山が、いつもよりも大きく見える。
まるで目の前に迫ってくるように見えて、真子は手を伸ばしてみた。
何だか届いてしまいそうな気がして少し怖くなる。
木の幹にしがみついたセミは、命を惜しむように鳴き続けて、猫は日陰を探しながらあくびをしている。
大好きな夏休みだけど、真子は退屈を持て余し、縁側で足をブラブラさせていた。
居間にはたくさんの親戚たちがいて居場所がない。
継ぎ足しの段違いなテーブルには、お寿司や天ぷらや、多くのご馳走が並んでいる。
赤い顔の男たちと、おしゃべりに夢中な女たち。
お母さんは台所と居間を行ったり来たりで忙しそうだし、お父さんはみんなと一緒になってビールを飲んでいる。
襖が外された奥座敷には祭壇が作られ、黒ぶちの写真の前には、たくさんのお菓子や果物が並んでいる。
「どうせ食べられないのにね」と真子はつぶやいた。
お葬式の時はみんな泣いていたのに、今日はずいぶんと賑やかだ。
真子にとって初めての新盆は、何だかとても不思議だった。
真子は、離れのおじいちゃんの部屋に行った。
おじいちゃんはこのところ体調を崩し、食事があまり摂れない。
客に気を遣わせては悪いと、自ら望んで離れの部屋にいた。
「おじいちゃん」
「おお、真子、来てくれたのか」
「おじいちゃん、ひとりで寂しくない?」
「なあに、窓を開ければみんなの賑やかな声が聞こえる。それだけで充分だ」
おじいちゃんは布団から「よっこらしょ」と起き上がった。
真子はおじいちゃんが大好きだ。仕事が忙しい両親に代わって、おじいちゃんがいつも傍にいてくれた。
真子の家は果樹園を営んでいる。夏から秋にかけて大忙しで、真子も毎年収穫を手伝った。
梨、ぶどう、栗。たくさんの人が買いに来る。インターネットでの注文もある。
お父さんはいつも汗まみれで働いていて、お母さんは笑顔で接客をしている。
だけど今年は収穫が少ないせいか、お得意様以外の注文を断っている。
お父さんは天候を恨むように空を見上げて、お母さんの顔からは笑顔が消えた。
だけど今日の新盆には、真子が大好きな果物がたくさん並んでいる。
「ねえ、おじいちゃん、果物なら食べられる?」
「うーん、どうかなあ」
「持ってきてあげようか」
「いや、お客さんに出したものだ。おじいちゃんはいらないよ」
「それなら、祭壇に上がってる果物を持ってきてあげる。どうせ誰も食べないんだもん。おじいちゃん、一緒に食べよう」
おじいちゃんは小さく笑った。
「お母さんに見つかるなよ」
「大丈夫。わたし、つまみ食いの名人だもん」
真子は、おじいちゃんにVサインをして、跳ねるように部屋を出た。
居間では、相変わらず大人たちが騒いでいた。誰も真子に気づかない。
お母さんがチラリとこちらを見たけれど、「奥さん、お醤油ある?」と声をかけられて台所に行った。
真子はその隙に、祭壇から梨とぶどうをひょいとつかんで部屋を出た。
「おじいちゃん、持ってきたよ」
真子が縁側から上がり込むと、弱弱しい風に風鈴が頼りない音を立てた。
「ああ、うまそうだ」
おじいちゃんは、ぶどうをひとつ、口に入れた。皮ごと食べられるマスカット。
お母さんの提案で始めた新しい品種だ。今ではすっかり人気商品になっている。
「甘いなあ」
おじいちゃんは、ゆっくり口を動かしながら、涙を流した。
太陽が傾き始め、客たちがひとり、またひとりと帰っていく。
何人かが離れまで来て、おじいちゃんに挨拶をしていった。
客が帰ると、お父さんとお母さんは奥座敷に並んで座り、祭壇の写真に手を合わせた。
「あれ? 梨とぶどうがなくなっている」
「あら本当だ。きっとあの子が食べたのね」
「真子は食いしん坊だからな」
二人は顔を見合わせて、寂しく笑った。
「違うよ。離れのおじいちゃんに持って行ったんだよ」
背中に向かって言ったけれど、真子の声は届かない。
お父さんとお母さんには、真子の姿も見えない。
「離れのお義父さんを呼んでくるわ。今日はこっちで休んでいただきましょう」
「そうだな。今夜は三人で、真子の話でもしよう。僕たちが大好きだった真子の話を」
「そうね」
真子は少し拗ねて、「三人じゃなくて四人よ」と言ってみたけれど、やっぱり声は届かない。
新盆の夜は、静かに、ゆっくり過ぎていく。
***
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「盆」でした。
去年の夏、初めて家族の新盆を迎え、昼はとても賑やかで、夜はしんみりだったことを思い出して書きました。
ちょっと悲しい話だったな。

にほんブログ村
まるで目の前に迫ってくるように見えて、真子は手を伸ばしてみた。
何だか届いてしまいそうな気がして少し怖くなる。
木の幹にしがみついたセミは、命を惜しむように鳴き続けて、猫は日陰を探しながらあくびをしている。
大好きな夏休みだけど、真子は退屈を持て余し、縁側で足をブラブラさせていた。
居間にはたくさんの親戚たちがいて居場所がない。
継ぎ足しの段違いなテーブルには、お寿司や天ぷらや、多くのご馳走が並んでいる。
赤い顔の男たちと、おしゃべりに夢中な女たち。
お母さんは台所と居間を行ったり来たりで忙しそうだし、お父さんはみんなと一緒になってビールを飲んでいる。
襖が外された奥座敷には祭壇が作られ、黒ぶちの写真の前には、たくさんのお菓子や果物が並んでいる。
「どうせ食べられないのにね」と真子はつぶやいた。
お葬式の時はみんな泣いていたのに、今日はずいぶんと賑やかだ。
真子にとって初めての新盆は、何だかとても不思議だった。
真子は、離れのおじいちゃんの部屋に行った。
おじいちゃんはこのところ体調を崩し、食事があまり摂れない。
客に気を遣わせては悪いと、自ら望んで離れの部屋にいた。
「おじいちゃん」
「おお、真子、来てくれたのか」
「おじいちゃん、ひとりで寂しくない?」
「なあに、窓を開ければみんなの賑やかな声が聞こえる。それだけで充分だ」
おじいちゃんは布団から「よっこらしょ」と起き上がった。
真子はおじいちゃんが大好きだ。仕事が忙しい両親に代わって、おじいちゃんがいつも傍にいてくれた。
真子の家は果樹園を営んでいる。夏から秋にかけて大忙しで、真子も毎年収穫を手伝った。
梨、ぶどう、栗。たくさんの人が買いに来る。インターネットでの注文もある。
お父さんはいつも汗まみれで働いていて、お母さんは笑顔で接客をしている。
だけど今年は収穫が少ないせいか、お得意様以外の注文を断っている。
お父さんは天候を恨むように空を見上げて、お母さんの顔からは笑顔が消えた。
だけど今日の新盆には、真子が大好きな果物がたくさん並んでいる。
「ねえ、おじいちゃん、果物なら食べられる?」
「うーん、どうかなあ」
「持ってきてあげようか」
「いや、お客さんに出したものだ。おじいちゃんはいらないよ」
「それなら、祭壇に上がってる果物を持ってきてあげる。どうせ誰も食べないんだもん。おじいちゃん、一緒に食べよう」
おじいちゃんは小さく笑った。
「お母さんに見つかるなよ」
「大丈夫。わたし、つまみ食いの名人だもん」
真子は、おじいちゃんにVサインをして、跳ねるように部屋を出た。
居間では、相変わらず大人たちが騒いでいた。誰も真子に気づかない。
お母さんがチラリとこちらを見たけれど、「奥さん、お醤油ある?」と声をかけられて台所に行った。
真子はその隙に、祭壇から梨とぶどうをひょいとつかんで部屋を出た。
「おじいちゃん、持ってきたよ」
真子が縁側から上がり込むと、弱弱しい風に風鈴が頼りない音を立てた。
「ああ、うまそうだ」
おじいちゃんは、ぶどうをひとつ、口に入れた。皮ごと食べられるマスカット。
お母さんの提案で始めた新しい品種だ。今ではすっかり人気商品になっている。
「甘いなあ」
おじいちゃんは、ゆっくり口を動かしながら、涙を流した。
太陽が傾き始め、客たちがひとり、またひとりと帰っていく。
何人かが離れまで来て、おじいちゃんに挨拶をしていった。
客が帰ると、お父さんとお母さんは奥座敷に並んで座り、祭壇の写真に手を合わせた。
「あれ? 梨とぶどうがなくなっている」
「あら本当だ。きっとあの子が食べたのね」
「真子は食いしん坊だからな」
二人は顔を見合わせて、寂しく笑った。
「違うよ。離れのおじいちゃんに持って行ったんだよ」
背中に向かって言ったけれど、真子の声は届かない。
お父さんとお母さんには、真子の姿も見えない。
「離れのお義父さんを呼んでくるわ。今日はこっちで休んでいただきましょう」
「そうだな。今夜は三人で、真子の話でもしよう。僕たちが大好きだった真子の話を」
「そうね」
真子は少し拗ねて、「三人じゃなくて四人よ」と言ってみたけれど、やっぱり声は届かない。
新盆の夜は、静かに、ゆっくり過ぎていく。
***
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「盆」でした。
去年の夏、初めて家族の新盆を迎え、昼はとても賑やかで、夜はしんみりだったことを思い出して書きました。
ちょっと悲しい話だったな。
にほんブログ村
ひまわり [公募]
夫の背中に、穴を見つけた。
最初はホクロだと思った。
だけど黒い小さな点は、日を増すごとに少しずつ大きくなっていく。
はっきり穴だと気づいたのは、直径が3ミリほどになったときだ。
くぼんでいる黒い空洞に、シャワーの水滴が吸い込まれて行くのを見たとき、思わず手を止めて覗き込んだ。何も見えず、ただの闇だった。
夫は半年前に事故に遭い、右手を失った。
それから私は、毎晩風呂場で夫の髪と背中を洗っている。生活はがらりと変わった。
夫はやり手の営業マンだったが、片手でも業務をこなせる部署に異動になった。
私はフルタイムの職場を辞めて、融通が利くパートで働き、左手しか使えない夫を支えた。
身体に穴があってもおかしくはない。鼻の穴、耳の穴、みんな意味があって、身体の内部と繋がっている。夫の背中の穴は、何処に繋がっているのだろう。
穴の直径が1センチになった。私は思い切って夫に言った。
「あなたの背中に穴が空いているんだけど」
「えっ? 何それ?」
私は、夫に手鏡を持たせ、合わせ鏡で背中を映した。
「何もないけど。変なこと言わないでよ」
夫が笑いながら手鏡を置いた。こんな大きな穴が、あなたには見えないの?
数日後、私は弟を家に呼んだ。自分の代わりに風呂で夫の髪と背中を洗って欲しいと頼んだ。
弟に、穴を確認してもらうためだ。
「背中に穴なんてなかったよ。……っていうかさ、あるわけないじゃん、穴なんか」
弟が、タオルで手をふきながら、揚げたての唐揚げをつまみ食いした。
「おかしいな。私は確かに見たのよ」
「姉さん、疲れてるんじゃない? だいたいさ、髪や背中、左手だけでも洗えるでしょ。食事だってさ、フォークやスプーンで食べられるものばっかり作ってさ、もっと自立させた方がいいんじゃない?」
弟が、唐揚げをもうひとつつまもうとしたところをピシャリと叩いた。
「あの人はね、新しい部署で慣れない仕事をしているの。家に帰ってきてまで無理してほしくないのよ」
弟は「ふうん」と、納得していない様子でキッチンを離れた。利き手を失くした人の気持ちなど、弟にわかるはずがない。
夫の背中の穴は、5センチに達した。肩甲骨を隠すほどの大きさだ。
中は相変わらず黒い闇で、何も見えない。
いつものように風呂場で背中を洗っていると、ヒューっという風のような音が聞こえた。
それは確かに穴の奥から聞こえる。私はそっと指を入れてみた。
力を入れたわけでもないのに、指がどんどん穴の中に入っていく。
まるで吸い込まれるように、指が、手が、そして私の体が、穴の中に入っていく。
ねっとりとした粘膜のような壁を滑り落ち、たどり着いたのはやはり闇だった。
何も見えないけれど、ここには悲しみが充満している。
ヒューっという音は、風ではなく誰かの泣き声で、呻くような嘆きの声と、やり場のない怒りに叫ぶ声。
「つらい」「せつない」「こんなはずじゃない」「死にたい」
絶望に満ちた世界。ああ、ここは、夫の心の中ではないか。
そう思ったら苦しくなって、私は声を上げてわんわん泣いた。
何もできない。髪と背中を洗うこと、食べやすい食事を作ること、それしかできない。
私は闇の中で泣き続け、いつの間にか眠っていた。
気がついたら、布団の上だった。夫が心配そうに私を見ている。
「私、どうしたの?」
「風呂場で倒れたんだ。ビックリしたよ」
「あなたが布団に運んでくれたの? 左手だけで?」
「うん。結構重かったから引きずった」
夫が笑った。この人は、いつも笑っている。
夫は思い出したように鞄から、紙を出して私に見せた。それは、ひまわりの絵だった。
「パソコンで描いたんだ。あんまり上手くないけど、味があるって評判なんだ」
「へえ、すごい。いい絵だね」
「おれ、社内広報のデザイン担当になったんだ。意外とセンスがいいらしい。給料は減ったけどさ、今の部署、嫌いじゃないよ」
確かに上手くはない。花びらも歪だし、葉っぱの形もちぐはぐだ。
だけど私は、このひまわりが、世界で一番好きだ。
夫の背中の穴は、その日を境になくなった。きっと最初からなかったのだ。
私が落ちたあの闇は、夫の心の中ではない。夫を憐れむ私の心だった。
私が思うよりずっと、夫は強くて明るい人だ。
「髪と背中を洗うの、今日で最後にするね」
まずは、ここから始めよう。夫は「了解」と、ひまわりみたいに笑った。
******
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「穴」でした。割と気に入っていたので、ちょっとがっかり。
SFや奇妙な話が多いと思いましたが、最優秀作は淡々とした日常を切り取ったような話でした。
そうか~そうきたか~(笑)
優しいお話だな~と思いました。
今月の課題は「彼岸」です。この前「お盆」を書いたばかりなので、似たような話にならないように気を付けよう^^

にほんブログ村
最初はホクロだと思った。
だけど黒い小さな点は、日を増すごとに少しずつ大きくなっていく。
はっきり穴だと気づいたのは、直径が3ミリほどになったときだ。
くぼんでいる黒い空洞に、シャワーの水滴が吸い込まれて行くのを見たとき、思わず手を止めて覗き込んだ。何も見えず、ただの闇だった。
夫は半年前に事故に遭い、右手を失った。
それから私は、毎晩風呂場で夫の髪と背中を洗っている。生活はがらりと変わった。
夫はやり手の営業マンだったが、片手でも業務をこなせる部署に異動になった。
私はフルタイムの職場を辞めて、融通が利くパートで働き、左手しか使えない夫を支えた。
身体に穴があってもおかしくはない。鼻の穴、耳の穴、みんな意味があって、身体の内部と繋がっている。夫の背中の穴は、何処に繋がっているのだろう。
穴の直径が1センチになった。私は思い切って夫に言った。
「あなたの背中に穴が空いているんだけど」
「えっ? 何それ?」
私は、夫に手鏡を持たせ、合わせ鏡で背中を映した。
「何もないけど。変なこと言わないでよ」
夫が笑いながら手鏡を置いた。こんな大きな穴が、あなたには見えないの?
数日後、私は弟を家に呼んだ。自分の代わりに風呂で夫の髪と背中を洗って欲しいと頼んだ。
弟に、穴を確認してもらうためだ。
「背中に穴なんてなかったよ。……っていうかさ、あるわけないじゃん、穴なんか」
弟が、タオルで手をふきながら、揚げたての唐揚げをつまみ食いした。
「おかしいな。私は確かに見たのよ」
「姉さん、疲れてるんじゃない? だいたいさ、髪や背中、左手だけでも洗えるでしょ。食事だってさ、フォークやスプーンで食べられるものばっかり作ってさ、もっと自立させた方がいいんじゃない?」
弟が、唐揚げをもうひとつつまもうとしたところをピシャリと叩いた。
「あの人はね、新しい部署で慣れない仕事をしているの。家に帰ってきてまで無理してほしくないのよ」
弟は「ふうん」と、納得していない様子でキッチンを離れた。利き手を失くした人の気持ちなど、弟にわかるはずがない。
夫の背中の穴は、5センチに達した。肩甲骨を隠すほどの大きさだ。
中は相変わらず黒い闇で、何も見えない。
いつものように風呂場で背中を洗っていると、ヒューっという風のような音が聞こえた。
それは確かに穴の奥から聞こえる。私はそっと指を入れてみた。
力を入れたわけでもないのに、指がどんどん穴の中に入っていく。
まるで吸い込まれるように、指が、手が、そして私の体が、穴の中に入っていく。
ねっとりとした粘膜のような壁を滑り落ち、たどり着いたのはやはり闇だった。
何も見えないけれど、ここには悲しみが充満している。
ヒューっという音は、風ではなく誰かの泣き声で、呻くような嘆きの声と、やり場のない怒りに叫ぶ声。
「つらい」「せつない」「こんなはずじゃない」「死にたい」
絶望に満ちた世界。ああ、ここは、夫の心の中ではないか。
そう思ったら苦しくなって、私は声を上げてわんわん泣いた。
何もできない。髪と背中を洗うこと、食べやすい食事を作ること、それしかできない。
私は闇の中で泣き続け、いつの間にか眠っていた。
気がついたら、布団の上だった。夫が心配そうに私を見ている。
「私、どうしたの?」
「風呂場で倒れたんだ。ビックリしたよ」
「あなたが布団に運んでくれたの? 左手だけで?」
「うん。結構重かったから引きずった」
夫が笑った。この人は、いつも笑っている。
夫は思い出したように鞄から、紙を出して私に見せた。それは、ひまわりの絵だった。
「パソコンで描いたんだ。あんまり上手くないけど、味があるって評判なんだ」
「へえ、すごい。いい絵だね」
「おれ、社内広報のデザイン担当になったんだ。意外とセンスがいいらしい。給料は減ったけどさ、今の部署、嫌いじゃないよ」
確かに上手くはない。花びらも歪だし、葉っぱの形もちぐはぐだ。
だけど私は、このひまわりが、世界で一番好きだ。
夫の背中の穴は、その日を境になくなった。きっと最初からなかったのだ。
私が落ちたあの闇は、夫の心の中ではない。夫を憐れむ私の心だった。
私が思うよりずっと、夫は強くて明るい人だ。
「髪と背中を洗うの、今日で最後にするね」
まずは、ここから始めよう。夫は「了解」と、ひまわりみたいに笑った。
******
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「穴」でした。割と気に入っていたので、ちょっとがっかり。
SFや奇妙な話が多いと思いましたが、最優秀作は淡々とした日常を切り取ったような話でした。
そうか~そうきたか~(笑)
優しいお話だな~と思いました。
今月の課題は「彼岸」です。この前「お盆」を書いたばかりなので、似たような話にならないように気を付けよう^^
にほんブログ村
解禁 [公募]
鮎釣りが解禁になり、新しい竿を抱えていそいそ出掛けた夫は、そのまま帰って来なかった。
夫は、慣れたはずの川で命を落とした。
川岸に残されたのは、空っぽのクーラーバッグと、ひとりの見知らぬ女だった。
女は、体中の全ての汁を出し切るような勢いで泣いていた。
「すみません。私のせいで芦田さんが……」
女は泣きながら、慣れない岩場で足を滑らせた女を庇って、夫が川に落ちたと話した。
「家庭を壊すつもりなんてありませんでした。たまにふたりで食事をするだけで幸せでした。だから週末の釣りに誘ってくれたときは嬉しくて……。それがこんなことに……」
ぼんやりした頭で、ぐちゃぐちゃになった女の顔を見ていた。
誰? この人? 冷たくなった夫に尋ねても、答えるはずがない。
夫には愛人がいた。そんな素振りは微塵も見せず、平然と女と釣りに行っていた。
梅雨のねっとりする風の中、骨になった夫を抱く。涙ひとつこぼれてこない。
泣こうとしても、あの女のぐちゃぐちゃの顔が浮かんで泣けなかった。
四十九日が過ぎたころ、安岡が訪ねてきた。夫の昔からの釣り仲間だ。
「芦田君の弔いをかねて、鮎釣りに行って来たよ。あいつが死んだ川で、あいつも分も釣ってやろうと思ってね。そうしたら、これが木の枝に引っかかっていたんだ」
安岡は、黒い携帯電話を差し出した。
夫のものだ。一緒に流されたのだと思っていた。
「誰かが拾って木に掛けたのかもしれない。ストラップに見覚えがあったから、芦田君のものだと気づいたんだ」
防水機能が付いた携帯は、思ったよりも傷がなく、きれいな状態だった。
「持ち帰って、家で充電してみたんだ。そうしたら未送信のメールがあってね。それもあの事故の日に、奥さんに宛てたメールだ。なんだか気になってね。」
女と出掛けた釣りで、どんなメールを送ろうとしていたのだろう。
震える指でボタンを押すと、何とも呑気な言葉が踊っていた。
『今から帰る。大漁だ。今夜は鮎祭りだ』
「芦田君らしいな。笑顔が目に浮かぶよ」
安岡が微笑んだ。拍子抜けするとともに、ふと、ひとつの疑問が沸いた。
「何が大漁よ。クーラーバッグは空だったわ」
「待てよ。変だな。この文面からすると、釣りが終わって帰り支度をしているようだ。じゃあ、あいつはなぜ川に落ちたんだ?」
私は少しためらった後、夫が愛人と釣りに行き、女を庇って川に落ちたことを話した。
安岡は何度も「信じられない」と言った。
「まさか芦田君が女を、しかも初心者を釣りに誘うなんて。いや、ありえないな。釣りはあいつにとってとても神聖なものなんだ」
言われてみればそうだ。長年連れ添った私でさえ、一度も誘われたことがない。
女の話は本当だろうか。
「ちょっと調べてみようか。釣り仲間に、何か事情を知っている奴がいるかもしれない」
安岡はそう言って帰って行った。
モヤモヤしながら季節はすっかり秋になり、鮎釣りの季節も終わりを告げた。
安岡が訪ねてきたのは、秋桜がだらしなく倒れた晩秋のことだ。
「奥さん、芦田君はやはり不倫なんかしてなかったよ。どうやらその女は、芦田君がたまに行くスナックの女だ」
安岡はそう言って写真を見せた。泣き顔しか見ていない女の、厚化粧の顔が写っていた。
「不幸な生い立ちの女で、芦田君は相談に乗ったり、酔って絡んでくる客から、彼女を助けたりしていたらしい。まあつまり、女がそれを愛だと、勝手に勘違いしたんだな」
それから女は、夫の会社を執拗に訪ねたり、帰り道を待ち伏せするようになった
あの釣りの日も、女が夫を尾行したのではないかと安岡は言った。
女が夫を突き落とし、釣った鮎を川に放ったのだとしたら……。
証拠はない。夫はもう骨になってしまった。
安岡が帰った後、夫の写真の前で初めて泣いた。
夏が来て、再び鮎釣りが解禁になった。
今日は夫の命日で、私は、あの川に来ている。
恐らく今日、女が花を手向けに来ると思ったからだ。
待ち伏せて、女が岩場に花束を置いたとき、思い切り背中を押してやる。
あの日から私は、そんなことばかり想像してきた。
やはり女はやってきた。大きな百合の花束を抱えている。
女はそれを岩場に置くと、私が近づくまでもなく、あっという間に川に身を投げた。
女は、夫の後を追ったのだ。
許せない。
夫の後を追って死ぬのが、あの女であってはならない。
私は大声で叫んだ。
「助けて。誰か助けて!」
後追い自殺など、させるものか。
「人が溺れています。誰か助けて!」
山間に響く大声で、私は助けを呼び続けた。
***********
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「鮎」です。難しい課題ですよね。
鮎の塩焼きは美味しいけれど、食べるの専門で釣りなんて行ったことないし。
やはり無理があったかもしれません。

にほんブログ村
夫は、慣れたはずの川で命を落とした。
川岸に残されたのは、空っぽのクーラーバッグと、ひとりの見知らぬ女だった。
女は、体中の全ての汁を出し切るような勢いで泣いていた。
「すみません。私のせいで芦田さんが……」
女は泣きながら、慣れない岩場で足を滑らせた女を庇って、夫が川に落ちたと話した。
「家庭を壊すつもりなんてありませんでした。たまにふたりで食事をするだけで幸せでした。だから週末の釣りに誘ってくれたときは嬉しくて……。それがこんなことに……」
ぼんやりした頭で、ぐちゃぐちゃになった女の顔を見ていた。
誰? この人? 冷たくなった夫に尋ねても、答えるはずがない。
夫には愛人がいた。そんな素振りは微塵も見せず、平然と女と釣りに行っていた。
梅雨のねっとりする風の中、骨になった夫を抱く。涙ひとつこぼれてこない。
泣こうとしても、あの女のぐちゃぐちゃの顔が浮かんで泣けなかった。
四十九日が過ぎたころ、安岡が訪ねてきた。夫の昔からの釣り仲間だ。
「芦田君の弔いをかねて、鮎釣りに行って来たよ。あいつが死んだ川で、あいつも分も釣ってやろうと思ってね。そうしたら、これが木の枝に引っかかっていたんだ」
安岡は、黒い携帯電話を差し出した。
夫のものだ。一緒に流されたのだと思っていた。
「誰かが拾って木に掛けたのかもしれない。ストラップに見覚えがあったから、芦田君のものだと気づいたんだ」
防水機能が付いた携帯は、思ったよりも傷がなく、きれいな状態だった。
「持ち帰って、家で充電してみたんだ。そうしたら未送信のメールがあってね。それもあの事故の日に、奥さんに宛てたメールだ。なんだか気になってね。」
女と出掛けた釣りで、どんなメールを送ろうとしていたのだろう。
震える指でボタンを押すと、何とも呑気な言葉が踊っていた。
『今から帰る。大漁だ。今夜は鮎祭りだ』
「芦田君らしいな。笑顔が目に浮かぶよ」
安岡が微笑んだ。拍子抜けするとともに、ふと、ひとつの疑問が沸いた。
「何が大漁よ。クーラーバッグは空だったわ」
「待てよ。変だな。この文面からすると、釣りが終わって帰り支度をしているようだ。じゃあ、あいつはなぜ川に落ちたんだ?」
私は少しためらった後、夫が愛人と釣りに行き、女を庇って川に落ちたことを話した。
安岡は何度も「信じられない」と言った。
「まさか芦田君が女を、しかも初心者を釣りに誘うなんて。いや、ありえないな。釣りはあいつにとってとても神聖なものなんだ」
言われてみればそうだ。長年連れ添った私でさえ、一度も誘われたことがない。
女の話は本当だろうか。
「ちょっと調べてみようか。釣り仲間に、何か事情を知っている奴がいるかもしれない」
安岡はそう言って帰って行った。
モヤモヤしながら季節はすっかり秋になり、鮎釣りの季節も終わりを告げた。
安岡が訪ねてきたのは、秋桜がだらしなく倒れた晩秋のことだ。
「奥さん、芦田君はやはり不倫なんかしてなかったよ。どうやらその女は、芦田君がたまに行くスナックの女だ」
安岡はそう言って写真を見せた。泣き顔しか見ていない女の、厚化粧の顔が写っていた。
「不幸な生い立ちの女で、芦田君は相談に乗ったり、酔って絡んでくる客から、彼女を助けたりしていたらしい。まあつまり、女がそれを愛だと、勝手に勘違いしたんだな」
それから女は、夫の会社を執拗に訪ねたり、帰り道を待ち伏せするようになった
あの釣りの日も、女が夫を尾行したのではないかと安岡は言った。
女が夫を突き落とし、釣った鮎を川に放ったのだとしたら……。
証拠はない。夫はもう骨になってしまった。
安岡が帰った後、夫の写真の前で初めて泣いた。
夏が来て、再び鮎釣りが解禁になった。
今日は夫の命日で、私は、あの川に来ている。
恐らく今日、女が花を手向けに来ると思ったからだ。
待ち伏せて、女が岩場に花束を置いたとき、思い切り背中を押してやる。
あの日から私は、そんなことばかり想像してきた。
やはり女はやってきた。大きな百合の花束を抱えている。
女はそれを岩場に置くと、私が近づくまでもなく、あっという間に川に身を投げた。
女は、夫の後を追ったのだ。
許せない。
夫の後を追って死ぬのが、あの女であってはならない。
私は大声で叫んだ。
「助けて。誰か助けて!」
後追い自殺など、させるものか。
「人が溺れています。誰か助けて!」
山間に響く大声で、私は助けを呼び続けた。
***********
公募ガイドTO-BE小説工房の落選作です。
課題は「鮎」です。難しい課題ですよね。
鮎の塩焼きは美味しいけれど、食べるの専門で釣りなんて行ったことないし。
やはり無理があったかもしれません。
にほんブログ村



